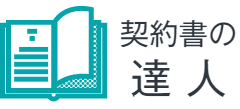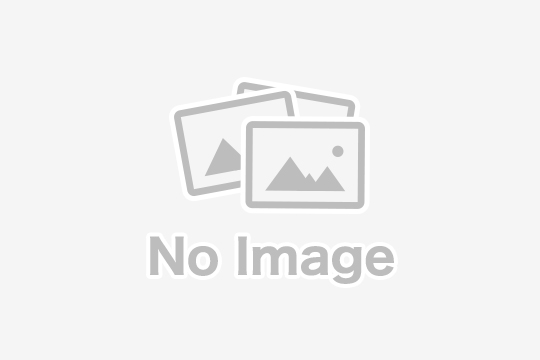契約書の雛形のニーズは非常に多いですが、その理由は、「無料だから」「安いから」という理由だと思われます。
他方で、法務部がある大手上場企業などでは、よほど作り込まれたものでない限り、無料の雛形はまず使いません。
なぜかといえば、一般的な無料の雛形では、リスクが高くてとても事業には使えないからです。
実際、無料の雛形は、特に企業間取引では実用できるものは非常に少なく、なんらかのリスクを抱えているものです。
このページでは、こうした無料の雛形のリスクについて、解説しています。
無料の雛形はメリットの割にリスクが多すぎる
無料の雛形はリスクが多すぎて使えない
コンプライアンスが徹底している企業では、契約書の作成やリーガルチェックは、法務部の主要な仕事となっています。
こうした企業では、無料の雛形を使うことはありません。
なぜかといえば、単純に、一般的な無料の雛形は、リスクが多すぎて使えないからです。
特に事業上の契約は、金額が多くなるため、いい加減な契約書では、それだけ損害のリスクも大きくなるため、余計に無料の雛形は使えません。
無料の雛形と専門家作成の契約書の違いは?
無料の雛形と専門家が作成した契約書では、メリット・デメリットともに、大きな違いがあります。
具体的には、次のとおりです。
| 無料の雛形 | 専門家作成の契約書 | |
|---|---|---|
| 費用・コスト | 無料 | 有料 |
| 作成時間 | そのまま使うのであれば時間はほぼかからない。 | ある程度作成に時間がかかる。 |
| 契約内容との合致 | 原理的に契約内容と雛形の内容が合致することは、偶然の一致以外あり得ない。 | 専門家が契約内容と契約書の記載内容を合致させてくれる。 |
| 表現の正確性 | 雛形によって様々。専門家や役所が作成した契約書は正確な表現であることが多い。 | 専門家が正確な表現にしてくれる。 |
| 適法性 | 雛形によって様々。そもそも、どの法律が適用されるか想定していない雛形では、違法となる可能性が高い。 | 専門家が適法な内容にしてくれる。 |
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
無料の雛形のメリット・デメリットは?
【メリット1】無料の雛形は「安い」
| 無料の雛形 | 専門家作成の契約書 | |
|---|---|---|
| 費用・コスト | 無料 | 有料 |
無料の雛形は、当然ながら、「安い」というメリットがあります。
まともな専門家に契約書の作成を依頼すると、安くても数万円はかかりますし、複雑な契約書であれば、案件によっては、数十万円以上となります。
依頼のしかたや、案件によって値段は様々ですが、専門家が作成するのに、さすがに無料というわけにはいきません。
逆にいえば、雛形の契約書を使ったところで、削減できる費用は、数万~数十万円程度でしかありません。
【メリット2】無料の雛形は時間がかからない
| 無料の雛形 | 専門家作成の契約書 | |
|---|---|---|
| 作成時間 | そのまま使うのであれば時間はほぼかからない。 | ある程度作成に時間がかかる。 |
無料の雛形は、すでに完成しているものを使うので、時間がかかりません。
これに対し、専門家が作成する契約書は、事前のヒアリングを含めて、それなりに時間がかかります。
もっとも、これは、あくまで雛形をそのまま使う場合であって、修正・調整する場合は、話は別です。
雛形の質によりますが、ヘタに修正・調整をすると、かえって一から作ったほうが早いような雛形もあります。
【デメリット1】無料の雛形は契約内容と合致していない
| 無料の雛形 | 専門家作成の契約書 | |
|---|---|---|
| 契約内容との合致 | 原理的に契約内容と雛形の内容が合致することは、偶然の一致以外あり得ない。 | 専門家が契約内容と契約書の記載内容を合致させてくれる。 |
無料の雛形は、特定の案件のために作成するものではありません。
このため、契約内容と雛形に記載された内容が合致することは、原理的にあり得ません。
もちろん、理論上、偶然の一致はあり得ます。
ただ、それは、契約内容と雛形の記載内容があまりにもあいまいなために、単にそのように「見える」だけの可能性もあります。
契約内容と雛形の内容がたまたま一致することはあり得る?
契約内容と雛形の記載内容が、両方ともあいまいで不明確な内容であれば、一見して一致しているように「見える」ことはあり得る。ただし、そのような状態で契約を締結しても契約書としては機能しない。
これに対し、専門家が作成する契約書は、専門家が、契約内容と契約書の記載内容を合致させてくれます。
実は、この点が、専門家に依頼して契約書を作成してもらう最大のメリットです。
契約書の専門家は、依頼者との打ち合わせを通じて、依頼者が気づいていない点をも引き出して、契約書に可視化・形式知化します。
専門家に契約書の作成を依頼する理由・目的
専門家に契約書の作成を依頼した場合、打ち合わせを通じて、依頼者が気づいていない契約内容を引き出し、契約書に規定することにより、契約内容の実態と契約書の記載を一致させることができるから。
【デメリット2】無料の雛形は表現が正確とは限らない
| 無料の雛形 | 専門家作成の契約書 | |
|---|---|---|
| 表現の正確性 | 雛形によって様々。専門家や役所が作成した契約書は正確な表現であることが多い。 | 専門家が正確な表現にしてくれる。 |
無料の雛形は、一般的な契約書の書き方の慣習やルールに従って正確に表現されているかどうかは、マチマチです。
通常、弁護士監修・作成の契約書や、役所が作成する契約書は、表現は正確なものが多いです(すべてがそうとは限りません)。
もっとも、仮に表現が正確な雛形であったとしても、記載内容が契約内容と一致していなければ、修正・調整しなければなりません。
この際、同じく慣習・ルールに従って正確に修正・調整しなければ、意図したものとは別の機能をする契約書になりかねません。
これに対し、専門家が作成した契約書は、契約書の書き方の慣習やルールに従い、しかも統一的な表現をしてくれます。
専門家に契約書の作成を依頼する理由・目的
専門家に契約書の作成を依頼した場合、慣習やルールに従った、正確な表現の契約書を作成してくれるから。
【デメリット3】無料の雛形は違法な場合がある
適法性雛形によって様々。そもそも、どの法律が適用されるか想定していない雛形では、違法となる可能性が高い。専門家が適法な内容にしてくれる。
| 無料の雛形 | 専門家作成の契約書 |
|---|
無料の雛形は、適用される法律を想定していれば適法なものといえます。
ところが、どの法律が適用されるか想定していない、または想定できない場合は、必ずしも適法なものとは限りません。
例えば、業務委託契約では、民法、商法のような、契約全般に適用される法律のほか、以下の法律が適用される可能性があります。
業務委託契約に適用される可能性がある法律
- 下請法
- 独占禁止法
- 建設業法
- 家内労働法
- 特定商取引法
- 資金決済法
- 著作権法
- 特許法
- 不正競争防止法
- 個人情報保護法
- 製造物責任法(PL法)
- 労働者派遣契約(実質的に労働者派遣契約だった場合=偽装請負の場合)
- 労働基準法(実質的に雇用契約・労働契約だった場合)
- 労働契約法(同上)
もちろん、こうした法律がすべて適用されることはありません。
ただ、どの法律が適用されるかは案件次第であり、これらの法律にすべて対応した雛形は、事実上作成することは不可能です。
これに対し、専門家が作成する雛形は、どのような法律が適用されるか、リーガルリサーチをしたうえで作成します。
専門家に契約書の作成を依頼する理由・目的
専門家に契約書の作成を依頼した場合、事前に徹底したリーガルリサーチをかけることにより、極力違法にならない契約書を作成してくれるから。
それですら、「漏れ」がある可能性はゼロではありませんが、少なくとも、雛形の契約書を使うよりは、遥かにリスクは低いです。
なお、代表的な契約に適用される法律を一覧にまとめましたので、詳しくは、次のページをご覧ください。
ポイント
無料の契約書の雛形を使ったところで、「安い・早い」しかメリットはない。しかも、削減できるコストは数万~数十万円程度。その代りに、大きなリスクを背負うことになる。
雛形の契約書を使ってはいけない理由は?
【理由1】いざとなったら頼れないから
このように、雛形の契約書は、さまざまなデメリットがあるため、少なくとも企業間取引では使ってはいけません。
特に、雛形の契約書は、トラブルや裁判になった場合には、機能しない可能性があります。
契約書にはいろんな機能がありますが、いい契約書は、裁判の際に証拠になり、そして裁判になることそのものを抑止してくれます。
しかし、こうした機能は、契約内容を忠実に反映した契約書だからこそ発揮できる機能であり、雛形の契約書では、それは望めない可能性が高いです。
これでは、本来は発生しないトラブルや、勝てるはずの裁判にも、対応できなくなります。
【理由2】相手方に不都合な事実が見透かされるから
また、雛形の契約書の中には、契約実務の慣例やルールに従っておらず、書式や表現が統一されていなかったり、間違っていたりするものがあります。
こうした表現のミスは、専門家がチェックするとすぐにバレるものです。
その結果、以下のような「不都合な事実」を相手方に伝えることになります。
雛形を使うことで相手方に伝わる「不都合な事実」
- 雛形を使わざるを得ない事情がある。
- 専門家に契約書の作成を依頼する意識・お金がない。
- 社内に契約書を作成・チェックできる人材がいない。
- コンプライアンス=法令遵守の体制が不十分である。
- 法務部門に対する投資をしていない。
こうした「不都合な事実」は、雛形の契約書を使っていては、取り繕うことはできません。
結果として、相手方からは、「コンプライアンスの体制に問題がある可能性があり、取引先としては不適当である」と判断されかねません。
【理由3】知らず知らずのうちに違法行為をしてしまうから
さらに、雛形の契約書は、必ずしも適法なものとは限りません。
契約内容とともに、使う雛形の契約書も併せて適法性を確認しなければ、知らず知らずのうちに、違法行為をしてしまうことになります。
法律の中には、契約書の書き方ひとつで、罰則付きの違法行為となる法律もあります(下請法、特定商取引法など)。
このため、雛形の契約書を使う場合は、適法な内容となっているかどうか、慎重に確認し、場合によっては修正・調整しなければなりません。
ポイント
- 雛形の契約書では、トラブルになった場合や裁判になった場合などには、まともに機能しない=いざとなったら頼れないリスクがある。
- 雛形の契約書を使うと、「不都合な事実」を相手方に伝えてしまうことになる。
- 法律の中には、契約書の記載内容や表現についても細かい規制があるものもあるため、雛形の契約書を使うと、知らず知らずのうちに法律違反となることがある。