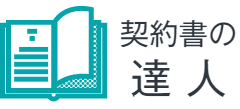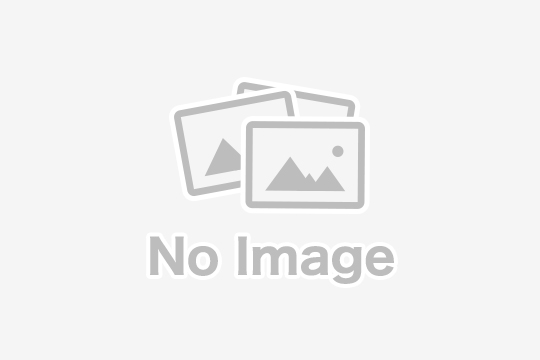協議事項とは、「甲乙協議のうえ決定する」、「協議する」と規定された契約条項の中で、協議対象となった事項のことです。
また、協議条項とは、これらの協議事項を規定した条項です。
協議事項が多い契約書は、本来は決めるべき契約内容を決めていない契約書であり、非常に問題が多い「ダメな契約書」の典型例です。
このため、なるべくこうした協議事項となっている条項については、契約締結前に、さらに交渉を重ねて、内容を決めるべきです。
このページでは、こうした協議事項や協議条項の問題点について、わかりやすく解説します。
なお、協議事項・協議条項そのものの解説や具体例につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
協議事項・協議条項=何も決まっていない
「協議」の数と契約書の質は反比例
管理人は、契約書のリーガルチェックをする際に、最初に「協議」の数を調べます。
使うソフトやファイルの種類にもよりますが、たいていは、「Ctrl+F5」で検索できます。
実は、「協議という言葉の数が多い契約書は質が低い」という傾向があります(ただし、少ないほうが質が高い、とは限りません)。
協議だらけの契約書
協議事項が多い契約書は質が低い。
「協議」の数が1つだけ、しかも文末の誠実協議条項(後ほど解説します)だけであれば、特に問題ではありません。
ところが、「協議」の数が5つや、6つ、あるいは10以上ともなると、チェックする前から閉口してしまいます。
契約書は「協議」の後に作る書面
なぜこれほど協議事項・協議条項が問題なのかといえば、そもそも、契約書には協議事項・協議条項がなくて当たり前だからです。
契約書は、交渉を重ねて、協議した結果について言語化した書面です。
このため、すべての協議事項・協議条項について、あらかじめ結論を出したうえで、契約書を作成するべきなのです。
契約書に協議事項・協議条項がある「矛盾」
契約書は協議が終わった後に作るもの。そもそも契約書に協議事項・協議条項があることは矛盾している。
つまり、協議事項・協議条項は、立派な契約条項でもなんでもなく、本来決定するべき事項について、棚上げしているだけなのです。
ポイント
- 協議事項・協議条項は、協議するための条項ではなく、何も決まっていない条項。
- 「協議」の数が多いほど、契約書の質は悪くなる。
- 契約書は「協議」の後に作る書面であるため、そもそも協議事項・協議条項があること自体、矛盾している。
協議事項・協議条項は規定する意味がない
協議事項・協議条項はあってもなくても法的効果は変わらない
また、協議事項・協議条項を規定した契約条項は、あってもなくても、ほとんど意味がありません。
例えば、次のような条文があったとしましょう。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】第三者に発生した損害に関する条項
第○条(第三者の損害)
工事の施工により、第三者が損害を受けた場合、当該損害にかかる賠償金の負担については、甲および乙は、協議のうえ、決定するものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
これは、建設工事請負契約の条項の例です。ちなみに、この内容については、建設工事請負契約書に規定することが義務づけられています(建設業法第19条第1項第8号)。
このような内容の条項であれば、内容が何も決まっていませんから、規定する意味がありません。
また、仮にこうした条項がなかったとしても、工事の施行で第三者に損害が発生したにもかかわらず、契約書に条項がないからといって、協議すらしない、ということはあり得ません。
トラブルになったら協議するのが当たり前
こうしたことは、建設工事請負契約に限った話ではありません。
どんな契約であれ、トラブルになった場合、契約書の協議事項・協議条項がなくても、協議くらいはするものです。
または、契約書に協議事項・協議条項があっても、協議ができないほど、信頼関係が破綻しているかの、いずれかでしょう。
このように、トラブルの対策という意味でも、協議事項・協議条項は、意味がありません。
規制の対処や戦略的意図で協議事項とすることもある
もちろん、各種法律による規制によって、あるいは、ある種の戦略的意図で、わざわざ協議のかたちを取る条項もあるにはあります。
前者の例では、ライセンス契約や知的財産権の利用がともなう製造請負契約における、改良発明の規定があります。
改良発明の規定では、ヘタに改良後の技術に関する知的財産権の帰属・移転についてあらかじめ決めてしまうと、独占禁止法違反(アサインバック・グラントバック)となることがあります。
【意味・定義】アサインバック・グラントバックとは?
- アサインバックとは、改良発明があった場合、その権利を注文者=ライセンサーに帰属させる義務をいう。
- グラントバックとは、改良発明があった場合、その権利を注文者=ライセンサーに独占的にライセンスさせる義務をいう。
ですが、こういうパターンは、極めてまれなパターンです。
また、戦略的意図的で協議事項・協議条項を設定するのは、高度な専門知識や経験が必要となりますし、よほどうまく交渉しないことには、最終的に良い方向にまとまらないリスクがあります。
ポイント
- 協議事項・協議条項は、契約条項としては規定する意味がない。
- 協議事項・協議条項は、あってもなくても法定効果は変わらない。
- トラブルになったら協議事項・協議条項があってもなくても、協議するのが当たり前。
- あえて意図的に協議事項・協議条項を設定するのは、極めて稀なケース。
協議事項・協議条項が多い=トラブルのリスクが高い
リスクがあることを知りながら棚上げするべきではない
このように、協議事項・協議条項は、あってもなくても、特に法的にはほとんど意味はありません。
ただ、協議事項・協議条項が多いということは、その協議事項・協議条項の対象となっていること自体は、契約当事者が把握していることを意味しています。
つまり、協議事項・協議条項が多いということは、問題点が多いことを知りつつ、その問題点を棚上げにして契約を締結していることになります。
リスクがあるのが分かっていながら、対応をせずに契約を締結するのは、特に企業間の契約では避けるべきです。
特に枚数が多い契約書では要注意
特に、契約書の枚数が多く、そのうえで協議事項・協議条項が多い契約書は、警戒するべきです。
こうした枚数が多い契約書は、契約内容が複雑であることが多いものです。
そうした複雑な契約であるうえ、協議事項・協議条項が多いとなると、相当のリスクについて棚上げしていることを意味します。
こうした契約書は、契約の締結の前後にかかわらず、できるだけ追加で交渉を重ねて、協議事項・協議条項を減らすべきです。
なお、企業間契約において、契約書の枚数が少ないという理由で、協議事項・協議条項が少ないのは、そもそも契約全体についての検討が甘いので、論外です。
ポイント
- 協議事項が多いということは、「リスクがあることを知りながら棚上げしている」ということ。
- 特に枚数が多い契約書で協議事項が多いということは、それだけ、質・量ともに問題が多い契約であるということ。
誠実協議条項は無意味
また、協議事項・協議条項と似た契約条項として、契約の最後の条項に、いわゆる「誠実協議条項」が規定されることもあります。
誠実協議条項とは、主に契約の最後 に規定される、契約当事者の双方に誠実な協議を義務づける条項です。
【意味・定義】誠実協議条項とは?
誠実協議条項とは、契約についてトラブルや解釈に関する疑義が生じた場合に、契約当事者の双方に対し、誠実に協議をするよう義務づけた条項をいう。
具体的には、以下のような規定となります。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】誠実協議条項
第○条(協議)
本契約に定めない事項もしくは本契約の条項の解釈について疑義を生じた場合または本契約について紛争が生じた場合、甲および乙は、誠実に協議のうえ、解決するものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
この誠実協議条項は、法的には(特に民法上)当然のことが規定されているものであり、効果がありません。
この他、誠実協議条項の法的な効果につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。