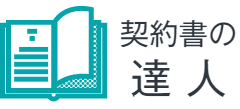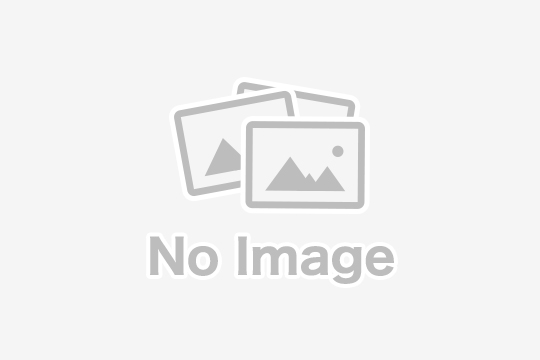このページでは、問題が多い契約書を見抜くコツとして、非論理的な契約条項の問題点について、解説しています。
契約書は、契約当事者の権利義務について、正確に記載しなければなりません。
このため、契約条項の文章も、論理的に記載する必要があります。
逆に、契約条項の文章が非論理的な場合、その契約条項は、内容が理解できず、どのような効果となのかがはっきりしません。
こうした非論理的な契約条項が規定されているのは、典型的な「ダメな契約書」です。
このページでは、こうした非論理的な契約条項の問題点について、解説します。
契約書の契約条項は正確に記載する
契約書はプログラム言語のような精密さで書くべき
本来、契約書の文章は、機械言語≒プログラム言語のように、緻密な論理で記載するものです。
契約書には、様々な目的がありますが、そのひとつが、契約内容という「事実」を記録しておくことです。
当然ながら、この事実は、正確に、かつ一義的に解釈できるように記載されなければなりません。
この際、重要となるのは、誰が見ても同じ解釈となるよう記載されているかどうかです。
事情を知らない第三者にも理解できる記載とする
契約書は、実際に契約交渉にあたった担当者だけが読むものではなく、多くの人が目を通します。
トラブルや裁判になった場合、弁護士や裁判官などが目を通します。
また、大企業のように、契約の担当者が頻繁に変わる場合、いろんな担当者が目を通すことになります。
このように、契約書は、当事者だけではなく、第三者を含めた多くの人の目に触れるものです。
このため、特に事情を知らない第三者が読んでも一義的な解釈ができるよう、論理的に記載する必要があります。
ポイント
- 契約書は、プログラム言語のように、精密で論理的な記述で書くべき。
- 契約書は、事情を知らない第三者、特に弁護士や裁判官が一義的に理解できるように書くべき。
非論理的な契約条項の具体例
非論理的な契約条項として、よくあるパターンがいくつかありますので、紹介します。
非論理的な契約条項のパターン
- 主語が抜けている
- 定義条項で用語と定義が循環している
- 指示語が明らかでない
以下、それぞれ具体的な文例を見てみましょう。
【文例1】主語が抜けている
主語が抜けている契約条項の具体例は?
【契約条項の書き方・記載例・具体例】技術指導に関する条項
第○条(技術指導)
本件製品の品質の向上のために必要なものと認めた場合、技術指導を求めることができるものとする。
(※製造業務委託契約の場合。便宜上、表現は簡略化しています)
この文章では、2箇所、主語が抜けています。
つまり、「必要なものと認めた」の部分と、「…求めることができるものとする。」の部分です。
ついやりがちな「必要なものと認めた場合」
1つ目の、「必要なものと認めた」という表現は、非常に便利なため、よく使われる表現です。
ただ、この表現で主語が抜けた場合、契約当事者のどちらが「認めた」場合なのかが、はっきりとしません。
ただでさえ、「必要と認めた」という表現は、恣意的に解釈されるリスクが高い表現です。
にもかかわらず、主語が規定されていなければ、誰が「必要と認めた」のかを巡って、トラブルの原因となります。
権利義務に関する規定では主語を必ず規定する
2つ目の、「…できるものとする。」という表現は、権利を意味する表現です。
同時に、この文例では、発注者の側が技術指導をすることを意味しますので、技術指導の実施そのものは、発注者の義務といえます。
問題は、この技術指導の請求が、誰の権利なのかが、明記されていません。
このような技術指導の条項は、発注者が受注者に対してできる権利とも解釈できますし、逆に、受注者が発注者に対してできる権利とも解釈できます。
主語が抜けているために4パターンの解釈が成り立つ
このように、2箇所の主語が抜けているため、以下の契約条項は、4パターンに解釈できます。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】技術指導に関する条項
第○条(技術指導)
本件製品の品質の向上のために必要なものと認めた場合、技術指導を求めることができるものとする。
(※製造業務委託契約の場合。便宜上、表現は簡略化しています)
4パターンの解釈
- 【パターン1】発注者が製品の品質が低いと認め、発注者が受注者に対し、技術指導を求めることができるパターン。
- 【パターン2】受注者が製品の品質が低いと認め、発注者が受注者に対し、技術指導を求めることができるパターン。
- 【パターン3】発注者が製品の品質が低いと認め、受注者が発注者に対し、技術指導を求めることができるパターン。
- 【パターン4】受注者が製品の品質が低いと認め、受注者が発注者に対し、技術指導を求めることができるパターン。
製造業務委託契約であり得る代表的なパターンは、パターン1とパターン4です。
ただ、パターン2やパターン3も、発注者と受注者の関係性によっては、あり得るパターンです。
蛇足ながら、この規定では、技術指導の費用負担についても明記されていませんので、実際には、さらに複雑な問題となります。
このほか、契約書の主語の書き方につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
ポイント
- 「必要と認めた場合」という表現は、主語が抜けがち。
- 権利義務に関する規定では、主語を必ず規定して、誰の権利義務なのかをハッキリさせる。
【文例2】定義条項で用語と定義が循環している
「知的財産権」とは知的財産権?
【契約条項の書き方・記載例・具体例】定義に関する条項
第○条(定義)
本契約において、「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、当社が提供するむ文書、データベース、ウェブサイト、グラフィック、ソフトウェア、アプリケーション、プログラム、コード等に関連するすべての権利、その他の知的財産権をいう。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
一見して、何ら問題がない定義に見えますが、「知的財産権」の定義なのに、文末にその「知的財産権」という表現があります。
これは、典型的な一種の循環論法であり、定義になっていません。
せめて「その他知的財産権という」にするべき
「その他の~」はあくまで例示の列挙に過ぎない
しかも、「その他の知的財産権」となっています。
「その他の~」という表現は、前に規定されているものは、あくまで例示とする表現です。
このため、「その他の知的財産権」の前に規定されている権利が知的財産権に含まれるかどうかも、解釈が分かれる可能性があります。
もちろん、これはあくまで理論上の話であり、実際に裁判になった場合は、「著作権はあくまで例示に過ぎず、この知的財産権には含まれない」という主張は、おそらく通りません。
「その他~」は並列的列挙
これに対し、「その他~」という表現は、前に規定されているものは、並列的に規定するものです。
このため、「その他知的財産権」とした場合は、その前に規定された具体的な権利については、少なくともこの(定義づけられるほうの)「知的財産権」の定義には確実に含まれます。
つまり、(定義づけるほうの)「知的財産権」の定義が何であれ、「その他知的財産権」とした場合は、その前の権利については、(定義づけられるほうの)「知的財産権」となります。
この点から、少なくとも、この文例では、「その他知的財産権」としたほうが、まだマシな規定であるといえます。
知的財産権は法律での定義がある
蛇足ですが、「知的財産権」という用語は、知的財産基本法に定義があります。
知的財産基本法第2条(定義)
1 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
3 (省略)
このため、この文例の「知的財産権」は、知的財産基本法第2条第2項で定義づけられている「知的財産権」との関係も明らかではありません。
こうした点も、当事者の用語の解釈に影響を与える可能性があります。
この点からも、この文例は、用語の定義としてはふさわしくない、非論理的な契約条項といえます。
ポイント
- 定義規定では、循環論法とならないよう、その文章だけで完結するように定義を記述する。
- すでに法律で定義づけられた用語がある場合は、その用語との関係性についても、定義づけるべき。
【文例3】指示語が明らかでない
「この限りではない」は「何の」限りはでない?
第41条(秘密情報の取扱い)
1 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後○日以内に書面により内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情報」という。)を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲及び乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
(1)秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)本契約及び個別契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(以下省略)
引用元:モデル取引・契約書<第一版>(PDF形式:4350KB) – 経済産業省(リンク切れ)
「この限りではない。」という表現は、例外を規定する表現です。
この表現自体は、特に問題があるわけではなく、法律や契約書では、よく使われる表現です。
問題は、「この限りではない」が、何の例外なのかが、必ずしも明らかでない場合があります。
秘密保持義務の例外か秘密情報の例外か
上記の文例では、前段の本文で、秘密保持の定義と秘密保持義務を規定しています。
わかりやすく下線部を引きます。
第41条(秘密情報の取扱い)
1 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後○日以内に書面により内容を特定した情報(以下あわせて「秘密情報」という。)【1】を第三者に漏洩してはならない。【2】但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲及び乙は秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
(1)秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)本契約及び個別契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(以下省略)
引用元:モデル取引・契約書<第一版>(PDF形式:4350KB) – 経済産業(リンク切れ)
【1】の部分が秘密情報の定義であり、【2】が秘密保持義務の定義です。
このように、一文の中に2つの内容が規定されているため、「この限りではない。」が、秘密情報の例外なのか、秘密保持義務の例外なのか(あるいは両方の例外?)必ずしも明らかではありません。
秘密情報の例外か秘密保持義務の例外かで目的外使用の禁止の内容が変わる
こうしたただし書きの規定では、秘密情報の目的外使用の禁止の解釈にも影響を与えます。
通常、目的外使用の禁止の内容では、「秘密情報」の目的外使用を禁止します。
このため、ただし書きの解釈が秘密情報の例外と秘密保持義務の例外では、次のように意味が変わってきます。
秘密情報の例外・秘密保持義務の例外の違い
- 秘密情報の例外の場合:例外とされた情報は、秘密情報ではないため、秘密保持義務の対象外であり、かつ、目的外使用ができる。
- 秘密保持義務の例外の場合:例外とされた情報は、秘密保持義務の対象外だが、秘密情報ではあるため、目的外使用ができない。
つまり、秘密保持義務の例外と解釈された場合、秘密情報の受領者は、秘密情報の開示者から開示をうけた情報については、たとえすでに保有している情報であっても、理論上は目的外使用ができなくなります。
ポイント
- 「この限りではない」の表現を使う場合は、「何の」限りでないのかについて、解釈が分かれないようにする。
- どうしても必要な場合を除いて、なるべく「この限りではない」は使わない。