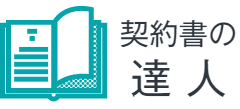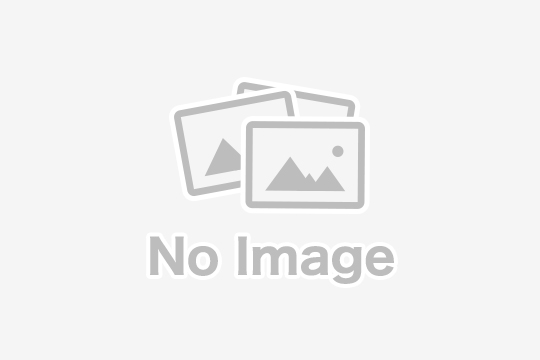善管注意義務とは、正式には「善良な管理者の注意義務」といいます。
善管注意義務は、一定の契約で契約当事者に課される義務で、代表的なものとしては、委任契約・準委任契約の受任者に課されます。
受注者が善管注意義務に違反した場合は、いわゆる債務不履行=契約違反となります。
ただ、善管注意義務は、客観的な定義が決まっていないため、実際の契約実務では、非常に扱いが難しい条項です。
このページでは、こうした善管注意義務のポイントについて、解説します。
【意味・定義】善管注意義務とは?
善管注意義務の定義は非常にあいまい
善管注意義務は、正式には「善良な管理者の注意義務」といい、一般的に、次のような意味となります。
【意味・定義】善管注意義務とは?
善管注意義務とは、行為者の階層、地位、職業に応じて要求される、社会通念上、客観的・一般的に要求される注意を払う義務をいう。
ただし、この定義は、民法をはじめ、法律の条文で規定されているものではありません。
つまり、善管注意義務には、必ずしも客観的な基準や定義があるわけではありません。
この点が、契約実務では、非常に厄介な点です。
善管注意義務を分かりやすくかんたんに言えば?
なお、善管注意義務をあえてわかりやすく表現すれば、次のようになります。
善管注意義務をわかりやすく言えば?
善管注意義務は、義務を負う人・会社が、「ちゃんとしなければならない」義務。
この「ちゃんとしている」かどうかは、契約内容や、義務を負う人・会社によって異なります。
このため、どの程度「ちゃんとしているか」、つまり善管注意義務を果たしているか、それとも善管注意義務に違反するかは、個別具体的な状況によります。
委任契約・準委任契約等で課される善管注意義務
善管注意義務は、一部の契約で契約当事者に課される義務です。
最も典型的なものとしては、委任契約・準委任契約で、受任者に課されます。
民法第644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
この他、商事寄託において、受寄者に善管注意義務が課されています(商法第595条)。
第595条(受寄者の注意義務)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
引用元:商法 | e-Gov法令検索
善管注意義務は契約の過程についての責任・義務
一般的な企業間契約における善管注意義務は、すでに触れた委任契約・準委任契約で重要となります。
こうした委任契約・準委任契約や、委任型・準委任型の業務委託契約では、受任者・受託者は、善良な管理者の注意をもって、契約を履行します。
これはどういうことかというと、受任・受託した一定の行為の実施そのもの(=過程)について責任を負う、ということです。
逆にいえば、行為を実施した結果については、責任を負う必要はありません。
この点が、仕事の結果に対してのみ責任を負う、請負契約の責任と違うところです。
ポイント
- 善管注意義務とは、行為者の階層、地位、職業に応じて要求される、社会通念上、客観的・一般的に要求される注意を払う義務のこと。
- 善管注意義務は、委任契約・準委任契約・商事寄託契約などで受任者・受寄者に課される義務。
- 善管注意義務は、契約の過程についての責任・義務であり、結果についての責任ではない。
善管注意義務の具体例(医療・弁護士・IT関係・コンサル契約等)
4種類の善管注意義務の具体例
一般的な(準)委任契約の事例としては、次のようなものがあります。
善管注意義務が課される契約の具体例
- 医師による医療行為に関する契約
- 弁護士による訴訟代理契約
- IT関係(アジャイル型開発契約・SES契約)
- コンサル契約(経営コンサルタント契約・経営コンサルティング契約)
医師による医療行為に関する契約
医師による医療行為に関する契約は、準委任契約です。
医師による医療行為により、診察・診療がおこなわれた場合、結果として患者が死亡することがあります。
この場合であっても、善管注意義務さえ果たしていれば、医師は、責任を負うことはありませんし医療報酬を受取ることもできます。
他方で、善管注意義務を果たしていなければ、いわゆる「医療過誤」となります。
この場合、医師は、善管注意義務違反つまり債務不履行(いわゆる契約違反)となり、損害賠償責任等を負うこととなります。
弁護士による訴訟代理契約
弁護士の善管注意義務とは
弁護士による訴訟代理は、委任契約です。弁護士による訴訟代理により、結果として裁判に敗訴することがあります。
この場合であっても、善管注意義務さえ果たしていれば、弁護士は、責任を負うことはありませんし、弁護士報酬を受取ることもできます(成果報酬の場合は別です)。
他方で、善管注意義務を果たしていなければ、弁護士は、善管注意義務違反つまり債務不履行(いわゆる契約違反)となり、損害賠償責任等を負うこととなります。
弁護士以外の士業の善管注意義務
弁護士以外のいわゆる「士業」の場合であっても、同様に善管注意義務が課されます(一部の業務を除きます)。
善管注意義務が課される士業の具体例
- 公認会計士
- 弁理士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 行政書士
なお、これらを含む士業は専門性が高いため、一般的な事業者の善管注意義務と比べて、より高度な善管注意義務が課される傾向があります。
IT関係(アジャイル型開発契約・SES契約)
(準)委任型のソフトウェア・システム・アプリなど、IT関連の開発業務委託契約、特にアジャイル型開発のものでは、善管注意義務が課されます。
また、いわゆる常駐型でコーディングやプログラミングの行為そのものを提供するシステムエンジニアリングサービス契約(SES契約)でも、善管注意義務が課されます。
なお、これらの契約は、請負契約ではないため、原則として、システム等の完成については責任を負いません。
コンサル契約(経営コンサルタント契約・経営コンサルティング契約)
経営コンサルタント契約・経営コンサルティング契約なども、一部の例外(成果物の作成があるもの)を除くと、多くが(準)委任契約となります。
このため、経営コンサルタントには、一定の善管注意義務が課されます。
経営コンサルタントの業務は多岐にわたりますが、基本的には、経営者や依頼者に対し、知識、情報、ノウハウ等を提供することとなります。
この提供される知識、情報、ノウハウが間違っている場合は、善管注意義務違反に該当する可能性があります。
ポイント
- 医師は、医療行為の実施そのものに善管注意義務を負うため、結果的に患者が死亡しても、その患者の死亡について責任を負わない。
- 弁護士は、訴訟行為の実施そのものに善管注意義務を負うため、結果的に敗訴しても、その敗訴について責任を負わない。
- 準委任型のシステムエンジニアリングサービス契約(SES契約)のベンダやアジャイル型開発のシステム等の開発契約は、システム等の開発行為の実施そのものに善管注意義務を負うため、結果的にシステム等の開発が失敗し、完成しなくても、その失敗について責任を負わない。
- 経営コンサルタントは、経営者や依頼者に対する知識、情報、ノウハウ等の提供そのものに善管注意義務を負うため、その成果について責任を負わない。
善管注意義務違反=債務不履行
善管注意義務違反は損害賠償請求や契約解除の原因となる
(準)委任契約では、受任者が善管注意義務を果たしているかどうかが、契約を履行しているかどうかの判断基準となります。
つまり、善管注意義務に違反しているということは、契約違反となります。
より正確には、債務不履行のうちの「不完全履行」(改正民法第415条)となります。
このため、善管注意義務違反があった場合、委任者は、受任者に対し、損害賠償の請求(改正民法第415条)ができますし、契約の解除(改正民法第541条)もできます。
「ちゃんとやっている」かどうかの判断が難しい
このように、理屈のうえでは、善管注意義務違反があった場合は、委任者は、損害賠償の請求や契約の解除ができます。
ただ、すでに述べたように、善管注意義務の定義自体が、非常に曖昧です。
このため、受任者が実際に善管注意義務を果たしているのか、あるいは違反しているのかは、客観的に判断するのは難しいと言わざるを得ません。
委任契約の例でわかりやすく言えば、受任者が受任内容を「ちゃんとやっているのか」「ちゃんとやっていないのか」は、簡単には判断がつかない、ということです。
ポイント
- 善管注意義務違反は契約違反=債務不履行。よって、損害賠償請求や契約解除の原因となる。
- 受任者が「ちゃんとやっている」のかどうかの判定は難しい。
(準)委任契約の目的に適した行為をする義務
【意味・定義】「委任の本旨に従い」とは?
(準)委任契約では、「委任の本旨に従い、」委任事務を処理しなければなりません。
民法第644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
この「委任の本旨に従い」とは、次のような意味です。
【意味・定義】「委任の本旨に従い」とは?
「委任の本旨に従い」とは、(準)委任契約の目的に適した事務処理をすることをいう。
言われたとおりにやるだけでは善管注意義務違反となることも
(準)委任契約は、委任者と受任者との信頼が基本となる契約です。
このため、受任者は、委任者の信頼に応えるため、「委任の本旨に」反しない程度に、自由裁量をもって事務処理ができます。
逆に言えば、例えば、委任者からの指図があった場合、その指図が間違っていなければ、その通りに処理するべきです。
ただ、委任者からの指図が間違っていた場合は、その間違いを指摘したり、指図の変更を求めたりしなければ、善管注意義務違反となる可能性もあります。
(準)委任型の業務委託契約では業務内容にない行為もできる
また、委任者からの指図が間違っている場合は、その指図に従わずに、臨機応変に対応することもできます。
特に、企業間取引である(準)委任型の業務委託契約では、商法第505条にもとづき、業務内容に規定されていないこともできます。
商法第505条(商行為の委任)
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
引用元:商法 | e-Gov法令検索
もちろん、この規定にあるとおり、「委任の本旨に反しない範囲内」に限定されています。
ポイント
- (準)委任型の業務委託契約では、受任者は、契約の目的に適した業務実施・業務処理をしなければならない。
- (準)委任型の業務委託契約では、委任者から間違った指示があった場合、受任者がそのまま指示に従うと、善管注意義務違反となることもある。
- (準)委任型の業務委託契約では、受任者は、業務委託契約の目的に適した範囲内で、業務内容にない行為もできる。