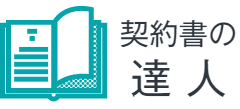準拠法とは、その契約に適用させる法律を決める契約条項です。
国内取引の契約ではあまり重要ではありませんが、国際取引の契約では非常に重要となる契約です。
このページでは、このような準拠法のポイントについて、解説します。
準教法はできるだけ自国の法律とする
準拠法は国際取引で適用される法律を決める条項
準拠法は、国際取引で問題となる特約です。
一般的な日本国内での取引の契約では、日本法が適用されます。
これに対し、海外との企業や消費者との国際取引では、どこの国の法律が適用されるかは、契約内容によって様々です。
もっとも、契約によって合意した場合は、その合意した法律を契約に適用させることができます(法の適用に関する通則法第7条)。
法の適用に関する通則法第7条(当事者による準拠法の選択)
法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
準拠法は自国の法律のほうが有利
実務上、準拠法を規定する場合は、できるだけ、自国側の法律を規定するようにします。
例えば、日本の法律を準拠法とする記載例は、次のとおりです。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】準拠法に関する条項
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
準拠法を自国の法律にする理由は、次のとおりです。
準拠法を自国の法律にするべき理由
- 裁判の手続きがしやすい(ただし、合意管轄裁判所も自国の裁判所の場合に限る)
- 法律の情報を入手しやすい
- 弁護士の手配・準備がしやすい
- 制度・情報に馴染みがある
もちろん、これは、相手方にとっても同じことです。
このため、準拠法は、利害が完全に対立する条項でもあります。
契約書を作成する理由・目的
国際取引においては、準拠法を規定しておかないと、自社にとって必ずしも有利な準拠法で契約内容を解釈されるとは限らないため、自社にとって有利な準拠法を規定した契約書が必要となるから。
国際取引の契約では準拠法を最初に決める
通常、こうした利害が完全に対立する条項については、契約交渉の最初の段階で、合意するものです。
利害が対立する条項の合意を最後に先延ばししてしまうと、まとまりかけた契約交渉が暗礁に乗り上げる可能性があります。
これは、合意管轄裁判所についても同様です。
このため、国際取引の契約では、準拠法と合意管轄裁判所いついて最初に交渉することが多いといわれています。
ポイント
- 準拠法は、主に国際取引で適用される法律を決める条項。
- 準拠法は、自国の法律のほうが有利であるため、なるべく自国の法律とする。
- 国際取引の契約では、利害が対立する準拠法と合意管轄裁判所を最初に決める。
準拠法は合意管轄裁判所とセットで規定する
準拠法と合意管轄裁判所は一致させる
準拠法は、必ず合意管轄裁判所とセットで規定します。
理屈のうえでは、準拠法の国と裁判所の国が異なっていても、裁判自体は、おこなわれます。
例えば、アメリカのニューヨーク州の法律を準拠法として、日本の東京地方裁判所を合意管轄裁判所とした場合は、ニューヨーク州法にもとづいて、東京地裁で裁判がおこなわれます。
ただ、これでは、日本の裁判官が、よく知らないニューヨーク州法にもとづいて判決を下さなければならなくなります。
このようなことを避けるためにも、準拠法と合意管轄裁判所の国を一致させるようにします。
準拠法と合意管轄裁判所は強制執行まで視野に入れる
なお、仮に裁判に勝った場合であっても、必ずしも、その確定判決にもとづいて強制執行ができるとは限りません。
トラブルを解決するための裁判と、その裁判による確定判決にもとづく強制執行とは、別物の手続きです。
例えば、日本と中国の関係では、裁判所の確定判決があっても、相手国では、その確定判決にもとづく強制執行はできません。
ですから、どこの法律を基準にどこ国の裁判所に裁判を起こすかは、裁判の後の強制執行を視野に入れたうえで検討しなければなりません。
上記の日中の例の場合は、仲裁を活用する方法も検討するべきです。
実務上も、日本の企業と中国の企業との契約の紛争処理については、仲裁によって解決するように規定することが多いようです。
ポイント
- 準拠法は合意管轄裁判所とセットで規定し、必ず国を一致させる。
- 準拠法と合意管轄裁判所を決める際は、強制執行がしやすいかどうかまで視野に入れる。
- 強制執行が難しいようであれば、仲裁による紛争解決も検討する。
準拠法を規定していない場合の取扱いは?
国内取引の場合は通常は日本法が適用される
準拠法の規定がない場合は、法の適用に関する通則法にもとづいて解釈されます。
この点について、契約当事者の所在地、契約締結の場所、契約を履行する場所など、契約に関係する場所がすべて日本国内である場合は、当事者間で別段の合意でもない限り、次のとおり、日本国の法律が適用されます。
法の適用に関する通則法第8条(当事者による準拠法の選択がない場合)
1 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
3 第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
海外の消費者との取引きには外国法が適用される場合もある
また、海外の消費者との取引の場合は、準拠法を定めた場合であっても、また、定めなかった場合には、次のとおり準拠法が適用されます。
準拠法が「消費者の常居所地法以外の法」の場合
契約の方式について「消費者契約の方式について消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、」専らその強行規定による。(法の適用に関する通則法第11条第3項)
| 契約の成立・効力・方式の別 | 効果 |
|---|---|
| 契約の成立・効力について | 「消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、」準拠法と常居所地法の強行規定を両方(=重畳的に)適用する(法の適用に関する通則法第11条第1項)。 |
準拠法が決まっていない場合
| 契約の成立・効力・方式の別 | 効果 |
|---|---|
| 契約の成立・効力について | 「消費者の常居所地法による。」(法の適用に関する通則法第11条第2項) |
| 契約の方式について | 「消費者の常居所地法による。」(法の適用に関する通則法第11条第5項) |
準拠法の取扱いの例外
なお、これらの規定には、例外があります(法の適用に関する通則法第11条第6項)。
法の適用に関する通則法第11条第6項(消費者契約の特例)
(第1項から第5項まで省略)
6 前各項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1)事業者の事業所で消費者契約に関係するものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在した場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地に赴いて当該消費者契約を締結したとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地において消費者契約を締結することについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。
(2)事業者の事業所で消費者契約に関係するものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在した場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地において当該消費者契約に基づく債務の全部の履行を受けたとき、又は受けることとされていたとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地において債務の全部の履行を受けることについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。
(3)消費者契約の締結の当時、事業者が、消費者の常居所を知らず、かつ、知らなかったことについて相当の理由があるとき。
(4)消費者契約の締結の当時、事業者が、その相手方が消費者でないと誤認し、かつ、誤認したことについて相当の理由があるとき。
海外の労働者との労働契約には外国法が適用される場合もある
海外の労働者との労働契約では、準拠法として、「労働契約に最も密接な関係がある地の法(=密接関係地法)以外の法」を定めた場合であっても、労働者が、密接関係地法の「特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、」その「労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する」(重畳適用)とされています(法の適用に関する通則法第12条第1項)。
ここでいう「労働契約に最も密接な関係がある地の法」は、「当該労働契約において労務を提供すべき地の法(その労務を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。)」であると推定されます(法の適用に関する通則法第12条第2項)。
また、準拠法の規定がない場合は、「労働契約に最も密接な関係がある地の法」が準拠法とされます(法の適用に関する通則法第12条第3項)。
つまり、労働契約については、準拠法を規定したとしても、その労働者の就業場所・事業所の法律(ただし、強行規定)が最優先で適用されます。
また、準拠法の規定がない場合も同様です。
ポイント
- 準拠法を規定していない場合であっても、一般的な国内取引の場合は、通常は日本法が適用される。
- 海外の消費者との契約の場合は、準拠法の規定があっても、海外の消費者の常居所地の法律が適用される場合もある。
- 海外の労働者との労働契約の場合は、準拠法の規定があっても、労働者の就業場所・事業所の法律(強行規定)が優先的に適用されることもある。