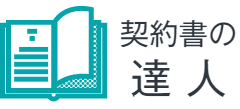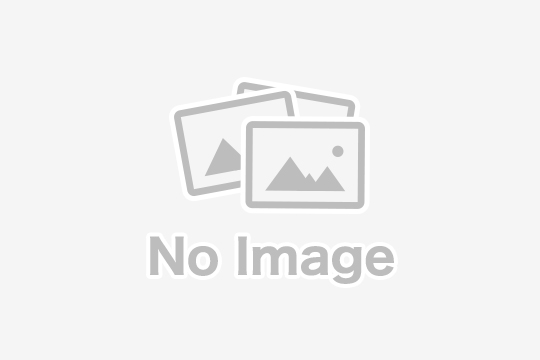契約書の雛形は、そのまま使えませんし、そのまま使っていいものではありません。
なぜなら、品質が高い契約書の雛形であっても、記載された内容と実態としての契約内容が一致していることはないからです。
このため、何らかの形で、修正・調整が必要となります。
このページでは、こうした契約書の雛形の修正・調整のポイントについて、解説します。
契約書の雛形はそのまま使ってはいけない
まず、大前提として、契約書の雛形は、そのまま使ってはいけないものです(自社専用に作成されたものは別です)。
これは、その契約書の雛形の品質の高低に関係ありません。
言うまでもなく、品質が低い契約書の雛形をそのまま使ってはいけません。
また、品質が高い契約書の雛形であっても、自社の契約内容にピタリと一致していることはありません。
このため、品質が高い契約書の雛形であっても、なんらかの修正・調整は、必要になってきます。
契約書は内容・表現・適法性
契約書の作成の際に重要となる点が、以下の3つの点です。
契約書の作成で重要な3つのポイント
- 内容:契約内容が妥当であること。
- 表現:契約条項の文章の表現が正確に契約内容を反映していること。
- 適法性:契約内容が適法であること。
これは、雛形を修正・調整する場合も、同じことです。
:ポイント:】雛形の内容を契約の実態に合わせる
雛形は”必ず”契約内容の実態に合ってない
契約書の雛形は、自社の契約内容の実態とピタリと一致することはありません。
つまり、契約書の雛形は、自社の契約内容とは”必ず”違うものである、ということです。
その理由は、その契約書の雛形は、特定の案件で使うことを想定せず、あくまで一般的な内容として作られたものだからです。
だからこそ、”必ず”修正・調整する必要があります。
「なんとなく合ってそう」な雛形は内容が足りない
「そんなことないけどなぁ…。この雛形、ウチのビジネスモデルに合ってるよ?」
中には、そんな経験がおありの方もいらっしゃるかもしれせん。
しかし、これは、単に書かれている内容が合っているように見えるだけの可能性があります。
見える部分だけ「合っている」
「なんとなく合ってそう」なのは、見えている契約条項だけ。本来はもっと必要な契約条項が書かれていない可能性もある。
多くの契約書の雛形は、最大公約数のような内容となっているため、本来あるべき内容の量となっていません(単にページ数が足りない、という話とは別です)。
つまり、「なんとなく合ってそう」な契約書の雛形は、最大公約数から漏れた重要な内容が足りない=書かれていない可能性があります。
追記するべき内容を知らないと追記ができない
このため、契約書の雛形の修正・調整の際には、書かれている内容の修正・調整だけでなく、足りない内容の追記も検討します。
このように、契約書の雛形は、書かれている内容を修正・調整するだけではなく、「書かれていないこと」の追記も重要となります。
ただ、「書かれていないけども追記するべき内容」は、知らなければ追記のしようがありません。
こうした「知らない」問題を解決するには、類似する契約書の雛形を大量にチェックするか、または知っている外部の専門家のチェックを受けるしかありません。
どちらの立場で作成されたのかを見極める
契約書の雛形の内容を修正・調整する際に、最低限、そして最初の段階ですることがあります。
それは、その雛形が、どちらの契約当事者の立場で作られたのか、という点を確認することです。
契約は必ず2者以上の当事者がいますが、契約内容は、そのいずれかの当事者にとって有利になっているものです。
これは、契約書の雛形も同じことで、ほとんど雛形は、契約当事者のどちらかにとって有利にできています。
うっかり自社にとって不利な内容の契約書の雛形を使ってしまうと、当然、不利な契約を結ぶことになりますので、よく確認してください。
ポイント
- 雛形は自社の契約のために作られていないため、”必ず”契約内容の実態に合ってない。
- 「なんとなく合ってそう」な雛形は、内容が足りず、追記が必要が場合が多い。
- 追記するべき内容を知らないと、雛形の契約書には追記ができない。
- 最低限、どちらの立場で作成されたのかを見極めたうえで、自社にとって不利な雛形は使わない。
ポイント2:契約条項を正確に表現する
契約書には表現のルール・慣習がある
契約書の表現・書き方は、法律上のルールがあるわけではありませんが、事実上のルールや慣習があります。
このため、契約書は、一般的に使用するような日本語の文章で表現すればいい、という単純なものではありません。
英語には「legalese」という表現がありますが、これは「専門家にしかわからない法律用語」という意味です。
法律や契約内容を正確に表現する場合、わかりやすさを犠牲にしてでも、正確性を優先した表現とします。
このため、法律や契約の表現は、慣習上、一般的な日本語の文章とは違った、独特の表現となります。
専門家は表現だけでも作成者のレベルがわかる
こうした事情があるため、契約書に一般的な日本語の文章が書かれていると、非常に違和感があります。
契約書の雛形の修正・調整に一般的な日本語の文章を使うと、法律・契約書の専門家には、すぐにバレてしまいます。
修正・調整の箇所が多くなると、その修正・調整した人の実務能力まで、見透かされてしまいます。
このため、ヘタに契約書の雛形を修正・調整すると、かえってリスクが高くなることもあります。
ルール・慣習を知らなければ書きようがない
ただ、そうは言っても、契約書の書き方のルールや慣習を知らなければ、書きようがありません。
例えば、法律用語や契約書の書き方としては、「その他」と「その他の」では、意味が違います。
また、著作権については、「使用」と「利用」では、概念が違います。
こうした知識がなければ、雛形の調整・修正はできませんし、単に文章を変えたとしても、いざトラブルになった際には、意図とは違った形で契約書が機能するリスクがあります。
このため、契約書の雛形の調整・修正は、それなりに専門知識を経験が必要となります。
最低限表現は統一する
意外と契約書の雛形を修正する際に重要となるのが、表現の統一です。
例えば、「及び」と「および」、「又は」と「または」、「基づき」と「もとづき」のように、表現は、漢字か平仮名のどちらかに統一します。
漢字・平仮名の統一は一例に過ぎませんが、表現が統一されていないと、修正・調整した箇所がバレてしまいます。
このため、少なくとも、表現くらいは統一するべきです。
この他、契約書の雛形の修正・調整に必要な法律用語・契約文書の使い方につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
ポイント
- 契約書の表現には、一定のルール・慣習がある。このため、こうしたルール・慣習に従って雛形の修正・調整をしないといけない。
- 法律・契約の専門家は、契約書の表現だけでも作成者のレベルがわかるため、ごまかせない。
- ルール・慣習を知らなければ、契約書の調整・修正はできない。
- 最低限、見た目の表現だけでも統一する。
ポイント3:適法な内容とする
適法な契約=刑事・行政・民事で違法でない
適法な契約内容とは、刑事・行政・民事のいずれの分野の法律にも違反しない、ということです。
適法な契約内容とは?
- 刑事上適法な契約内容:刑事罰がある法律に違反していないこと
- 行政上適法な契約内容:行政処分を受ける法律の規制に抵触していないこと
- 民事上適法な契約内容」契約内容が無効でないこと・損害賠償の対象とならないこと
契約自由の原則により、契約は、自由に決めることができます。
【意味・定義】契約自由の原則とは?
契約自由の原則とは、契約当事者は、その合意により、契約について自由に決定することができる民法上の原則をいう。
ただ、契約自由の原則は、意外と例外が多く、好き勝手に契約書の雛形を修正・調整していると、知らないうちに違法となることがあります。
刑事上の違法性はないか
当たり前の話ですが、刑事罰を課されるように契約書の雛形を修正してはいけません。
契約書に関する刑事罰は、殺人や窃盗のように、典型的な刑事犯がするような犯罪ではありません。
例えば、下請法第3条に規定する書面(いわゆる三条書面)を交付しなかった場合(下請法第3条の要件を満たしていない書面を交付した場合も含みます)、最大で50万円の罰金が科されます。
この他にも、契約には意外と刑事罰が科される法規制が多く、知らず知らずのうちに、その法規制に抵触することがあります。
このため、契約書の雛形の修正・調整のしかたによっては、結果的に犯罪行為を犯してしまうことになります。
行政上の違法性はないか
事業者間(BtoB)の契約、事業者と消費者(BtoC)の契約のいずれも、意外と行政上の法規制があります。
行政上の法規制の例
- 企業間取引の例:独占禁止法、下請法、建設業法、労働者派遣法など。
- 企業対消費者の取引の例:消費者契約法、特定商取引法など。
- 業法の例:資金決済法、金融商品取引法、貸金業法など。
こうした法規制に抵触すると、営業停止処分などの、行政処分となる可能性があり、最悪の場合、すでに触れた刑事罰が科されることもあります。
契約書の雛形を修正・調整する際には、こうした個々の行政上の法律の規制に抵触しないよう、注意しなければなりません。
民事上の違法性はないか
刑事罰が科されるような内容や、行政処分を受けるような内容ではなくても、民事上、違法となる契約内容もあります。
契約内容が民事上違法の場合、契約条項が無効となります。
また、民事上違法な契約条項の内容である債務を相手方に強要した場合、損害賠償の対象となります。
このように、ヘタに契約書の雛形を修正・調整してしまうと、刑事罰や行政処分はなかったとしても、契約条項が無効となったり、損害賠償の対象となることがあります。
知らない法律は調べようがない
このように、契約には様々な法律が適用されますが、こうした法律は、そもそも知らなければ調べようがありません。
実は、法律・契約の専門家にとっても、こうした法律の問題は、悩ましいものです。
「適法な契約書」は専門家でも難しい
契約書の作成・修正・調整で、完全に適法な契約書とするのは、専門家でも難しい作業。
いくら専門家といっても、すべての法律について知っているわかではありませんので、有名な法律しか頭に入っていません。
だからこそ、いわゆる「リーガルリサーチ」の能力が問われてきます。
契約書の雛形の修正・調整の際にも、その契約内容にどのような法律が適用され、そしてその法律に違反しないように対処する能力が必要となります。
なお、代表的な契約に適用される法律を一覧にまとめましたので、詳しくは、次のページをご覧ください。
ポイント
- 適法な契約は、刑事・行政・民事いずれの法律にも違反しない。
- 契約に適用される法律を知らなければ、契約書の雛形を適法に修正・調整できない。
- 契約書の作成・修正・調整で、完全に適法な契約書とするのは、専門家でも難しい作業。