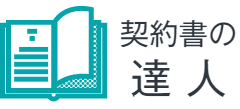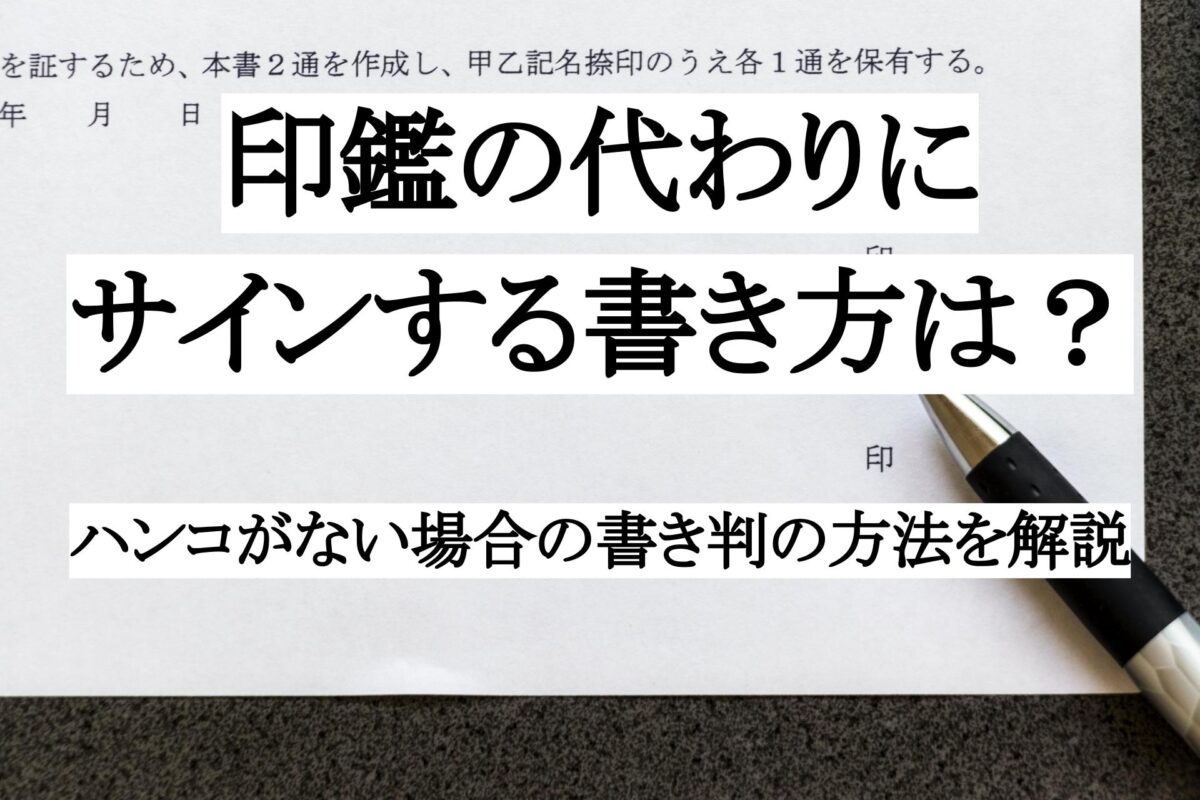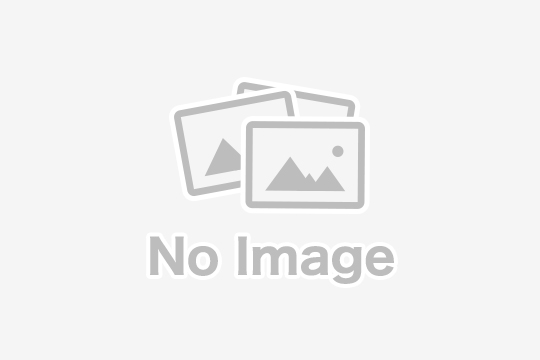取締役による署名・サインは、代表権がある場合は、株式会社などの法人の署名・サインとして、有効となります。
他方、代表権がない取締役の署名・サインも、法人の署名・サインとみなされる場合と、そうでない場合があります。
このため、契約の相手方の署名者・サイナーが取締役である場合は、注意が必要です。
このページでは、こうした取締役による、契約書への署名・サインについて、わかりやすく解説します。
取締役は代表権がある場合とない場合がある
会社法では原則として代表権があるが実際にはないことが多い
取締役は、代表権がある場合とない場合があります。
会社法では、原則として、株式会社の取締役は、会社を代表します(会社法第349条第1項本文)。
ただし、例外として、代表取締役が定められている株式会社の場合は、取締役には代表権はありません(会社法第349条第1項ただし書き)。
会社法第349条(株式会社の代表)
1 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
引用元:会社法 | e-Gov法令検索
もっとも、実際は話が逆で、ほとんどの会社では、代表取締役が定められていて、取締役には代表権がないことが多いです。
取締役に契約の締結権があるかどうかがポイント
さて、法人における契約書の署名者・サイナーは、その法人における契約の締結権がなければ、法人としての署名・サインはできません。
会社の代表権がある場合は、当然ながら、契約の締結権があります。
このため、代表権がある取締役による契約書への署名・サインは、会社として契約書に署名・サインをしたことになります。
問題は、日本の会社における多くの取締役のように、代表権がない取締役(いわゆる「平取締役」)による契約書への署名・サインが、会社としての署名・サインとして有効かどうかです。
ポイント
- 会社法では、取締役は原則として会社を代表するとされるが、実際には、代表取締役だけが会社を代表し、取締役には代表権がない会社が多い。
- 契約書に署名・サインをする者が取締役の場合、その取締役に契約の締結権があるかどうかがポイントとなる。
代表権がない取締役の署名・サインが有効な場合
表見代表取締役の場合
会社法には、表見代表取締役という制度があります(会社法第354条)。
【意味・定義】表見代表取締役とは?
表見代表取締役とは、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を株式会社が付与した場合において、その株式会社が、善意の第三者に対し責任を負う制度のことをいう。
会社法第354条(表見代表取締役)
株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
引用元:会社法 | e-Gov法令検索
ここでいう善意の第三者とは、「事情(この場合は、本当は代表権がないこと)を知らない第三者」ということです。
【意味・定義】善意の第三者とは?
善意の第三者とは、事情を知らない第三者をいう。
つまり、実際は代表権がない取締役の署名・サインであっても、契約の相手方が「代表権がないこと」を知らない場合は、株式会社としては、その署名・サインについて、責任を負わなけばなりません。
ということは、こうした場合の取締役の署名・サインは、株式会社としての署名・サインとして有効となります。
判例でも、常務取締役について、同様の判決が出ています(最高裁判決昭和35年10月14日)。
取締役が支配人の場合
取締役に代表権がなかっとしても、その取締役が、いわゆる支配人(会社法第10条)である場合は、契約を締結する権限を有します(会社法第11条)。
会社法第11条(支配人の代理権)
1 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
引用元:会社法 | e-Gov法令検索
支配人とは、会社法では明確な定義があるわけではありませんが、一般的には、本店や支店を統括する立場や主任者の立場にある者のことをいいます。
【意味・定義】支配人(会社法)とは?
支配人(会社法)とは、一般に、本店や支店を統括する立場や主任者の立場にある者をいう。
一般的な株式会社としては、いわゆる支社長、支店長、営業所長などは、支配人に該当するものと思われます。
このため、取締役が支社長、支店長、営業所長などの場合は、その署名・サインは、会社としての署名・サインとして有効となります。
表見支配人の場合
また、実際には本店や支店の統括や主任者をしていない者が支配人の名称を付与した場合であっても、その者による署名・サインは、会社のものとして有効となります。
このような制度を表見支配人といいます(会社法第13条)。
【意味・定義】表見支配人とは?
表見支配人とは、会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人について、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる制度のことをいう。ただし、相手方が悪意の場合は、そのようにみなされない。
ここでいう「悪意」とは、その表見支配人が本当は支配人でないことを知っていること、を意味します。
【意味・定義】悪意とは?
悪意とは、ある事情を知っていることをいう。
つまり、一方の契約当事者が、相手方の署名者・サイナーである表権支配人を支配人と信じてしまった場合は、契約は、会社と締結したものとして成立します。
担当事業に関する契約の場合
一般的な取締役は、会社から、なんらかの事業の担当を委任されています。
この場合、取締役は、「当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する」ことになります(会社法第14条第1項)。
これにより、担当事業に関する契約書への取締役による署名・サインは、会社のものとして有効になります
また、こうした担当事業に関する取締役の権限に制限があったとしても、その制限を知らなかった第三者(=善意の第三者)に対しては、会社の側は、制限があることを主張できません(会社法第14条第2項)。
会社法第14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
1 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
引用元:会社法 | e-Gov法令検索
ポイント
- 取締役に会社を代表する肩書きがある場合、表見代表取締役に該当し、その取締役の署名・サインは、会社による契約書への署名・サインとなることがある。
- 取締役が支社長・支店長・営業所長のように、会社法上の支配人に該当する場合は、その取締役の署名・サインは、会社による契約書への署名・サインとなる。
- 実際には支社長・支店長・営業所長としての権限がなくても、そのような名称を付けられている取締役の場合は、その取締役の署名・サインは、会社による契約書への署名・サインとなる
- 担当事業に関する契約書への取締役の署名・サインは、会社による契約書への署名・サインとなる
会社法だけでなく契約書でも対策する
代表権がない場合でも有効な著名・サインとなるようにする
このように、会社を代表しない取締役の署名・サインでなかったとしても、会社による契約の締結とみなされる会社法の制度や判例があります。
こうした会社法の制度や判例により、取締役の署名・サインの多くは、会社によるものとみなされます。
ただ、せっかく契約書に署名・サインをしてもらうにもかかわらず、その契約が会社と締結するかどうかについて、会社法や判例だけに頼るわけにはいきません。
そこで、契約書にも、万が一、代表権がない取締役が署名・サインした場合についての対策を記載しておきます。
契約書には契約を締結する代表権があることを明記する
具体的には、サインをする取締役が、会社として契約を締結する権限を有している旨を宣誓する条項を規定しておきます。
特に、こうした内容は、署名欄の直前(いわゆる後文)に記載しておくと、効果的でしょう。
これにより、仮に代表権がない取締役が署名・サインをした場合であっても、すでに触れた表見代表取締役や表見支配人の規定を、より適用しやすくなります。
なお、株式会社の署名・サインのしかたにつきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
ポイント
- 会社法に頼るのではなく、契約書にも、会社としての署名・サインとなるように、工夫する。
- 契約書の後文には、署名者・サイナーに契約の締結権があることを宣誓させ、明記する。