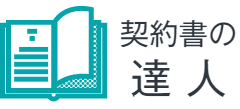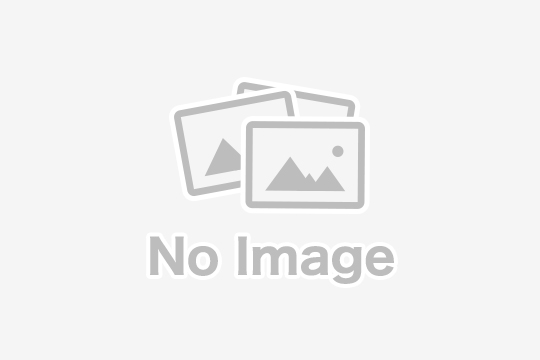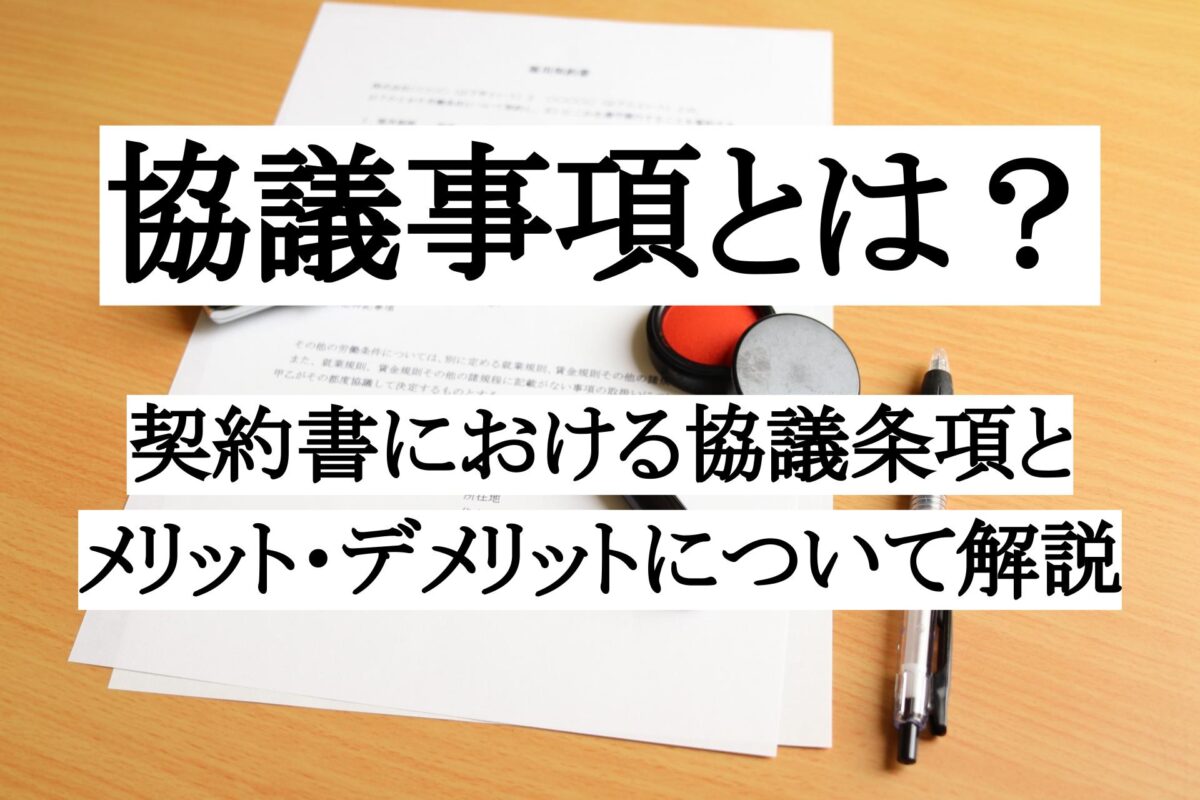ほとんどの契約書では、わざわざ契約解除条項を規定します。
というのも、民法上の契約の解除に関する規定は、あまりにも限定された条件でしか利用できません。
このため、より柔軟に契約の解除ができるように、わざわざ契約解除の条項を規定し、より広い契約解除事由を設定します。
このページでは、契約解除条項と民法上の契約解除の規定について、詳しく解説します。
契約は原則として解除できない
契約解除ができるのは例外中の例外
契約は、契約当事者同士の合意にもとづく約束ですから、原則として解除できません。
「Pacta sunt servanda」(ラテン語で「合意は拘束する」)という言葉があるように、契約実務の世界では、合意=契約は守らて当然なのです。
このため、当事者の合意がない限り、一方の当事者が勝手に契約を解除することはできません。
例外として、契約の解除ができるのが、契約解除権にもとづく場合です。
契約解除権(契約解約権)は主に3種類(+1種類)
契約解除権には、次の3種類があります。
3種類の契約解除権
- 約定解除権=契約にもとづく一定の条件つきの契約解除権
- 任意解除権=契約にもとづく任意の契約解除権
- 法定解除権=法律にもとづく契約解除権
そして、厳密には契約解除権ではありませんが、当事者の合意がある場合も、契約解除ができます。
これを合意解除(合意解約)といいます。
契約解除条項は、このうちの、約定解除権のことです。
ポイント
- 原則として、契約は守られるべきものであり、契約解除・契約解約は、あくまで例外。
- 解除権は、約定解除権、任意解除権、法定解除権の3種類。
契約解除が可能となる契約解除事由とその具体例
【意味・定義】契約解除事由とは?
では、実際に契約解除条項を見てみましょう。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】契約解除条項
第○条(契約解除)
本契約の当事者に次の各号の事由が生じた場合、相手方は、本契約の全部または一部を解除できるものとする。
(1)(以下省略)
(※便宜上、表現は簡略化しています)
このように、契約解除条項では、一般的に、契約当事者による契約の解除ができる事由を各号で列記するように規定します。
この契約を解除できる事由のことを、「契約解除事由」といいます。
【意味・定義】契約解除事由とは?
契約解除事由とは、一方の当事者に生じた場合に、他方の当事者が契約を解除できるようになる事由をいう。
契約解除事由の11の具体例
一般的な契約では、次のような契約解除事由を規定します。
契約解除事由の具体例
- 公租公課・租税の滞納処分
- 支払い停止・不渡り処分
- 営業停止・営業許可取り消し
- 営業譲渡・合併
- 債務不履行による仮差押え・仮処分・強制執行
- 破産手続き開始申立て・民事再生手続き開始申立て・会社更生手続開始申立て
- 解散決議・清算
- 労働争議・災害等の不可抗力
- 財務状態の悪化
- 信用毀損行為
- 契約違反・債務不履行
これらの契約解除事由は、一般的なものですので、契約の実態によっては、適宜加除修正する必要があります。
契約書に契約解除条項を規定する際は、この契約解除事由の規定が非常に重要となります。
契約解除事由と期限の利益喪失事由は共通する部分が多い
なお、これらの事由は、期限の利益喪失条項における、「期限の利益喪失事由」と共通するものです。
つまり、多くの契約解除事由は、期限の利益を喪失させるべき危機的な緊急事態を定めたものといえます。
また、逆に、期限の利益喪失事由に相当するような事態では、契約の解除も検討するべきだともいえます。
暴力団排除条項にも契約解除権を規定する
なお、暴力団排除条項を規定する場合、その一部として、契約解除権を規定します。
この契約解除権も、一種の約定解除権といえます。
暴力団排除条項の場合は、催告が不要な無催告解除(後述)とします。
また、契約を解除する側は、その契約解除による自らの損害賠償の免責と、相手方に対する損害賠償請求権も併せて規定します。
ポイント
- 契約解除事由とは、一方の当事者に生じた場合に、他方の当事者が契約を解除できるようになる事由のこと。
- 契約解除事由と期限の利益喪失事由は共通する部分が多い。
- 暴力団排除条項にも契約解除権を規定する。
なぜ契約解除事由を契約書に記載するのか?
【理由1】民法上の法定解除権では不十分だから
民法上、基本的には、(後ほど解説する)債務不履行の状態になっていないと、法定解除権を行使できません。
このため、債務不履行の一種である履行遅滞や履行不能になるおそれがある状態では、契約の解除はできません。
また、民法上、契約解除の手続きが必ずしも明確でない部分があり、契約解除=トラブルとなっている状態では、実質的に解除権が行使できない可能性があります。
そこで、契約書では、契約の解除ができる条件=要件(契約解除事由)や効果を追加・修正し、手続きを明確に規定します。
契約書を作成する理由・目的
民法上の法定解除権は、極めて限定された条件を満たさないと行使できない不十分なものであることから、特約として約定解除権とその契約解除事由、効果、手続きを規定した契約書が必要となるから。
こうすることで、状況に応じて、柔軟に契約を解除できるようになります。
【理由2】契約解除を検討する段階では合意解除ができる状態ではないから
また、一般的に、契約を解除しようとする状態では、信頼関係が破綻している場合が多いです。
信頼関係が破綻した状態では、事実上、コミュニケーションが取れないことがほとんどです。
もちろん、協議による合意による契約の解除もできません。
こうした場合、契約書で、あらかじめ詳細に契約解除の条件(要件)と手続きを明記しておくことで、わざわざ相手方とコミュニケーションを取ることなく、契約解除ができます。
契約書を作成する理由・目的
契約解除を検討する段階では、すでに相手方との信頼関係が破綻し、合意解除が難しくなることから、あらかじめ契約解除について規定した契約書を作成することで、信頼関係が破綻した状態でも相手方と合意することなく契約解除ができるようにするため。
このように、協議が成立しない状態でこそ、契約解除条項は効果を発揮します。
ポイント
- 約定解除権を設定する理由のひとつは、民法上の法定解除権では不十分だから。
- 約定解除権を設定する理由のもうひとつは、契約の解除・解約を検討する状態では、協議ができる状態ではないことが多いから。
無催告解除権と催告解除権とは?
【意味・定義】無催告解除権・催告解除権とは?
約定解除権には、催告の有無により、2種類あります。
つまり、ひとつは「無催告解除権」、もうひとつは「催告解除権」です。
【意味・定義】無催告解除権・催告解除権とは?
- 無催告解除権とは、契約解除事由が発生した場合に、契約当事者からの催告を要せずして、当然に契約解除ができる権利をいう。
- 催告解除権とは、契約解除事由が発生した場合であっても、契約当事者からの一定の期間を定めた催告を経て、なおその契約解除事由が解消されないときに、契約解除ができる権利をいう。
一般的に、緊急性が高い契約解除事由については無催告解除権とし、そうでない契約解除事由については催告解除権とします。
債務の履行に関わる緊急度に応じて使い分ける
具体的には、債務者の債務の履行に重大な影響を与えるような緊急事態の契約解除事由は、無催告解除権とします。
つまり、無催告解除権は、いちいち催告している時間がもったいない契約解除事由や、催告しても解消される見込みがないほど深刻な契約解除事由などの、緊急事態に備えたものです。
無催告解除権の規定のしかた
無催告解除権は、催告の時間的余裕がない、あるいは解消される見込みがない、深刻な契約解除事由に備えて規定する。
これに対し、それほど緊急性が高くないまでも、契約当事者による債務の履行に影響を与える契約解除事由は、催告解除権とします。
つまり、催告解除権は、債契約当事者に対し催告をする余裕がある契約解除事由や、催告により解消される可能性がある契約解除事由などの、緊急性が高くない事態に備えたものです。
催告解除権の規定のしかた
催告解除権は、催告の時間的余裕がある事態や、催告により契約解除事由が解消される可能性のある事態に備えて規定する。
これについても、期限の利益の喪失に請求が必要か、または不要か、という点と同様です。
ポイント
- 無催告解除権とは、契約解除事由発生した場合に、契約当事者からの催告を要せずして、当然に契約解除ができる権利のこと。
- 催告解除権とは、契約解除事由発生した場合であっても、契約当事者からの一定の期間を定めた催告を経て、なおその契約解除事由が解消されないときに、契約解除ができる権利のこと。
- 無催告解除権は、緊急度が高い事態や解消する見込みがない契約解除事由に備えて規定する。
- 催告解除権は、緊急度が低い事態または解消する見込みがある契約解除事由に備えて規定する。
民法上の契約解除権=法定解除権とは?
【意味・定義】法定解除権とは?
法定解除権は、文字どおり、法律に規定された解除権のことです。
【意味・定義】法定解除権とは?
法定解除権とは、法律に規定された契約解除権をいう。約定解除権とは別の解除権。
一般的に、法定解除権といえば、民法に規定された解除権を意味しますが、他の法律に規定された解除権もあります。
ここでは、民法に規定された2種類の法定解除権(催告解除権・無催告解除権)について解説します。
民法第541条の催告解除権とは
民法上の催告解除権は、第541条に規定されています。
民法第541条(催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
【意味・定義】催告解除権とは?
催告解除権とは、その行使に催告を要する契約解除権をいう。
改正民法により、ただし書きが追記され、相当の「期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」の要件を満たした場合は、契約の解除ができないことが明文化されました。
民法第542条の無催告解除とは
民法上の無催告解除権は、第542条に規定されています。
民法第542条(催告によらない解除)
1 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
【意味・定義】無催告解除権とは?
無催告解除権とは、その行使に催告を要しない契約解除権をいう。
それぞれの契約解除事由=要件は、大まかに次の3つに分類されます。
民法第542条の契約解除事由=要件
- 債務不履行(履行不能)(第1項第1号、同第3号、第2項第1号)
- 債務不履行(履行拒絶)(第1項第2号、同第3号、第2項第2号)
- 定期行為(第1項第4号)
なお、すでに述べたとおり、これらの無催告解除権の契約解除事由では一般的な契約における契約解除事由としては不十分であるため、別途約定解除権を規定することが重要となります。
改正民法で債務者の帰責事由が不要となった
旧民法では、法定解除権の行使には債務者の帰責事由が必要でした。
2020年施行された改正民法では、法定解除権の行使に債務者の帰責事由が必要ではなくなりました。
これにより、法定解除権の条項は、催告解除権(第541条)と無催告解除権(第542条)に整理されました。
ただし、債権者に帰責事由がある場合は、債権者は、法定解除権を行使できません(第543条)。