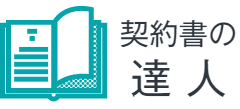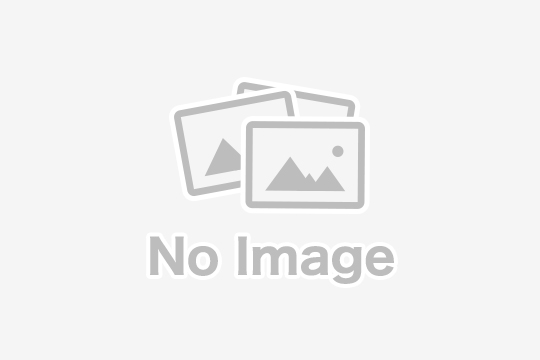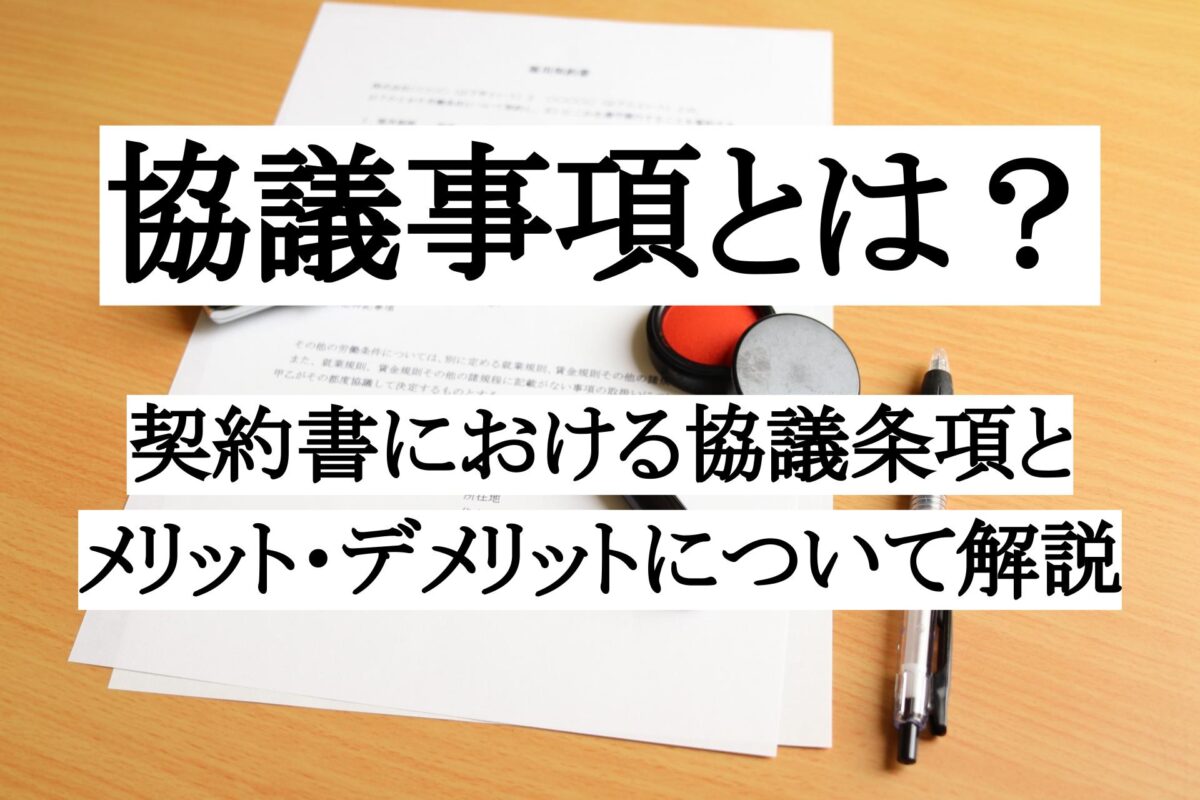危険負担の移転の時期の条項は、契約にもとづき引渡しや納入がある物品・製品・成果物等の目的物に後発的事由が発生した場合、その損害を誰が負担するのかについて規定する契約条項です。
一般的な契約では、後発的事由のうち、発注者・受注者の双方に責任がない場合(例:自然災害や第三者による損害)の損害について、危険負担として取扱います。
具体的には、目的物の引渡し・納入の時点か、または検査完了の時点で、危険負担の当事者が、受注者から発注者に移転することが多いです。
なお、危険負担の移転の時期は、民法では実態とかけ離れた内容となっていて、非常に批判が多いため、契約で修正することが重要となります。
【意味・定義】危険負担とは?
危険負担は後発的事由による損害の負担のこと
危険負担の移転の条項は、売買契約、請負契約、取引基本契約など、目的物の引渡しや納入がある契約において、後発的な事由によって生じた目的物の損害に関する負担について規定される条項です。
【意味・定義】危険負担とは?
危険負担とは、後発的な事由によって、目的物になんらかの損害が生じた場合における損害の負担をいう。
ここでいう後発的な事由というのは、天変地異のような不可抗力や火災・盗難などの第三者による災害が該当します。
一般的な契約では、危険負担の移転の条項では、最初は受注者の側に危険負担があるのを前提に、ある時点、通常は納入か検査完了のいずれかの時点で、発注者の側に移転するように規定します。
危険負担が問題になるのは発注者・受注者双方に責任がない場合
後発的事由のうち、契約条項として危険負担が問題となるのは、発注者・受注者の双方に責任がない場合に限ります。
発注者・受注者のいずれか、または双方に責任がある場合は、債務不履行か、または発注者の側の一方的な危険負担となります。
具体的には、次のとおりです。
| 責任当事者 | 危険負担・債務不履行 (履行不能)の別 | 負担当事者 |
|---|---|---|
| 受託者 | 受託者の債務不履行(履行不能) | 受託者 |
| 委託者 | 危険負担 | 委託者 |
| 委託者・受託者双方 | 受託者の債務不履行(履行不能) | 委託者・受託者双方 (過失相殺による) |
| 委託者・受託者いずれも責任がない | 危険負担 受託者の債務不履行(履行不能) 委託者の反対給付債務の履行拒絶権の発生 | 契約内容次第 危険負担の規定がなければ改正民法第567条により目的物の引渡しは受注者、引渡し後は発注者の責任 |
このように、発注者・受注者のいずれか単独の責任による後発的事由にもとづく損害は、当然、その責任者たる発注者・受注者のいずれかの負担となります。
単に、債務不履行または危険負担による、という理論上の違いがあるだけです。
なお、改正民法第536条第2項により、発注者の責任による危険負担の場合は、反対給付の履行(一般的な契約の場合は報酬・料金の支払い)を拒むことはできません。
また、発注者・受注者双方の責任による場合は、受注者にも責任があるため、債務不履行として扱い、発注者の過失の程度によって、過失相殺されます。
このため、契約条項として問題となるのは、あくまで、発注者・受注者の双方に責任がない場合における危険負担とその移転の時期です。
ポイント
- 危険負担とは、後発的事由(例:天変地異・天災などの不可抗力や火災・盗難などの第三者による行為)による損害の負担のこと。
- 危険負担が問題になるのは発注者・受注者双方に責任がない場合に限る。発注者・受注者単独や、双方による場合は、単独による責任または双方による責任の負担。
危険負担の移転の時期を規定する理由は単純に危険を負担したくないから
危険負担の移転の時期は利害が完全に対立する
なぜわざわざ危険負担の移転の時期を、契約でわざわざ規定する必要があるのでしょうか?
そのほとんどの理由は、契約当事者の双方が、自身の責任でない損害について、単に責任を負担したくないからです。
このため、受注者としては、「早く危険負担を移転させたい」と考えますし、発注者としては、「遅く危険負担を移転させたい」と考えます。
危険負担に関する委託者・受託者の双方の思惑
- 発注者:遅い時期に危険負担が移転したほうがいい。
- 受注者:早い時期に危険負担が移転したほうがいい。
こうした事情があるため、契約条項として危険負担の移転の時期を規定する際は、発注者と受注者の間で完全に利害が対立し、しばしば調整が難航します。
契約書を作成する理由・目的
発注者・受注者ともに、自己にとって都合のいい危険負担の移転の時期が規定された契約書が必要となるから。
民法の原則では引渡し(納入)の時点で危険負担は移転する
契約当事者双方に責任がない場合における危険負担は、民法第559条によって準用される改正民法第567条により、目的物の引渡しの時点で、引渡す側の受注者から受取る発注者の側に移転します。
【意味・定義】準用とは?
準用とは、ある法律の規定を、必要な修正・変更をしたうえで、類似した別の規定に当てはめることをいう。
このため、危険負担の移転の時期を納入の時期とするのであれば、わざわざ契約内容として規定する必要はありません。
ポイント
- 発注者としては、遅い時期に危険負担が移転したほうがいい。
- 受注者としては、早い時期に危険負担が移転したほうがいい。
- 危険負担の移転の時期を契約書に明記するのは、単純に、契約当事者の双方が、後発的事由による損害を負担したなくないから。
- 目的物の引渡し≒納入がある契約において、民法第567条の原則どおり引渡し≒納入の時点で危険負担を移転させる場合は、特に契約内容として規定する必要はない。
危険負担の移転の時期は納入時か検査完了時
通常は納入時か検査完了時に危険負担が移転する
一般的な売買契約、請負契約、取引基本契約では、発注者・受注者の双方に責任がない場合における危険負担の移転の時期は、納入時または検査完了時のいずれかとします。
つまり、納入時または検査完了時のいずれかまでは受注者が危険負担の責任を負い、それ以降は発注者が危険負担の責任を負います。
通常の売買契約、請負契約、取引基本契約では、検査は、納入の後で実施されます。
つまり、危険負担の移転の時期は、より早い納入時のほうが、受注者にとっては有利であり、より遅い検査完了時のほうが、発注者にとって有利ということです。
検査完了時に危険負担が移転する場合は特約として規定する
この点につき、すでに述べたとおり、民法の原則どおり、納入時に危険負担が移転する内容とするのであれば、わざわざ契約内容として規定する必要はありません。
他方で、民法の原則とは異なり、検査完了時に危険負担が移転するのであれば、特約として規定する必要があります。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】●●条項
第○条(危険負担)
1 各契約当事者のいずれの責にも帰すことのできない事由により、第○条の検査完了時前に本件製品に関して生じた一切の損害は、すべて受注者の負担とし、当該検査完了時の後に本件製品に関して生じた損害は発注者の負担とする。
2(以下省略)
(※便宜上、表現は簡略化しています)
契約書を作成する理由・目的
民法の原則では、目的物の危険負担の移転の時期は引渡しの時期=納入時であることから、納入時以外、特に検査完了時としたい場合は、特約としてその旨を規定した契約書が必要となるから。
理論上は他の時期に危険負担を移転させることができる
危険負担の移転時期を物品・製品・成果物の完成時にすることもできる
なお、この他の時期であっても、理論上は、危険負担を移転させることはできます。
例えば、受注者にとって最も有利なのは、物品・製品・成果物が完成した時点で、発注者に危険負担を移転させる規定です。
ただ、こうした規定では、受注者の倉庫にある出荷前の物品・製品・成果物に関する損害まで、発注者が負担しなければなりません。
こうした、あまりにも受注者にとって有利な契約内容は、一般的な契約で規定しません。
危険負担の移転時期を報酬・料金・委託料の支払完了時とすることもできる
これとは逆に、発注者にとって最も有利なのは、報酬・料金・委託料の支払いを完了した時点で、受注者に危険負担を移転させる規定です。
言いかえれば、報酬・料金・委託料の支払いを完了するまでは、報酬・料金・委託料に発生した損害について、発注者は責任を負担しない、ということです。
ただ、こうした規定では、すでに納入や検査まで終わり、発注者の倉庫にある、物品・製品・成果物に関する損害まで、受注者が負担しなければなりません。
こうした、あまりにも委託者にとって有利な契約内容は、一般的な契約では規定しません。
ポイント
- 受注者としては、より早い方=納入時のほうが有利。
- 発注者としては、より遅い方=検査完了時のほうが有利。
- 受託者としては、より早い方=納入時のほうが有利。
- 委託者としては、より遅い方=検査完了時のほうが有利。
【補足】改正民法により危険負担の規定は「債務者主義」から「債権者主義」へ
危険負担の考え方は債権者主義と債務者主義
民法における危険負担には、何らかの目的物の引渡しを請求できる債権について、債権者主義と債務者主義の2種類があります。
改正民法では、危険負担は、次のように改められました。
改正民法での危険負担の分類
- 債務者主義(改正民法第536条第1項):債務者が危険を負担する制度。債務者は、目的物が滅失・既存した場合、代金・報酬・料金・委託料を請求する権利はない。
- 債権者主義(改正民法第536条第2項、第567条第2項):債権者が危険を負担する制度。債権者は、目的物が滅失・毀損した場合、代金・報酬・料金・委託料を支払う義務がある。
例えば、業務委託契約でいえば、危険負担は、受託者が何らかの物品・製品・成果物等の目的物を引渡す契約内容の場合に、火災などの後発的な事由でその目的物が滅失してしまったときが該当します。
こうした場合、目的物の引渡しに関する債権者(委託者)がその損害を負担するのが、債権者主義であり、債務者(受託者)が負担するのが債務者主義です。
旧民法の危険負担は契約実務の実態に合っていなかった
旧民法における危険負担の規定は、企業間取引の実態と合っていない部分がありました。
また、契約内容や、契約の目的物によって、誰が危険負担を負うのかが、非常に複雑に規定されていました。
このため、改正民法では、危険負担について、通常の契約実務と同様に、目的物の引渡し前後で委託者から受託者に移転するように改められました。
ただし、すでに述べたとおり、危険負担の移転の時期について、目的物の引渡し=納入の時点以外(主に検査完了時)に変更するために、あえて契約において、危険負担の条項を規定することはあります。
ポイント
- 債権者主義とは、物品・製品・成果物の引渡しを請求できる債権者が危険を負担する制度。債権者は、目的物が滅失・毀損した場合、代金・報酬・料金・委託料を支払う義務がある。
- 債務者主義とは、物品・製品・成果物の引渡しをする義務がある債務者が危険を負担する制度。債務者は、目的物が滅失・既存した場合、代金・報酬・料金・委託料を請求する権利はない。
- 改正民法により、危険負担の規定は通常の契約実務に近い形で改められた。
- 危険負担の移転の時期を納入時以外(主に検査完了時)に変更するために、危険負担の移転の条項を規定することもある。
【補足2】所有権の移転の時期について
危険負担の移転の時期と同様に問題となる契約条項に、所有権の移転の時期があります。
所有権の移転の時期は、危険負担の移転の時期とセットで考えられることが多い条項です。
所有権の移転の時期の詳しい解説につきましては、以下のページをご覧ください。