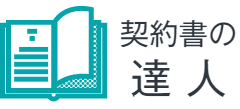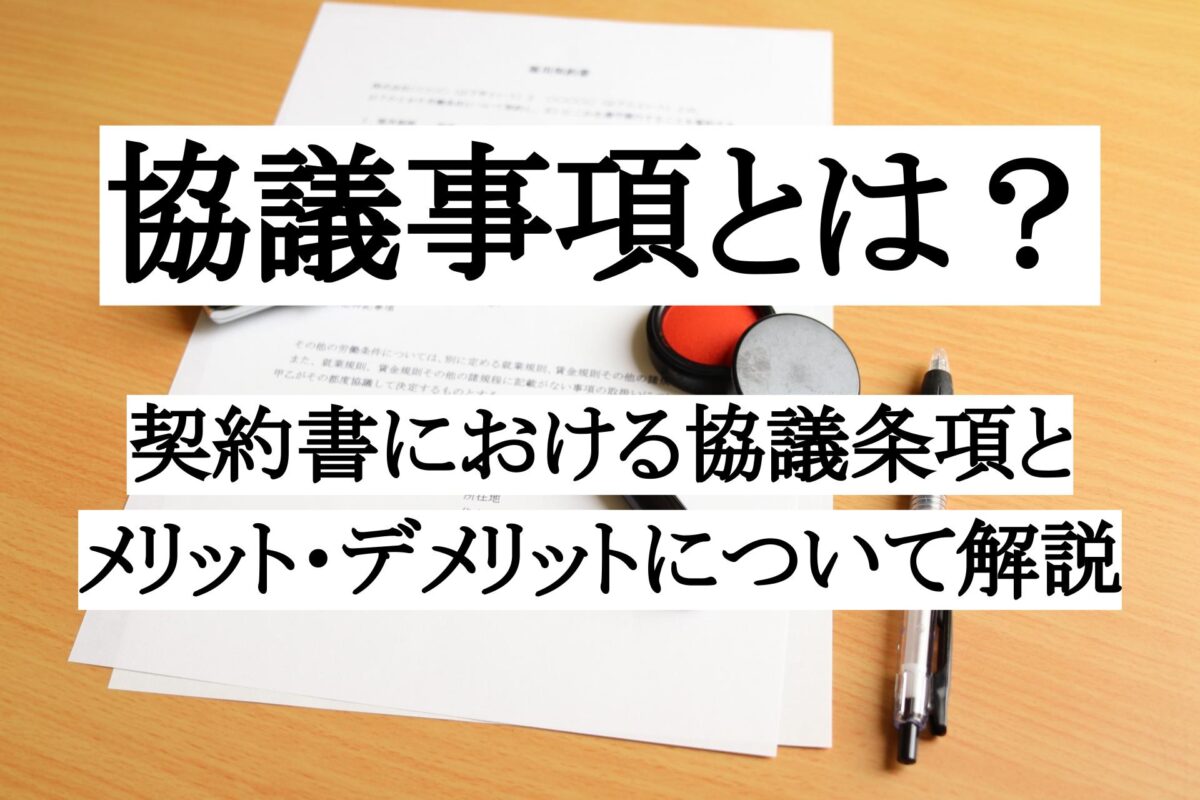不安の抗弁権とは、相手方の信用リスクや相手側の契約の履行能力に不安を感じた当事者が、相手方に対して有する、自己の債務の履行を拒絶できるなどの権利です。
不安の抗弁権は、法律に規定されているものではありませんが、これまで多くの判例が認めてきている権利です。
ただ、平成29年の民法改正の際には、明文化が見送られ、依然として不明確な部分が多いという実態もあります。
このページでは、こうした不安の抗弁権の条項について、解説します。
不安の抗弁権とは
【意味・定義】不安の抗弁権の定義とは?
「不安の抗弁権」とは、「双務契約において,債務者が債務を履行すべき場合でも,相手方から反対給付を受けられないおそれが生じたことを理由に,自己の債務の履行を拒絶することなどができる権利」をいう。
不安の抗弁権によって契約の履行を拒絶できる
不安の抗弁権は相手方の信用状態の悪化に備えた権利・契約条項
不安の抗弁権は、具体的には、相手の信用状態などが不安な状況になった場合、先に履行しなくてはならない債務の履行を拒絶(抗弁)できる権利です。
例えば、継続的な売買契約・請負契約などの、いわゆる「取引基本契約」の場合に、重要となります。
取引基本契約では、一般的には後払いの契約ですので、受注者(売主・請負人)のほうが、先に物品・製品・成果物を納入します。
この納入の際、発注者(買主・注文者)の信用状態が急速に悪化し、後払いの料金が払えない状態になることがあります。
こうした状態で、一時的に納入を保留できる(場合によっては契約解除ができる)権利が、不安の抗弁権です。
不安の抗弁権は継続的な契約で問題となる
すでに触れたとおり、不安の抗弁権は、継続的な契約において問題となる契約です。
一回的契約(いわゆるスポットの契約)では、契約の際の信用状態から突然信用状態が悪化することはまずありません。
このため、スポット契約では、不安の抗弁権は問題になりません。
ただし、1回だけとはいえ、建設工事請負契約のように、契約の履行が終わるまで、長時間を要する契約の場合も、不安の抗弁権は問題となる可能性はあります。
ポイント
- 不安の抗弁権を行使することで、相手方の義務の履行に不安を感じた場合は、契約の履行を拒絶できる場合がある。
- 不安の抗弁権は、主に継続的な契約での信用状態の悪化の際に問題となる。
民法改正では明文化が見送れられた不安の抗弁権
一般化した要件を規定するのが難しいため明文化されなかった
平成29年の民法改正では、不安の抗弁権は議題とはなりましたが、明文化は見送られました。
これは、次のような事情によるものです。
不安の抗弁権の明文化が見送られた経緯
- 具体的・制限的な要件で規定することは困難であるため。
- 抽象的な要件として規定しても、適用できるかどうかが明らかでない規定になるため。
- 抽象的な要件として規定した場合であっても、濫用されるリスクがあるため。
- 最高裁判例がない=下級審の判例しかなく、しかも数も少ないため、明文化したとしても、運用の予測がつかないため。
このため、改正民法の施行後も、不安の抗弁権は、数少ない下級審判例に類似する案件でしか行使しづらい権利といえます。
そこで、企業間取引で、より確実に不安の抗弁権を行使しやすくするためには、その契約に適合した不安の抗弁権の要件・効果を規定する必要があります。
【参考】中間試案の条文案
ちなみに、「民法(債権関係)の改正に関する 中間試案」では、不安の抗弁権については、次の条文案が提示されていました。
不安の抗弁権
双務契約の当事者のうち自己の債務を先に履行すべき義務を負う者は,相手方につき破産手続開始,再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあったことその他の事由により,その反対給付である債権につき履行を得られないおそれがある場合において,その事由が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは,その債務の履行を拒むことができるものとする。ただし,相手方が弁済の提供をし,又は相当の担保を供したときは,この限りでないものとする。
ア 契約締結後に生じたものであるときは,それが契約締結の時に予見することができなかったものであること
イ 契約締結時に既に生じていたものであるときは,契約締結の時に正当な理由により知ることができなかったものであること
もちろん、この条文案は、明文化が見送られたものです。
このため、この条文案を契約条項のたたき台とする場合、多少アレンジした程度では、規定する意味はありません。
実際に契約条項とする場合は、特に柱書本文の「…その他の事由」について、その契約の実態に適合した条項とするように、大幅に具体化する必要があります。
ポイント
- 不安の抗弁権は、具体的要件の規定が難しい等の理由により、民法改正では明文化が見送れられた。
- 中間試案の条文案は、契約条項のたたき台として使う場合は、そのまま使わず、必ず要件の具体化をするべき。
判例による不安の抗弁権の行使の効果
下級審判例でしか認められていない効果
不安の抗弁権の行使による効果は、具体的には、次のとおりです。
不安の抗弁権の効果
- 後払いの継続的な売買契約・請負契約の場合、受注者は、商品の引渡しを拒絶することができる(東京地裁判決平成2年12月20日)。
- 信用状態の改善のため、物的担保の提供や、保証人の提供を求めることができる(東京地裁判決昭和58年3月3日)。
- 信用状態の改善に応じなければ、契約そのものも解除できる東京地裁判決平成2年12月20日)。
ただし、これらは、下級審の判例でしか認められていない権利です。
つまり、一歩間違えれば、不安の抗弁権の行使が認められず、逆に債務不履行となる可能性もあります。
このため、不安の抗弁権を権利として契約書に規定する場合や、実際に権利を行使する場合には、逆に債務不履行とならないように、細心の注意が必要です。
契約書を作成する理由・目的
下級審でしか認められていない不安の抗弁権を行使するためには、その行使について、適正な要件を規定した契約書が必要となるから。
「不安」な取引はなるべく受発注の前の段階で判断する
なお、現実問題として、不審な発注があった場合は、1回だけの取引であろうと、継続的な取引であろうと、受発注の前に、個別の与信調査をおこないます。
その与信調査の結果、信用できないような相手であれば、取引をしないようにします。
結局のところ、受注する前の慎重な与信調査こそが、最もリスクを軽減する対策であるといえます。
このため、特に継続的な取引の場合、不審な発注を拒否できるよう、受発注の手続きを契約書に明記しておく必要があります。
ポイント
- 不安の抗弁権を行使することで、債務の履行の停止、担保の提供・追加の請求、契約解除ができる。
- ただし、あくまで不安の抗弁権は、下級審での判例でしか認められておらず、最高裁の判例がない。
- 取引に関する「不安」は、受発注の前の段階での与信調査で解消するべき。