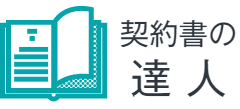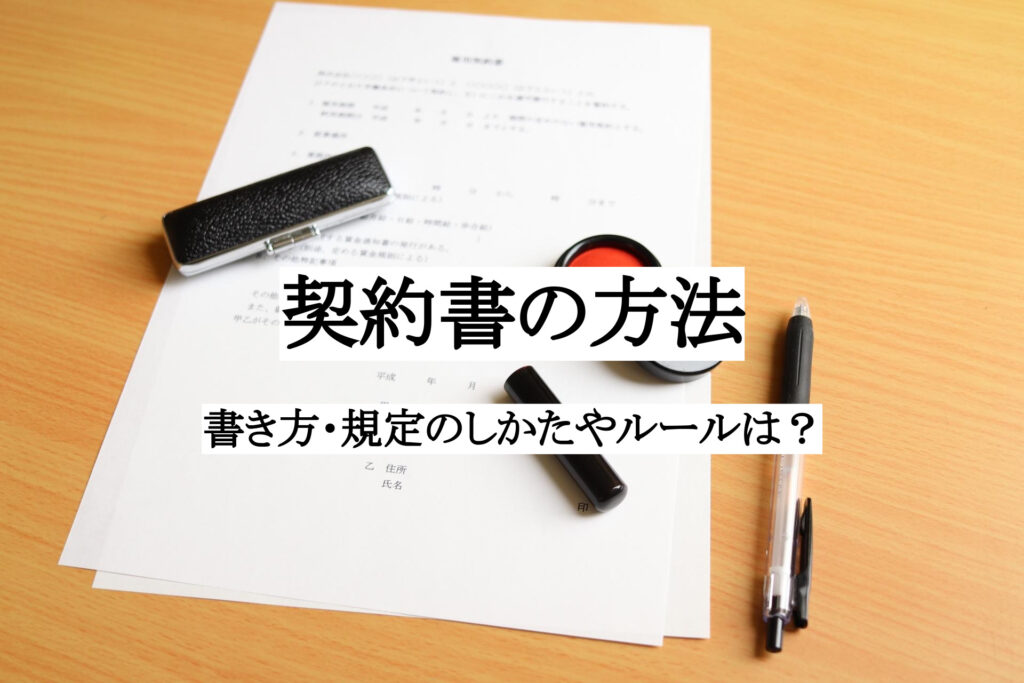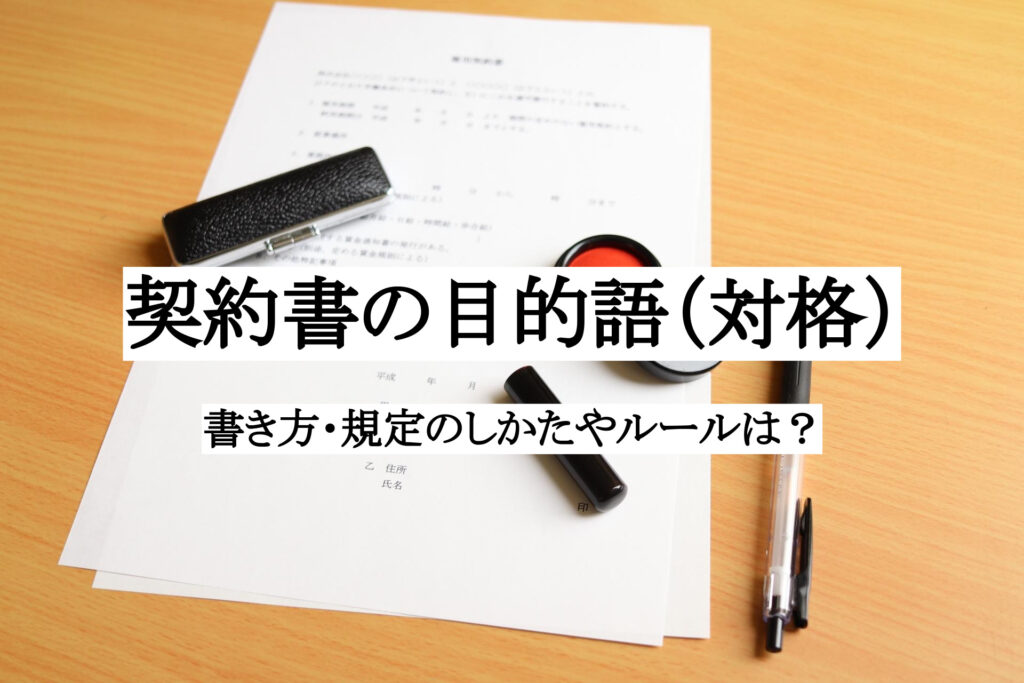このページでは、契約書の書き方のうち、相手方(甲乙・対象・客体)の書き方について解説しています。
相手方というのは、「誰に対して」どうする権利・義務があるのか、つまり権利・義務等の対象、客体のことです。
文法的な表現では、「間接目的語」といいます。
権利や義務の対象となるため、相手方の書き方は、非常に重要となります。
このページでは、このような、契約書における相手方の書き方のポイントや注意点について、わかりやすい解説します。
契約書における相手方の書き方とは?
契約条項の大半は相手方が存在する
契約は、2以上の契約当事者がいることが前提ですので、必ず相手方がいます。
そして、個々の契約条項の大半は、権利と義務が規定されています。
権利や義務は、一方の契約当事者の権利や義務が、相手方にとっての義務や権利となる、という特徴があります。
このため、個々の契約条項においても、主語となる当事者と同様に、相手方の表記が重要です。。
このように、多くの契約条項では、相手方の表記が重要となります。
契約書の客体の書き方は「に、」「に対し、」「に対して、」
契約書において、相手方等の客体の書き方は、通常は、「(誰々)…に、」「(誰々)…に対し、」「(誰々)…に対して、」のいずれかです。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】客体
第○条(報酬の支払い)
甲は、乙に、報酬を支払うものとする。
第○条(報酬の支払い)
甲は、乙に対し、報酬を支払うものとする。
第○条(報酬の支払い)
甲は、乙に対して、報酬を支払うものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
いずれも、日本語としても、契約書の書き方としても、間違いではありません。
ただ、助詞(格助詞)の「に」は、非常に広い意味をもっていますので、条項によっては、誤解の原因となることもあります。
このため、一般的な契約書の書き方としては、客体の書き方は、「…に対し、」か、「…に対して、」を使います。
個人的には、前者の「…に対し、」のほうが、短くてスッキリしていますので、おすすめです。
契約書で相手方を記載する箇所は主語の直後
また、相手方を記載する箇所は、特に法的にも、慣例としても、決まっているわけではありません。
わかりやすさという点では、原則としては、主語の直後としたほうがいいでしょう。
もっとも、これもケース・バイ・ケースで、長い文章の場合は、主語の直後ではなく、述語(動詞)=権利義務の表記の直前のほうがわかりやすい場合があります。
ただ、そもそも、契約書でそれほど文章が長くなるのは、書き方に問題がある可能性があります。
ポイント
- 契約条項の大半は相手方が存在するため、主語の表記と同じくらい重要となる。
- 相手方の書き方は「…に、」「…に対し、」「…に対して、」。ただし、「…に」は他にも意味があるので、なるべく使わない。
- 相手方は主語の直後に記載する。
契約当事者は甲乙などの略称で表記する
「甲乙」「発注者・受注者」「委託者・受託者」等どれでもいい
なお、契約当事者の表記は、「株式会社◯◯は、…」のように、商号=正式名称で表記しても、特に法的には問題はありません。
ただ、契約当事者の表記は、契約書の中では非常に多く記載されます。このため、通常は、略称を使います。
略称は、いわゆる甲乙の表記が最も一般的ですが、他の表記でもかまいません。
契約当事者の略称の具体例
具体的には、次のようなものがあります。
契約当事者の略称・具体例
- 発注者・受注者:企業間契約
- 一方の当事者・他方の当事者:契約全般
- 買主・売主:売買契約
- 委託者・受託者:業務委託契約
- 注文者・請負人:請負契約
- 委任者・受任者:(準)委任契約
- 貸主・借主:貸借契約
- 使用者・労働者:雇用契約・労働契約
- 開示者・被開示者(受領者):秘密保持契約
- ライセンサー・ライセンシー:ライセンス契約
- フランチャイザー(本部)・フランチャイジー(加盟店):フランチャイズ契約
- 本部(サプライヤー)・代理店:代理店契約
- 本部(サプライヤー)・販売店:販売店契約
- ユーザー・ベンダー:システム・アプリ開発契約
契約書では場合によっては第三者が客体となることもある
第三者は再委託・下請負や秘密保持義務の条項で規定する
また、場合によっては、相手方だけではなく、第三者が客体となる場合もあります。
例えば、典型的な例としては、次のような再委託・下請負の条項があります。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】再委託条項
第○条(再委託)
受託者は、第三者に対し、本件業務の全部または一部を再委託してはならない。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
また、秘密保持義務でも、次のように規定します。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】秘密保持義務条項
第○条(秘密保持義務)
甲は、第三者に対し、秘密情報を開示し、または漏えいしてはならない。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
場合によっては第三者の定義が重要となる
【意味・定義】第三者とは?
なお、この「第三者」ですが、一般的な意味でも、また法令用語としても、「(契約)当事者以外の者」という意味・定義になります。
【意味・定義】第三者(契約書)とは?
第三者とは、契約当事者以外の者をいう。
ただ、残念ながら、こうした意味・定義が、必ずしもビジネスの現場では通用しないことがあります。
例えば、子会社・親会社や下請先を第三者と解釈されず、契約当事者と同様に解釈されることがあります。
また、厳密には、契約当事者である法人=会社と、その役員や労働者は同一の人格ではないため、役員や労働者もまた、第三者となります。
特に秘密保持契約では要注意
役員・労働者は第三者・秘密保持義務の例外とする
第三者の定義は、秘密保持契約で特に重要となります。
繰り返しになりますが、秘密保持契約では、次のような秘密保持義務を規定します。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】秘密保持義務条項
第○条(秘密保持義務)
甲は、第三者に対し、秘密情報を開示し、または漏えいしてはならない。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
この規定では、甲が株式会社である場合、甲は、第三者=相手方以外の者、たとえそれが自己の役員や労働者であっても、秘密情報を開示してはいけません。
このため、通常の秘密保持契約や秘密保持義務では、第三者の例外として、必要最低限の役員や労働者に対し、秘密情報を開示できるようにします。
特に再委託先・下請先は第三者であることを徹底する
問題は、親会社・子会社・再委託先・下請先などです。
すでに触れたとおり、親会社・子会社・再委託先・下請先なども第三者ですから、当然、秘密情報は開示してはいけない対象です。
にもかかわらず、特に再委託先や下請先が第三者として扱われず、当事者のように、秘密情報が開示される場合があります。
このため、秘密情報の取扱い重要となる契約では、第三者について、特に厳密に定義を規定して、安易な情報開示がされないように、注意します。
ポイント
- 契約当事者だけではなく、場合によっては第三者が客体となることもある。
- 特に、再委託・下請負や秘密保持義務の条項では、第三者が行為の客体となることがある。
- 第三者とは、契約当事者以外の者。ただし、この意味が通じない、または意図的に無視されることがあるため、要注意。
- 親会社・子会社・再委託先・下請先は第三者。それどころか、厳密には契約当事者である株式会社の役員・労働者も第三者。
- 第三者が重要となる契約では、その定義・例外が重要なる。場合によっては、担当者や経営者レベルの「第三者」の認識が重要となる。
契約書では相手方が関係する条項には相手方を必ず記載する
相手方を省略しても法的には問題ない場合もある
契約書で相手方を書くときに注意するべきことは、とにかくバカ正直に「書く」ということです。
「こんな当たり前のこと、書かなくてもわかるだろう」と思って、勝手に省略してはいけません。
例えば、業務委託契約における報酬の支払いの条項では、報酬は、受託者に対して支払われるのが当然です。
ですから、相手方である受託者に対する部分を省略したからといて、法的なリスクは特ににありません。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】報酬の支払いに関する条項
第○条(報酬の支払い)
受託者は、報酬を支払うものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
しかしながら、通常は、わざわざ相手方を省略して記載することはありません。
契約書では相手方を省略してはいけない
というのも、上記のような、明らかに省略しても法的に問題ない規定は、むしろ少数です。
他の規定は、相手方の表記を省略していいかどうかの判断が、難しい場合もあります。
こうした相手方の省略について、いちいち判断していたら、キリがありませんし、時間の無駄です。
相手方の表記は省略するべき?
相手方の表記を省略するべきかどうかの判断は時間の無駄。よって、そのまま記載しておくべき。
そもそも、相手方の表記をしておくことに問題はないのですから、判断に迷うくらいなら、表記しておくべきです。
このため、よほど冗長な条文になった場合を除いて、相手方の表記は、省略せずに記載します。
相手方を省略するとリーガルチェックで見抜かれる
それ以前の問題として、ヘタに相手方の表記を省略したり、書かなかったりすると、作成者の契約実務の経験や能力が見抜かれます。
というのも、日常的に契約書を作成・起案している専門家は、契約書を書く際、客体を書くことが、一種のクセやスタイルになっています。
契約書の専門家は、契約条項を書く際に、「甲は、」とタイピングした後で、例えば相手方がいる条文では、自然と「乙に対し、」とタイピングします。
これは一種の機械的な処理に近く、タイピングしている時は、わざわざ相手方の表記を省略するかどうかなど、考えていません。
相手方を書くのはクセ・スタイル
日頃から契約書を作成していると、契約条項で相手方を書くのが「クセ・スタイル」となる。このため、相手方が書かれていない条項を見ると、違和感を感じる。
このような事情もあるため、相手方が省略されていたり、相手方が書かれていない契約書を見かけると、経験が浅い作成者のような印象を受けます。
このため、特に契約書の作成の経験が浅い方は、相手方の記載に抜け・漏れ・不必要な省略がないか、十分に気をつけてください。
ポイント
- 相手方を省略しても法的には問題ない場合もある。
- 相手方の省略について、いちいち判断するのは時間の無駄であるため、契約書では相手方を省略しない。
- 契約書の専門家は、クセやスタイルで、契約条項を書く際には、機械的に相手方を書く。このため、相手方がない契約条項には違和感を感じる。
長い契約書では当事者表記のミスに注意する
甲乙が誰なのかを混同せずに作成・チェックをする
当事者の表記を甲乙の略称にした場合、特に、甲が誰で、乙が誰なのかということを混同しないように注意します。
甲・乙のような表現は、日常使うことはほとんどありません。
ですから、契約書を作成していると、どちらがどちらなのか混乱することがあります。
まだ混乱で済めばいいのですが、契約書を作成してい当事者ですら、混同してそのまま書くこともあります。
このため、契約書の作成時はもとより、作成が終わって、推敲の段階であっても、当事者の表記が間違っていないか、念入りにチェックします。
甲乙が逆転していないかチェックする
特にありがちななのが、甲乙が逆転するミスです。
こればかりは、ケアレスミスですので、いくら経験を積んでも防ぐことが難しいミスです。
このため、契約書の作成が終わり、推敲する際には、なるべく複数の人のチェックを受けるなど、念入りにチェックしてください。
また、一括置換の機能を使って、甲乙表記を、敢えて法人名=商号にしてチェックする方法も効果的です。
この場合、チェックが終わったら、再度一括置換で甲乙表記に戻します。
ポイント
- 契約当事者の表現で甲乙等の略称を使う場合は、契約書作成の際、混同や逆転に注意する。
- 契約当事者の混同や逆転のチェックのためには、複数人のチェックが有効。
契約書の相手方に関するよくある質問
- 契約書の相手方については、どのように表現しますか?
- 契約書の相手方は、主語の直後に、「(誰々)…に、」「(誰々)…に対し、」「(誰々)…に対して、」のいずれかで表現します。
- 契約書の相手方や当事者の略称・表現の具体例を教えて下さい。
- 契約書の相手方や当事者の略称・表現の具体例としては、以下のものがあります。
- 発注者・受注者:企業間契約
- 一方の当事者・他方の当事者:契約全般
- 買主・売主:売買契約
- 委託者・受託者:業務委託契約
- 注文者・請負人:請負契約
- 委任者・受任者:(準)委任契約
- 貸主・借主:貸借契約
- 使用者・労働者:雇用契約・労働契約
- 開示者・被開示者(受領者):秘密保持契約
- ライセンサー・ライセンシー:ライセンス契約
- フランチャイザー(本部)・フランチャイジー(加盟店):フランチャイズ契約
- 本部(サプライヤー)・代理店:代理店契約
- 本部(サプライヤー)・販売店:販売店契約
- ユーザー・ベンダー:システム・アプリ開発契約