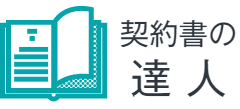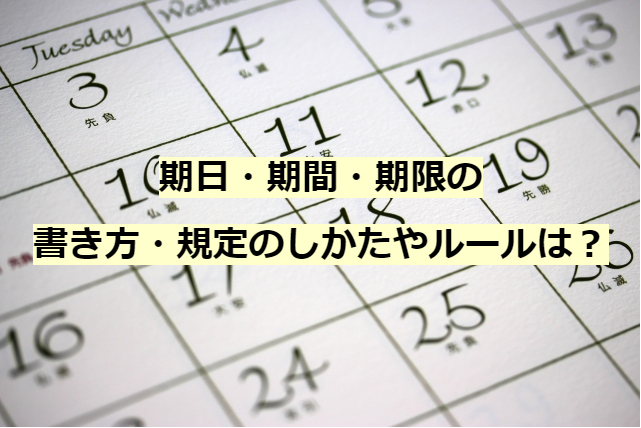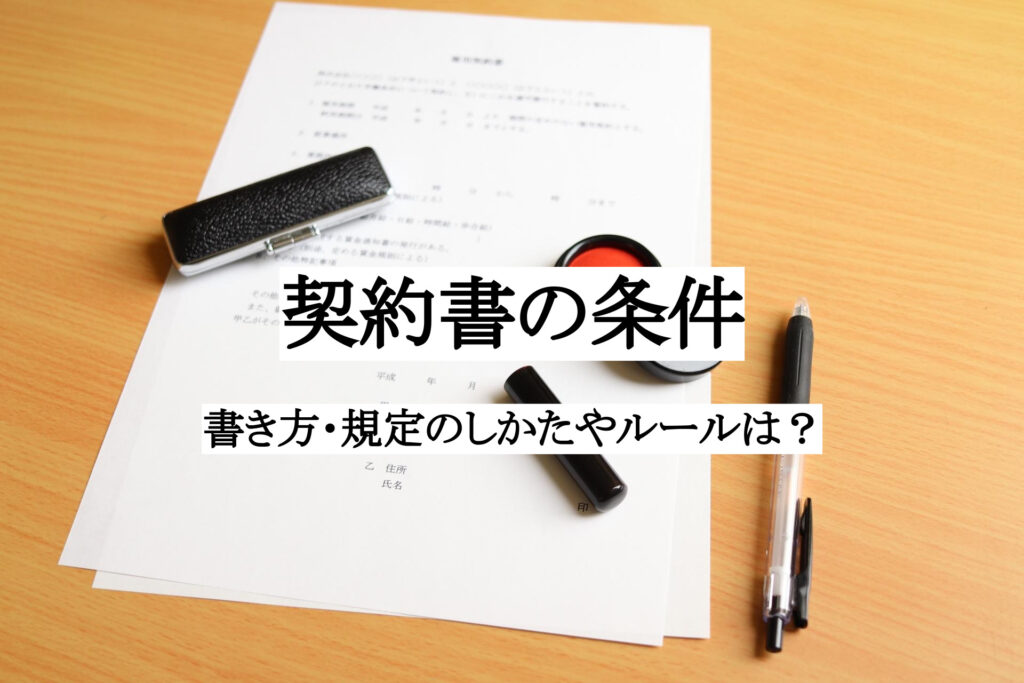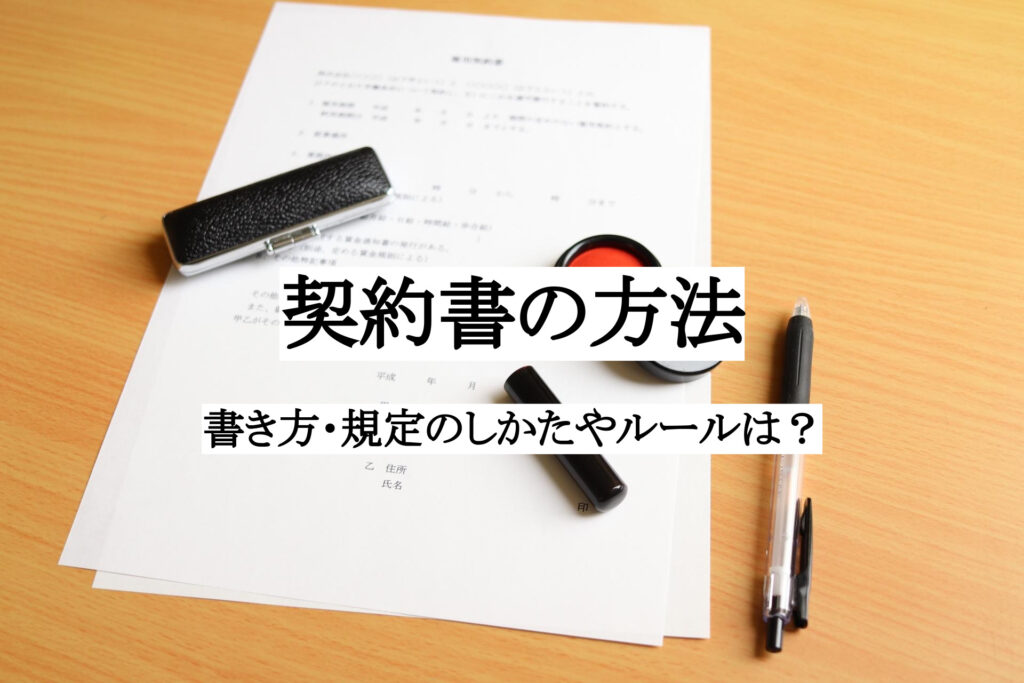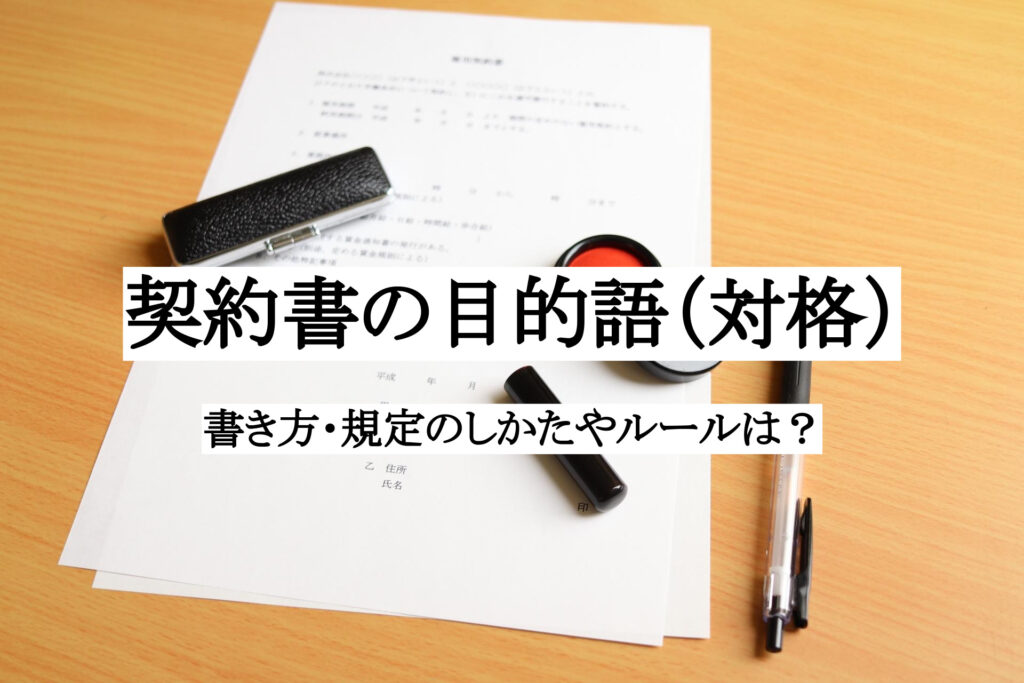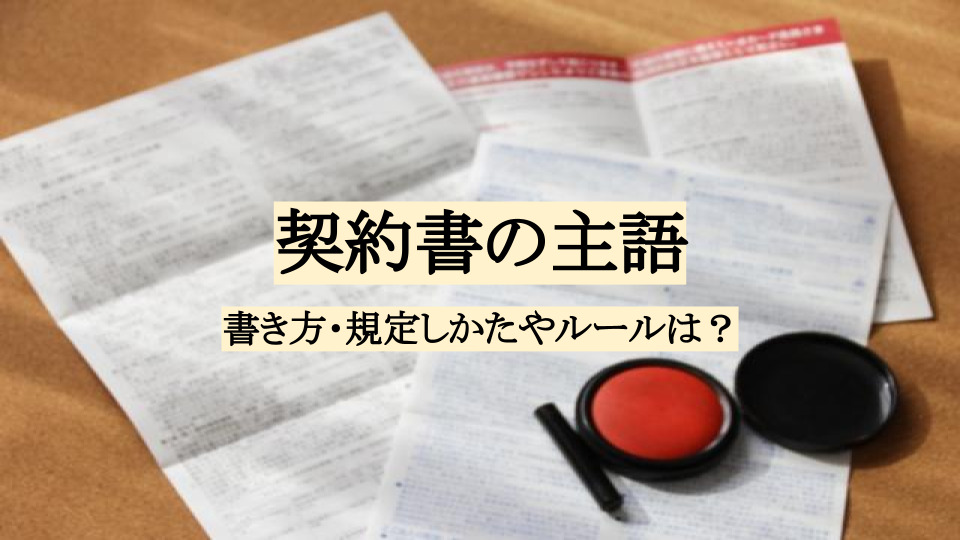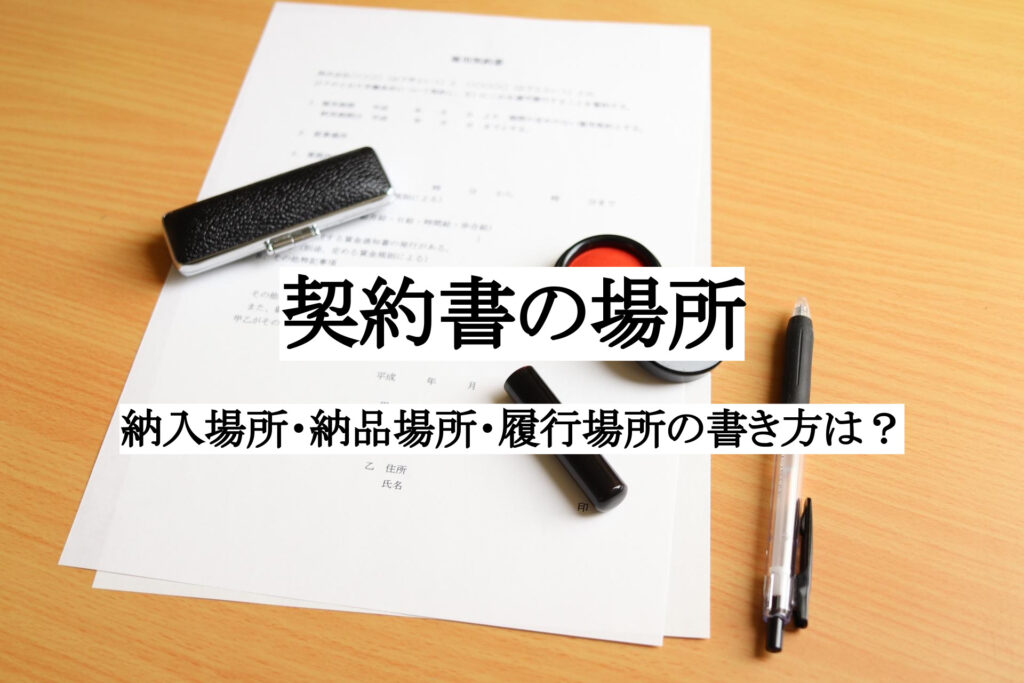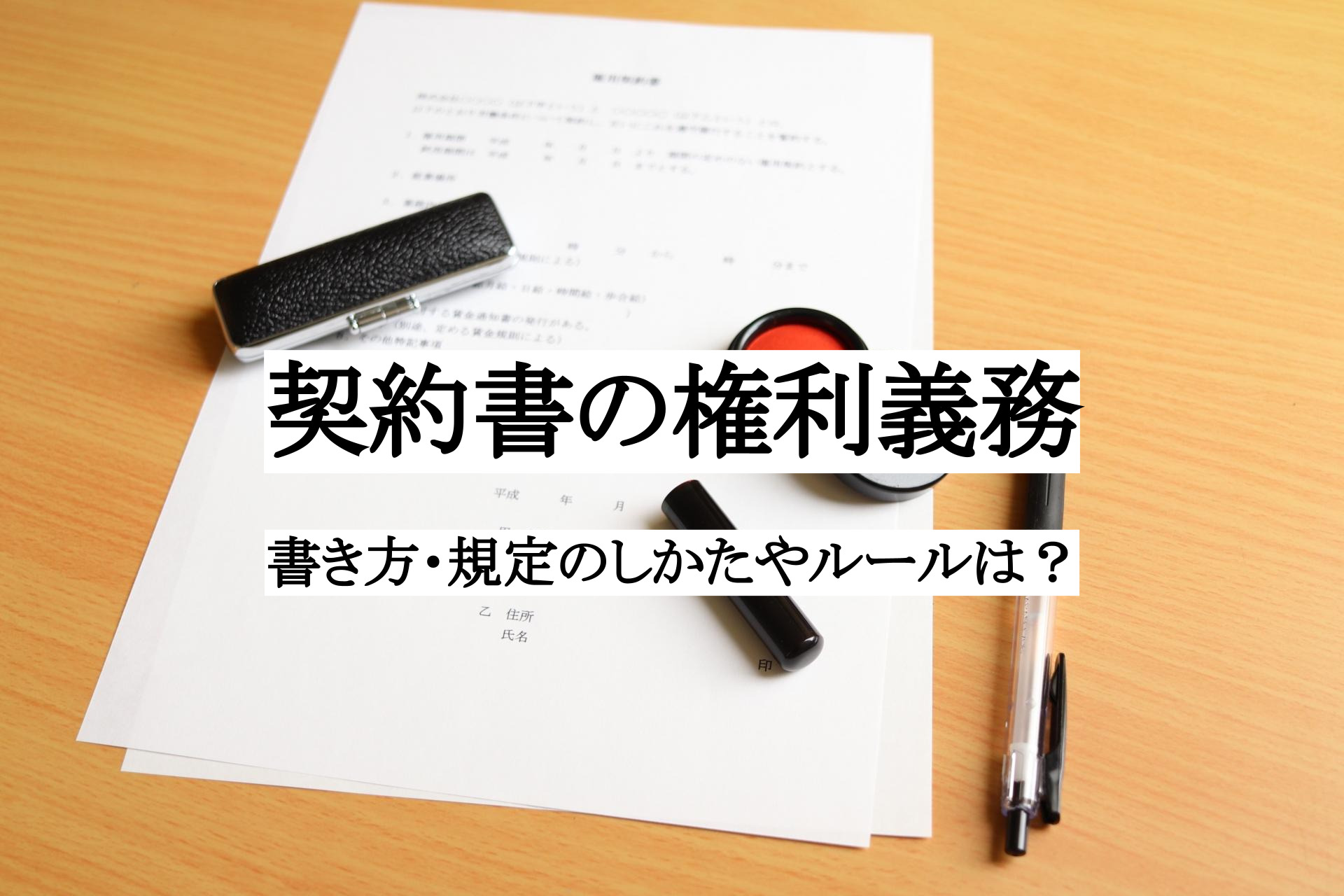
このページでは、契約書の書き方のうち、述語の書き方について解説しています。
契約書は、ほとんどの文章で、契約当事者の権利または義務のいずれかを規定します。
このため、契約書の文章では、述語は、権利と義務のどちらであるかがわかるように記載しなければなりません。
このページでは、こうした述語=権利義務の書き方について、解説します。
契約書の述語には当事者の権利義務を表現する
契約文章は用語の定義か権利義務のいずれか
契約書の文章は、大きく分けて、用語の定義か、契約当事者の権利義務のいずれかがの表現です。
用語の定義は、最近の契約書では、契約条項の冒頭の部分(多くは第2条)でまとめて規定します。
これ以外の規定は、ほとんどが、契約当事者の権利義務についての規定です。
このため、大半の規定が、契約当事者の権利義務を規定した条項です。
権利か義務かは述語の末尾の書き方で判断する
契約当事者の権利義務を規定した条項では、述語の書き方によって、権利か義務のいずれかを判断します。
もちろん、「甲は、◯◯の権利を有する。」や「乙は、◯◯の義務を有する。」のような、古い書き方もないわけではありません。
ただ、こうした書き方は、非常に堅苦しい書き方となるため、契約書を読む側にとっては、負担となります。
このため、通常は、「◯◯できるものとする。」(権利)や「〇〇しなければならない。」(義務)のような書き方をします。
ポイント
- 契約書の文章は、ほとんどが契約当事者の権利義務を表現するもの。
- 述語が権利なのか義務なのかは、文末の表現で判断する。
契約書における権利義務の書き方は?
契約書における権利の書き方
契約書における権利の書き方は、非常にシンプルで、「◯◯できる。」または「◯◯できるものとする。」です。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】受領証書に関する条項
第○条(受領証書の交付)
受注者は、発注者に対し、本件製品の納入と引換えに、受領証書の交付を求めることができる。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
【契約条項の書き方・記載例・具体例】費用負担
第○条(費用負担)
受注者は、発注者に対し、料金とは別に、本件業務の実施に要する実費の負担を求めることができるものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
契約書における作為の義務の書き方
契約書において、作為の義務(=何かをする義務)の書き方は、「〇〇するものとする。」または「〇〇しなければならない。」です。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】納入条項
第○条(納入)
受注者は、納入場所に持込むことにより、本件製品を納入するものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
【契約条項の書き方・記載例・具体例】支払条項
第○条(支払い)
発注者は、本契約に従い、受注者に対し、本件製品の対価の支払いをしなければならない。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
なお、前者の「◯◯するものとする。」については、義務を規定する書き方ではない、とする見解もあります。
もっとも、すべての作為義務の条項で、「〇〇しなければならない。」という書き方にした場合は、非常に厳しい印象を与える契約書となります。
契約書における不作為義務の書き方
契約書において、不作為の義務(=何かをしない義務)の書き方は、「◯◯しないものとする。」または「◯◯してはならない。」です。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】知的財産権の侵害に関する条項
第○条(知的財産権の侵害)
受注者は、本件業務の実施により、第三者の知的財産権を侵害しないものとする。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
【契約条項の書き方・記載例・具体例】秘密保持義務
第○条(秘密保持義務)
発注者および受注者は、秘密情報を第三者に対し開示し、または漏えいしてはならない。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
「◯◯できない。」は義務の規定ではない
「○○できない。」は権利・権原・権限が無いこと
なお、義務と似たような表現で、「◯◯できない。」または「◯◯できないものとする。」という表現があります。
これは、義務の表現ではなく、権利・権限・権限がないことを意味する表現です。
法律の条文としてはよく見かける表現ですが、契約書では、滅多に規定されることはありません。
「○○できない。」は債務不履行ではなく無効となる
なお、権利・権原・権限がない行為(=瑕疵ある行為)をしてしまった場合の法的な効果としては、その行為が無効となる程度です。
義務に違反した場合とは異なり、理論上は、債務不履行=契約違反とはなりません。
ただし、裁判で争われた場合は、実態に応じて判断されることとなります。
ポイント
- 権利は「〇〇できる。」「〇〇できるものとする。」で表現する。
- 作為の義務は「〇〇しなければならない。」「〇〇するものとする。」で表現する。
- 不作為の義務は「〇〇してはならない。」「〇〇しないものとする。」で表現する。
- 「〇〇できない。」「〇〇できないものとする。」は、義務の規定ではなく、権利・権限・権原がないことを意味する表現であり、契約書ではめったに使わない。
契約書の契約条項は権利義務がわかるように明記する
面倒でもすべての契約条項で権利義務がわかるように規定する
このように、契約書の文章を起案する際は、必ず述語・文末を意識して、誰の権利義務かがわかるように記載します。
ある程度、契約書の作成の経験を積むと、特に意識せずに述語・文末で権利義務を表現できるようになりますので、そのレベルまでは、意識的に述語・文末を書くようにします。
もちろん、単に契約書の述語・文末の記載で、権利義務が明記されていなかったとしても、実際の裁判では、他の条項や証拠などから、総合的に判断されます。
このため、明らかにどちらの権利義務であるかが判断できるような条項では、述語・文末の記載が問題になることはありません。
権利義務のどちらとも解釈できる可能性もある
契約条項によっては権利義務の解釈が分かれる場合もある
ただ、契約条項によっては、権利・義務のどちらとも解釈できるようなものもあります。
例えば、OEM生産の基本契約書などには、次のような条項があります。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】技術指導に関する条項
第○条(技術指導)
本製品の品質を担保するために必要と認めた場合、甲は、乙に対して、必要な技術指導をおこなう。
(※甲=発注者 乙=受注者。便宜上、表現は簡略化しています)
上記のような表現では、「技術指導をおこなう。」としか記載がありませんので、甲の権利なのか義務なのかが明確ではありません。
権利とする場合は、「技術指導をできる。」「技術指導をできるものとする。」とし、義務とする場合は、「技術指導をしなければならない。」「技術指導をするものとする。」とします。
技術指導は権利であり義務でもある?
上記の記載例では、そもそも「本製品の品質を担保するために必要と」誰が認めるのか、という問題があります。
それは別としても、「技術指導をおこなう主体が甲である」ということは明らかですが、特に権利義務について記載されていません。
この点につき、甲乙それぞれの立場で、甲の権利または義務(逆に言えば乙の義務または権利)と解釈できます。
技術指導における甲乙それぞれの思惑・立場
- 甲:そもそも請負契約であるOEM生産の契約では、一定の品質を確保するのは乙の義務であるため、技術指導は甲の権利であり、乙は技術指導を受ける義務がある。また、技術指導に要する費用は乙の負担とするべき。
- 乙:甲が要求する仕様に従って生産している以上、甲には、その技術指導をする責任と義務がある。従って、(乙が)必要と認めた場合、甲は、乙に技術指導をする義務がある。まt、技術指導に要する費用は甲の負担とするべき。
このように、当事者の立場によっては、権利義務の解釈が完全に対立することもあり得ます。
このため、必ず述語・文末の記載は、権利・義務のいずれかがわかるように、明確に記載します。
ポイント
- 面倒でも、すべての契約条項について、権利義務のいずれかがわかるように規定する。
- 文章の表現によっては、契約当事者のいずれの権利義務とも解釈できる可能性がある。
契約書の権利義務(術後)に関するよくある質問
- 契約書の述語には何を書きますか?
- 契約書の述語には、権利・義務のいずれかを規定します。
- 契約書では、権利義務はどのように書きますか?
- 契約書では、権利義務は、以下のいずれかで書きます。
- 権利は「〇〇できる。」「〇〇できるものとする。」で表現する。
- 作為の義務は「〇〇しなければならない。」「〇〇するものとする。」で表現する。
- 不作為の義務は「〇〇してはならない。」「〇〇しないものとする。」で表現する。