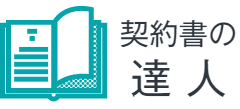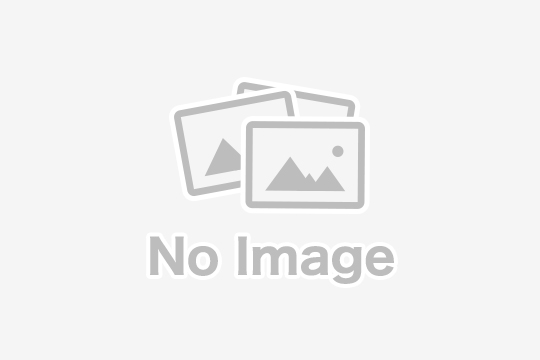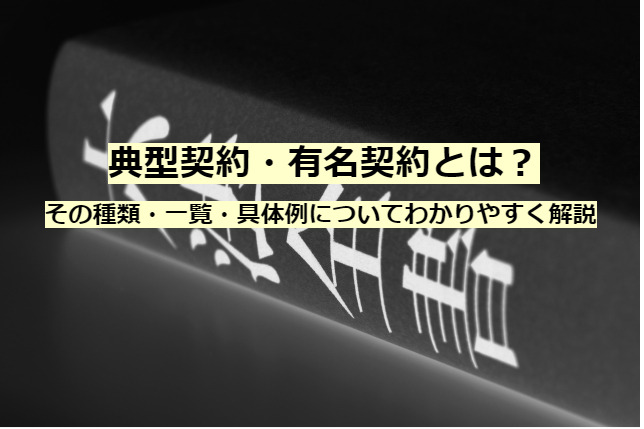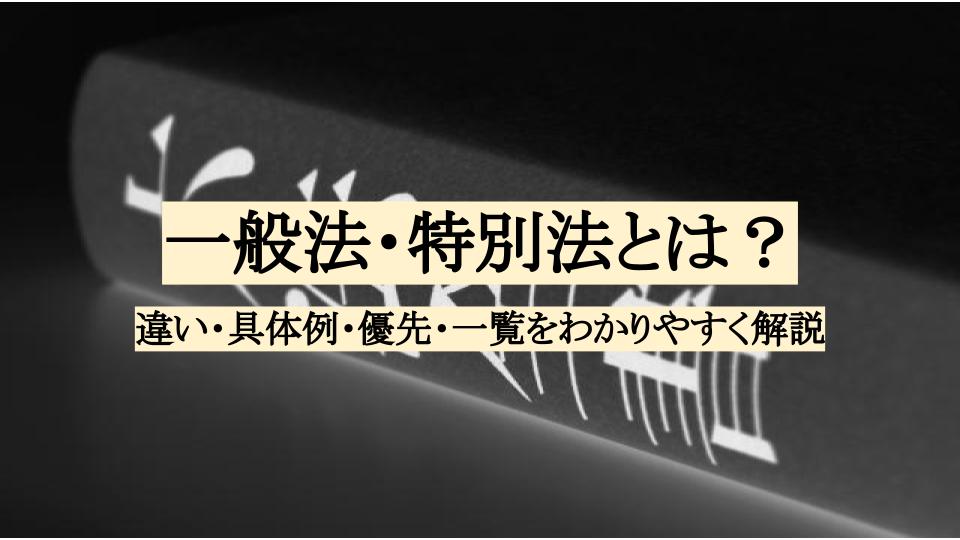
一般法とは、ある特定の事項について、一般的に適用される法律のことです。
特別法とは、一般法が適用される事項のうち、特定の事項に限定して適用される法律のことです。
契約実務においては、一般法も特別法もどちらも重要ですが、特に特別法に気をつける必要があります。
このページでは、こうした一般法・特別法の定義、違い、具体例、どちらが優先するのかなどのポイントについて、くわしく解説します。
【意味・定義】一般法とは?
一般法とは、ある事項全般について一般的に適用される法律のことです。
【意味・定義】一般法とは?
一般法とは、ある事項全般について、一般的に適用される法律をいう。
例えば、私人間の民事上の事項全般については、民法が一般法として適用されます。
これが、民法が「私法の一般法」といわれる理由です。
【意味・定義】特別法とは?
特別法とは、ある特定の事項について、一般法よりも優先して適用される法律のことです。
【意味・定義】特別法とは?
特別法とは、ある特定の事項について、一般法よりも優先して適用される法律をいう。
例えば、商人による取引については、民法の特別法として、商法が優先して適用されます(商法第1条)。
また、事業者と労働者との雇用契約・労働契約には、民法の雇用(第623条以下参照)の規定よりも、労働基準法や労働契約法が優先して適用されます。
同様に、不動産の賃貸借には、民法の賃貸借(第601条以下参照)の規定よりも、借地借家法が優先して適用されます。
一般法・特別法の具体例・一覧
一般法・特別法の具体例
- 民法(一般法)<商法(商人の取引に適用される特別法)
- 民法(一般法)<労働基準法や労働契約法(事業者と労働者の雇用契約・労働契約に適用される特別法)
- 民法(一般法)<借地借家法(土地・建物の賃貸借契約に適用される特別法)
- 民法(一般法)<独占禁止法(主に企業間取引に適用される特別法)
- 独占禁止法(一般法)<下請法(企業間取引のうち、資本金に差がある事業者による一部の取引に適用される特別法)
一般法・特別法の優先は?
特別法は一般法に優先する・特別法は一般法を破る
法学の世界では、「特別法は一般法に優先する」「特別法は一般法を破る」という言葉があります。
これは、ある特定の条件のもとでは、一般法よりも特別法が優先して適用されることを意味した言葉です。
これを「特別法優先の原則」ともいいます。
【意味・定義】特別法優先の原則とは?
特別法優先の原則とは、特定の事項について、特別法が一般法に優先して適用される原則をいう。
特定の事項以外は一般法が優先する
なお、特別法が優先するのは、あくまで特別法に規定された特定の事項についてのみです。
逆に言えば、特別法に規定された特定の事項以外の部分については、一般法が適用されます。
例えば、すでに触れたとおり、商法は民法の特別法とされ、商人による商取引(一般的な企業間取引)では、民法よりも商法が優先して適用されます(商法第1条)。
商法第1条(趣旨等)
1 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
引用元:商法 | e-Gov法令検索
より正確には、商慣習や一般の慣習など、次のような細かな優劣関係があります。
この優先順位も、あくまで「他の法律の特別の定め」や商法に規定がある部分のみとなります。
一般法と特別法は相対的な関係
一般法と特別法の関係は、絶対的なものではなく、相対的なものです。
つまり、ある法律が一般法であるとか、特別法であるとかいうように決まっているものではありません。
このため、法律Aと法律Bの関係が一般法(法律A)と特別法(法律B)の関係であっても、法律Bと法律Cの関係が一般法(法律B)と特別法(法律C)であることがあります。
一般法と特別法の相対性の具体例
同じ独占禁止法でも、関係性によっては、一般法になり、特別法にもなる。
- 独占禁止法の一部の規定は、民法の特別法。この関係では独占禁止法が特別法であり、民法は一般法。
- 下請法の一部の規定は、独占禁止法の特別法。この関係では独占禁止法は一般法であり、下請法は特別法。
企業間取引における一般法・特別法の具体例・優先順位
下請法>独占禁止法>(「他の法律の特別の定め」(商法第1条第1項)>商法>商慣習>「任意規定と異なる慣習」(民法第92条)>民法
なお、法律間の優劣については、明文で規定されていないこともありますので、常に気をつけなければなりません。
ポイント
- 特定の条件のもとでは特別法が優先して適用される。
- 一般法と特別法は相対的なものであり、それぞれの関係性によって、ある法律が、一般法となることもあれば、特別法になることもある。
契約実務では一般法・特別法ともに重要
「民法は私法の一般法」
すでに触れたとおり、「民法は私法の一般法」と言われる法律です。
このため、ほとんどの契約では、一般法として、民法が適用されます。
こうした事情から、どのような契約にとっても、民法は、最も重要な法律であるといえます。
ですから、どのような業界であれ、契約実務に関わるのであれば、民法の規定を知らなければなりません。
契約実務で重要となる(主に民法の)特別法一覧
しかしながら、契約に適用されるのは、民法だけではありません。
契約において適用される特別法は、数多くあります。
主要なものでも、以下のものがあります。
契約実務で重要となる特別法の具体例一覧
- 商法
- 会社法
- 建設業法
- 労働者派遣法
- 労働基準法・労働契約法
- 独占禁止法
- 下請法
- 借地借家法
- 消費者契約法
- 特定商取引法
- 金融商品取引法
- 利息制限法
- 貸金業法
契約実務においては、民法の他に、これらの特別法についても、慎重に検討する必要があります。
ポイント
- 契約実務において、「私法の一般法」である民法は、最も重要な法律。
- 契約に適用される法律は、民法以外にも、多数の特別法がある。
特別法に違反は事業の根幹に関わるリスク
特別法により契約条項が無効となることが多い
民法の特別法は、特定の契約当事者を保護することを目的とした法律であることが多いです。
その目的から、多くの規定が強行規定となっているからです。
このため、せっかく苦労して契約書を作成しても、その内容の規定が特別法に違反するために、無効となることがあります。
この点から、契約実務においては、民法の特別法は、民法以上に慎重に検討しておかなければなりません。
契約に適用される特別法の多くは弱者保護のための法律
契約実務に関する特別法は、弱者の保護という、政策的配慮のために作られているものが多いです。
例えば、すでに触れた特別法は、次のような目的で制定されています。
特別法の保護対象
- 建設業法:建設工事の発注者・下請の建設業者
- 労働者派遣法:派遣労働者
- 労働基準法・労働契約法:労働者
- 独占禁止法:劣位の事業者
- 下請法:下請事業者
- 借地借家法:借地人・借家人
- 消費者契約法:消費者
- 特定商取引法:消費者
- 金融商品取引法:金融商品等の購入者等
- 利息制限法:金銭消費貸借契約の債務者
- 貸金業法:金銭消費貸借契約の債務者
このように、特別法は、立場の弱い当事者を保護する目的があることから、強行規定が数多く存在します。
その理由は、特別法の規定を強行規定ではなく任意規定としてしまうと、立場の強い当事者による不当な要求が、当事者間の合意として、有効となってしまうからです。
特別法違反は罰則が科されることもある
また、上記のような法律は、立場の弱い当事者を保護することが目的である以上、立場の強い者にとっては、不利な内容となっています。
もちろん、法律を守らない者への対策として、ほとんどの特別法では、罰則や行政処分の規定があります。
これらの特別法を守らなければ、罰金、懲役、営業停止処分、許認可の取消しなど、事業の根幹に関わる結果となる可能性もあります。
このため、契約書を作成する際には、特に、特別法に違反しないようにしなければなりません。
なお、任意規定と強行規定については、詳しくは、それぞれ次のページをご覧ください。
ポイント
- 特別法により、契約条項が無効となることが多い。
- 契約に適用される特別法の多くは、弱者保護のための法律。
- 特別法に違反すると、罰則が科されたり、行政処分がくだされたりすることもある。
一般法・特別法に関するよくある質問
- 一般法・特別法とは何ですか?また、どのような具体例がありますか?
- 一般法・特別法の意味は、それぞれ次のとおりです。
- 一般法とは、ある事項全般について、一般的に適用される法律のこと。
- 特別法とは、ある特定の事項について、一般法よりも優先して適用される法律のこと。
- 一般法・特別法には、どのような具体例がありますか?
- 一般法と特別法の具体例は、以下のとおりです。
- 民法(一般法)<商法(商人の取引に適用される特別法)
- 民法(一般法)<労働基準法や労働契約法(事業者と労働者の雇用契約・労働契約に適用される特別法)
- 民法(一般法)<借地借家法(土地・建物の賃貸借契約に適用される特別法)
- 民法(一般法)<独占禁止法(主に企業間取引に適用される特別法)
- 独占禁止法(一般法)<下請法(企業間取引のうち、資本金に差がある事業者による一部の取引に適用される特別法)
- 一般法・特別法の優先はどのようになっていますか?
- 一般法・特別法の優先は、適用される事項に応じて、次のとおりです。
- 特別法に規定がある特定の事項=特別法が優先
- 特別法に規定がない事項=一般法が適用