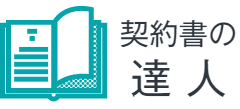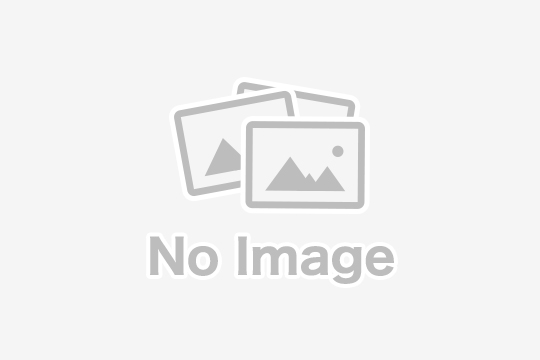このページでは、連帯保証契約とそのリスクについて解説しています。
連帯保証契約は、保証契約のうち、主たる債務社と連帯したもののことです。
連帯保証契約は、単なる保証契約とは異なり、連帯保証人がさあざまな権利の成約を受けます。
このため、連帯保証人となる連帯保証契約は、可能な限り避けるべき契約と言えます。
このページでは、こうした連帯保証契約の意味や定義、そしてそのリスクについて解説していきます。
【意味・定義】連帯保証契約とは?
【意味・定義】連帯保証契約とは?
「連帯保証契約」とは、連帯保証人が債権者に対し債務者(主たる債務者)による債務の履行を連帯して保証する契約をいう。
連帯保証契約は、保証契約の一種であり、連帯保証人が債権者に対して主たる債務者と連帯して保証をする契約です。
逆にいえば、単なる保証契約は、保証人が債権者に対して主たる債務者とは連帯せずに保証する契約となります。
【意味・定義】保証契約とは?
保証契約とは、主たる債務者が債務を履行しない場合において保証人が債権者に対しその債務の履行を保証する契約をいう。
民法第446条(保証契約)
1 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
よく勘違いされがちですが、連帯保証契約は、連帯保証人と主たる債務者との契約ではなく、連帯保証人と債権者との契約です。
連帯保証契約は、一般的によく知られている有名な契約であり、危険性もよく指摘されています。
連帯保証契約は金銭消費貸借契約に関係する契約
保証契約は他の契約に紐付いた契約
保証契約は、何か他の契約の債務を保証する契約のことです。
このため、保証契約自体は、独立して存在することはあり得ず、常に他の債務(主たる債務)に紐付いて存在します。
民法第447条(保証債務の範囲)
1 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
このように、保証契約が他の債務に従って存在することを「保証契約の附従性」といいます。
連帯保証契約は主に金銭消費貸借契約に付随する契約
一般的な連帯保証契約は、金銭消費貸借契約の債務(=金銭債務)の保証のために締結されることが多いです。
いわゆる「借金の保証人」になる契約が、連帯保証契約です。
このほか、次のような継続的な契約の支払いに関して、連帯保証契約が締結されることがあります。
連帯保証契約が締結される主たる債務の契約
- 取引基本契約(売買・請負)
- 販売店契約
- リース契約
- (土地・建物・不動産)賃貸借契約
- フランチャイズ契約
これらの契約の場合は、法人としての会社が締結した契約に関して、代表取締役個人が、会社の契約の相手方と連帯保証契約を締結することが多いです。
連帯保証契約は契約書が必須の契約
連帯保証契約を含む保証契約は、書面を作成しなければ成立しない契約です。
このように、契約の成立に一定の要式が必要な契約を、要式契約といいます。
【意味・定義】要式契約とは?
要式契約とは、契約の成立に契約書の作成・取交しが必要なものをいう。
民法第446条(保証契約)
1 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
このため、連帯保証契約を締結する場合は、契約書の作成は必須です。
契約書を作成する理由・目的
保証契約は、契約の成立に契約書の交付が必須である要式契約だから。
もっとも、債権者としては、連帯保証契約のような重要な契約は、当然ながら、口頭で締結するべきではありません。
ポイント
- 保証契約は他の契約に紐付いた、「附従性」がある契約。
- 連帯保証契約は、主に金銭消費貸借契約に付随する契約。
- 事業上の継続的な契約に付随する連帯保証契約もある。この場合は、会社が主たる債務者となり、その会社の代表取締役が連帯保証人となる場合が多い。
- 連帯保証契約は、成立するために契約書が必須の「要式契約」。
連帯保証人にはなってはいけない
連帯保証契約は連帯保証人にとって一方的なリスクしかない
連帯保証契約は、(特に第三者である)連帯保証人にとって、まったくメリットのない契約です。
それどころか、連帯保証契約は、連帯保証人にとっては、一方的にリスクだけを負担させられるうえ、リターンがありません(保証料を設定した場合を除く)。
最も一般的な事例として、金銭消費貸借を例に挙げると、連帯保証人は、お金を借りているわけでもないのに、(主たる)債務者とほぼ同等のリスクを負うことになります。
逆にいえば、お金を貸している債権者にしてみれば、連帯保証人が多ければ多いほど、借金の返済を請求できる相手が増えることになります。
連帯保証人は主たる債務者と同じ立場に立たされる
連帯保証契約では、債権者は主たる債務者に返済の請求にせずに、いきなり連帯保証人に返済を請求することができます。
また、たとえ主たる債務者に財産があろうとも、連帯保証人には、この請求を断ることができません。
しかも、請求される金額についても、債権者が自由に決めることができるため、最悪の場合、債務の全額を負担することになります。
このように、連帯保証人は、債権者との関係では、主たる債務者とほとんど同じ立場に立たされ、非常に大きなリスクを負うことになります。
連帯保証人は主たる債務者の財産状態を把握できない
主たる債務者と同一の義務を負うにもかかわらず財産状態を把握できない
さらに、連帯保証人は、主たる債務者の財産の状況や信用状態を把握できない、というデメリットもあります。
つまり、主たる債務者が借金を返せるかどうかということを知ることができない、ということです。
主たる債務者の心理としては、連帯保証人に対して「借金を返せそうにない」などとは言いません。
ですから、連帯保証人にしてみれば、事実上、主たる債務者と同一の義務を負うにもかかわらず、リスクがまったくわからない状況がずっと続くことになるわけです。
【改正民法】一定の条件のもとでは債務の内容や財産状態を把握できる
債務の金額等は把握できる
なお、改正民法により、主たる債務者による債務の履行状況について、債権者が保証人に対して情報提供をするよう、義務づけられました。
民法第458条の2(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
ただし、これは、「保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合」に限ります。
また、情報についても、mあくまで債務の元本、利息、違約金、損害賠償等の不履行の有無、残額、弁済期(支払いの期限)が到来していないものの金額の情報に限られています。
このため、連帯保証人は、主たる債務者の財産状態などについては、依然として把握することができません。
期限の利益の喪失について把握できる
また、同様に、改正民法により、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合も、連帯保証人は、債権者から通知を受けることができます。
【意味・定義】期限の利益とは?
期限の利益とは、期限の到来までは、債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益をいう。
【意味・定義】期限の利益の喪失とは?
期限の利益の喪失とは、債務者の期限の利益が喪失し、期限の到来前に、債務の履行を求められることをいう。
民法第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
1 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
3 前2項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
ただ、「期限の利益を喪失したとき」は、すでに主たる債務者による債務の履行は望めない状態となっている場合がほとんどでしょう。
このため、通知を受けたとしても、対策の打ちようがありません。
この点から、この改正民歩第458条の3の規定も、連帯保証契約のリスクの軽減には繋がりません。
この他、期限の利益の喪失条項につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
ポイント
- 連帯保証契約は、連帯保証人にとって一方的なリスクしかない契約。
- 連帯保証人は、主たる債務者と同じ立場に立たされる。
- 連帯保証人は、主たる債務者の財産状況を把握できない。
- 改正民法により債権者に対し保証人に対する情報提供義務が課されたものの、保証人のリスクの軽減にはならない。
保証契約と連帯保証契約の違いは?
連帯保証契約ではなく、単なる保証契約であれば、保証人は、まだ保護される余地があります。
保証契約と連帯保証契約の違いは、次のとおりです。
| 保証契約 | 連帯保証契約 | |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | 有り。 主たる債務者のへの請求を先にするように抗弁できる。 | 無し。 主たる債務者のへの請求を先にするように抗弁できない。 |
| 検索の抗弁権 | 有り。 主たる債務者に財産がある場合、その財産から先に取り立てるように抗弁することができる。 | 無し。 主たる債務者に財産がある場合であっても、その財産から先に取り立てるように抗弁することができない。 |
| 分別の利益 | 有り。 債権者から請求される金額は、保証人の数に応じて軽減される。 | 無し。 債権者から請求される金額は、保証人の数に応じて軽減されず、債務の全額であっても請求されることもある。 |
「連帯」の二文字が有るか無いかで、これほどの差があります。
逆にいえば、これだけの差があるため、実態としては、ほとんどの保証契約が連帯保証契約(または根保証契約)であるといわれています。
連帯保証人にはなってはいけない
第三者のために連帯保証人になるメリットはまったくない
以上のように、連帯保証という制度は、連帯保証人にとって極めて不利な制度です。
実際の連帯保証契約では、期間の制限が無かったり、金額に関しても、場合によっては根保証になっていたりと、極めて高いリスクが伴います。
このため、まったく関係がない第三者の連帯保証人には、なるべきではありません。
せいぜい、自身が代表取締役になっている会社の契約(特に事業上の融資の金銭消費貸借契約)の連帯保証人になるくらいしか、検討してはいけません。
すでに成立した連帯保証契約は解約できない
また、既に連帯保証人になってしまっているという方は、連帯保証契約そのものをどうにかするのは、難しいと言わざるを得ません。
というのも、現在の法制度では、適正な手続きの下で締結してしまった連帯保証契約を、連帯保証人から一方的に解約することはできません。
このため、既に連帯保証人になってしまっている方は、残念ながら、連帯保証契約から逃れる対策を検討するのは時間の無駄です。
むしろ、万が一問題が発生した場合に備えて、主たる債務者とともにその問題を乗り越えていく方向で対策を講じていくべきです。
ポイント
- 第三者のために連帯保証人になるメリットは、まったくない。
- すでに成立した連帯保証契約は解約できない。