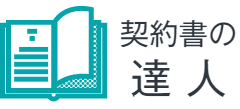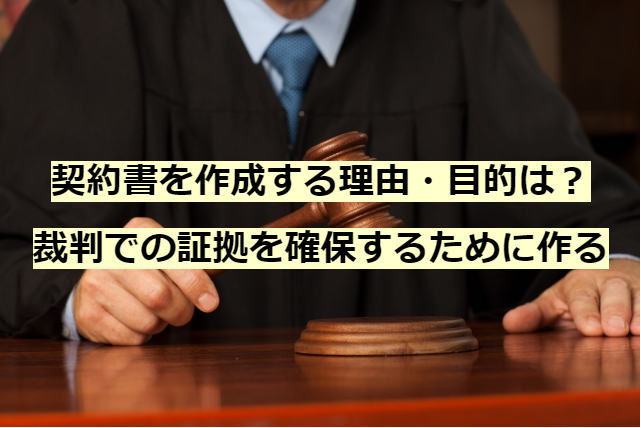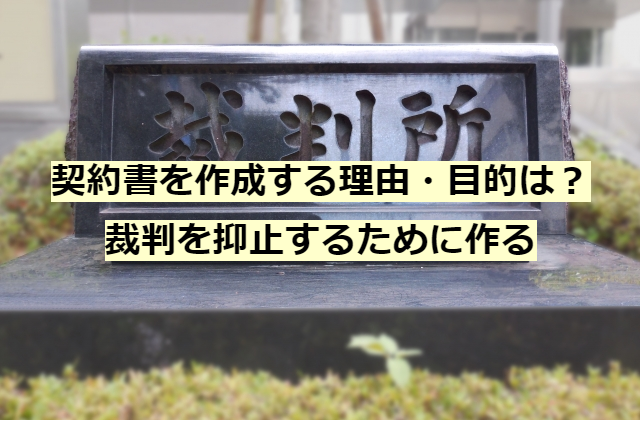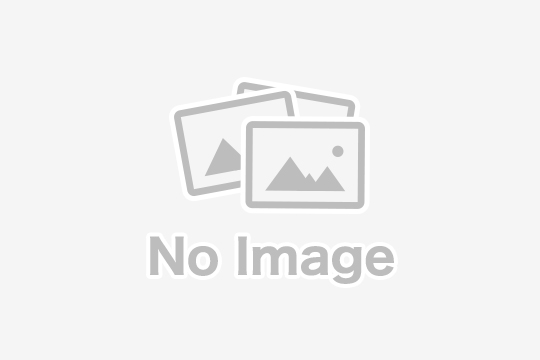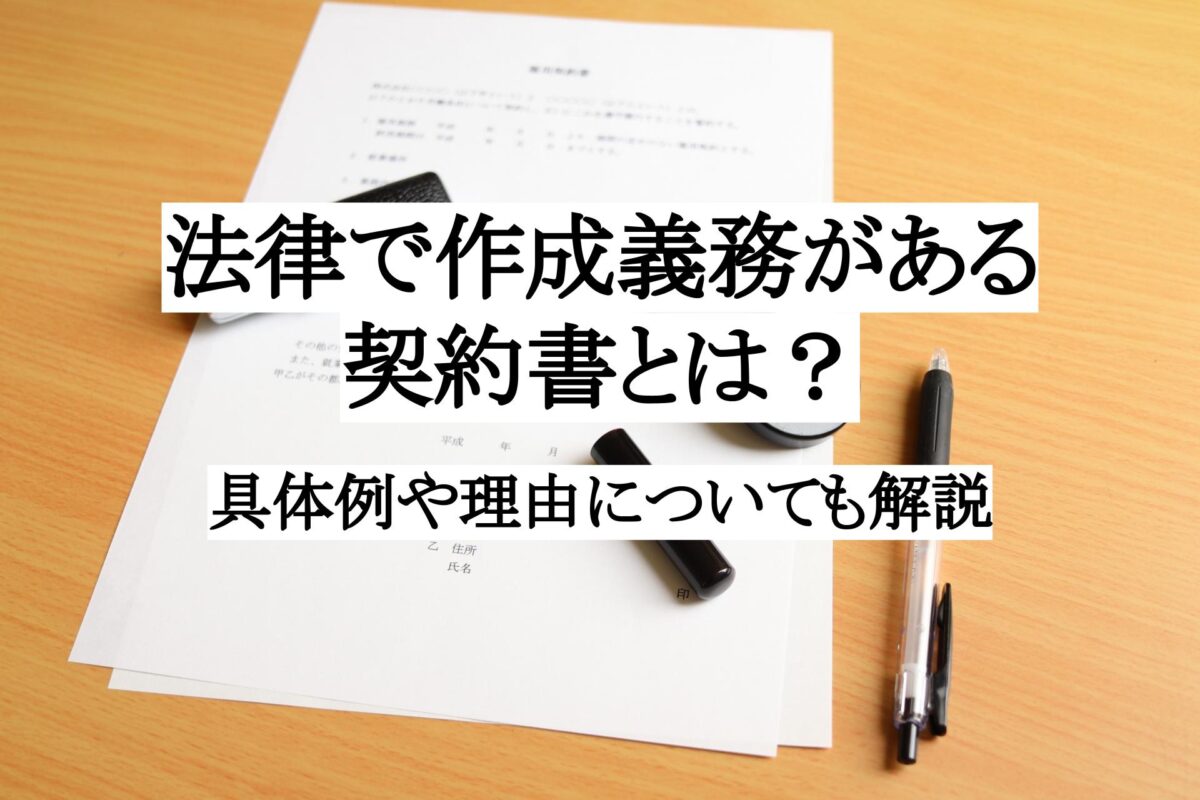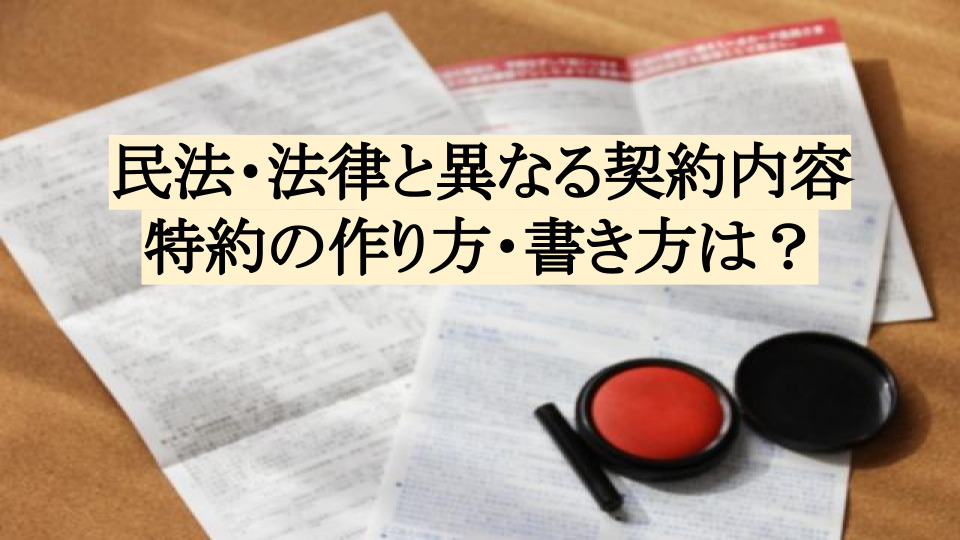
契約の内容は、民法や一部の法律とは異なるものであっても、有効になりますし、違法にはなりません。
こうした、当事者の合意によって変えられる、言いかえれば、当事者の合意が優先される規定のことを、任意規定といいます。
【意味・定義】任意規定とは?
任意規定とは、ある法律の規定に関して、契約当事者による合意がある場合に、その合意のほうが優先される法律の規定をいう。
契約書は、こうした任意規定とは異なる内容(いわゆる特約)を規定する、言い換えれば、任意規定を修正するために作成するものです。
契約書を作成する理由・目的・メリットは様々ありますが、任意規定の修正は、契約書を作成する最も重要な理由・目的・メリットです。
また、契約書の修正は、実務的には高度な専門知識が必要となるため、非常に難しい作業でもあります。
このページでは、こうした法律=任意規定を修正するための契約書作成のポイントについて、解説します。
契約書を作成すると法律とは異なる内容・特約にできる
当事者の関係は契約で自由に決めていい
契約は、法律の内容と違っていても、原則として有効となります。
そもそも、日本では、私人の間の関係は、当事者の合意によって、自由に決めて良いことになっています。
これを「私的自治の原則」、または「契約自由の原則」といいいます。
【意味・定義】契約自由の原則とは?
契約自由の原則とは、契約当事者は、その合意により、契約について自由に決定することができる民法上の原則をいう。
契約自由の原則は、改正民法で次のとおり規定されました(第522条については第2項)。
第521条(契約の締結及び内容の自由)
1 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
第522条(契約の成立と方式)
1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
契約自由の原則は、さらに次の4種類に分類されます。
4つの契約自由の原則
- 締結自由の原則(改正民法第521条第1項)
- 相手方自由の原則(改正民法第521条第1項)
- 内容自由の原則(改正民法第521条第2項)
- 方法自由の原則(改正民法第522条第2項)
この他、契約自由の原則の解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。
こうした原則により、私人同士の関係は、法律よりも当事者の合意・特約のほうが優先されます。
契約には様々な法律が適用される
一方で、契約には、様々な法律が適用されます。
企業間取引であろうと、個人間の取引であろうと、契約には、原則として民法が適用されます。
また、場合によっては、民法以外の法律が適用される場合があります。
契約自由の原則によって、当事者の契約関係は自由に決めてもいいのに、なぜこうした法律があるのでしょうか?
法律は契約の実態に合っていないことが多い
実は、こうした法律は、当事者の合意=契約がない場合(またはその証拠がない場合)に適用されるものです。
当事者の合意やその証拠がない場合に備えたものであるため、こうした法律は、どうしても平均的・最大公約数的なものが多い、という特徴があります。
また、裁判になった際に、裁判官が幅広く解釈できるように、あまり詳細な部分まで個別具体的に規定されていない、という特徴もあります。
つまり、契約がない場合に適用される法律は、実際の契約や取引の実態に合っていないことが多いのです。
ポイント
- 契約自由の原則・私的自治の原則により、当事者の関係は契約で自由に決めていい。
- 原則として、当事者の合意は、法律に優先するため、法律に反した合意も有効となる。
- 契約には様々な法律が適用されるが、必ずしも契約の実態とは適合していない。
契約書は法律の規定を修正するために作成する
契約書で実態に合っていない法律を修正できる
このように、民法をはじめとした契約に関する法律は、必ずしも契約・取引の実態に合っているとは限りません。
このため、仮に契約書がない場合にトラブルになったときは、実態に合っていない法律の規定によって、トラブルについて判決が下されます。
実態に合っていない法律が判断基準となる場合、どう判断されるか、予測がしづらいうえ、必ずしも自社にとって有利な判決が出るとは限りません。
こうした事情があるため、法律の規定を修正するために、契約書を作成する必要があります。
契約書を作成する理由・目的
契約書がない状態では、裁判において、実際の契約や取引の実態に合っていない法律が適用される可能性があるため、詳細で実態に合った契約内容を規定した契約書が必要となるから。
契約を優先する法律=任意規定は修正できる
ただし、どんな法律であっても修正できるかといえば、そうではありません。
確かに、通常、契約に関する規定は、修正できる=当事者の合意(=契約)が優先される任意規定が多いとされます。
契約で修正できるのは、あくまで、この任意規定に限ります。
契約より優先される法律=強行規定は修正できない
逆に、いくら当事者の合意があったとしても、優先される法律の規定のことを、「強行規定」といいます。
【意味・定義】強行規定とは?
強行規定とは、ある法律の規定に関して、契約当事者による合意がある場合であっても、その合意よりも優先される法律の規定をいう。
強行規定に違反した場合、単に契約条項として無効となるだけではなく、場合によっては、刑事罰や行政処分の対象となることがあります。
すでに触れたとおり、契約に関する法律の規定は、一般的には任意規定が多く、強行規定は少ないと言われています。
しかしながら、重要な規定ほど、強行規定であることが多いため、なんでも自由に契約条項を規定していいわけではありません。
なお、任意規定と強行規定につきましては、詳しくは、それぞれ次のページをご覧ください。
ポイント
- 契約書は、実態に合っていない法律を修正するために作成する。
- 任意規定とは、ある法律の規定に関して、契約当事者による合意がある場合に、その合意のほうが優先される法律の規定のこと。
- 強行規定とは、ある法律の規定に関して、契約当事者による合意がある場合であっても、その合意よりも優先される法律の規定のこと。
- 重要な規定ほど、強行規定であることが多い。
- 契約書で修正できるのは、任意規定だけ。
任意規定を修正するには高度な専門知識が必要
任意規定と強行規定は必ずしも明らかではない
そこで重要となるのが、任意規定と強行規定のチェックです。
すでに触れたとおり、強行規定に反した契約内容は、契約条項として無効となるばかりか、場合によっては、刑事罰や行政処分の対象となることもあります。
このため、契約書に規定した契約条項が、強行規定に反していないかどうか、よく確認する必要があります。
ところが、非常に厄介なことに、実は、どの法律の規定が任意規定か強行規定かは、ほとんど法律に明記されていません。
任意規定か強行規定かはわからない
法律の規定が任意規定か強行規定かは、大半の法律には明記されておらず、その法律を読んだだけではわからないことが多い。
過去の判例や専門書を読まないと強行規定か確認できない
契約に適用される法律を知らないと対処できない
この点について、比較的新しい法律や、罰則まで規定されている規定については、強行規定であることは、推測できます。
場合によっては、強行規定であることが明記されていることもあります。
このような場合は、契約にどの法律が適用されるのかを知っていれば、ある程度推測はできます。
逆にいえば、契約にどの法律が適用されるのかを知らなければ、そもそも任意規定や強行規定があるかどうか、確認のしようがありません。
このため、ある程度の法律の知識がなければ、契約書を作成しても、意味がないばかりか、場合によっては刑事罰や行政処分を受ける可能性があります。
強行規定を確認するためには専門知識が必要
それ以上に厄介なのが、任意規定なのか強行規定なのかが、法律に明記されてない場合です。
特に、民法のように古い法律の場合、ある規定が任意規定か強行規定かは、明確に規定されていません。
このため、契約書を作成する際は、契約に適用される法律の規定について、専門書や過去の判例を調べて、強行規定か任意規定かを調べなければなりません。
こうした専門書や判例は、読むだけでのそれなりの専門知識が必要となるうえ、内容を契約書に反映させる必要まであります。
ポイント
- 法律のある規定が任意規定か強行規定かは、法律で明記されていないことが多い。
- 契約にどの法律が適用されるか知らなければ、調べようがない。
- 法律の規定が任意規定か強行規定かは、専門書や過去の判例を確認しないといけない。
違法な契約とならないよう専門家に確認する
このように、契約自由の原則によって、原則としては、契約当事者の合意=契約は、法律に反したものでも、有効となります。
しかしながら、重要な契約条項ほど、強行規定に違反することが多いものです。
こうしたことを意識せずに契約書を作成していると、知らず知らずのうちに、法律違反となる契約書を作成していることもあります。
特に、企業間取引の契約や、企業と消費者のとの契約は、強行規定=様々な規制があります。
こうした契約に関する契約書は、違法とならないように、必ず専門家によるリーガルチェックを受けましょう
ポイント
強行規定に違反して、契約内容が無効となったり、刑事罰や行政処分の対象とならないよう、必ず専門家のリーガルチェックを受ける。
契約書の特約に関するよくある質問
- 契約書は何のために作成するのですか?
- 契約書は法律とは異なる特約を設定するために作成します。
- 法律とは異なる特約を規定しても法律違反にならないのでしょうか?
- 法律とは異なる特約を規定したとしても、その法律が任意規定である場合は、法律違反にはなりません。