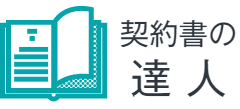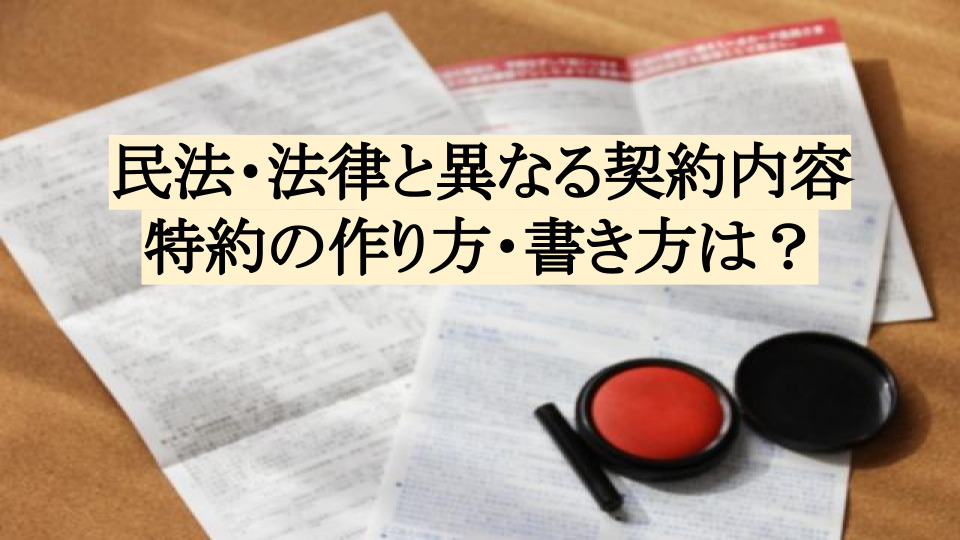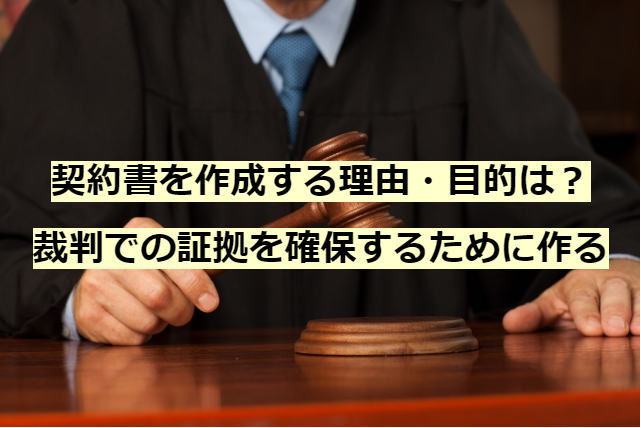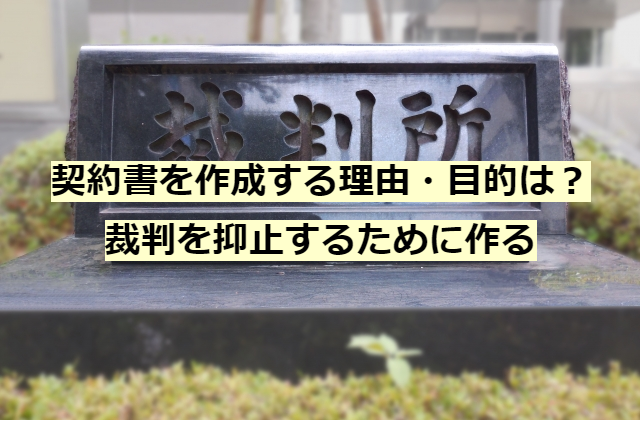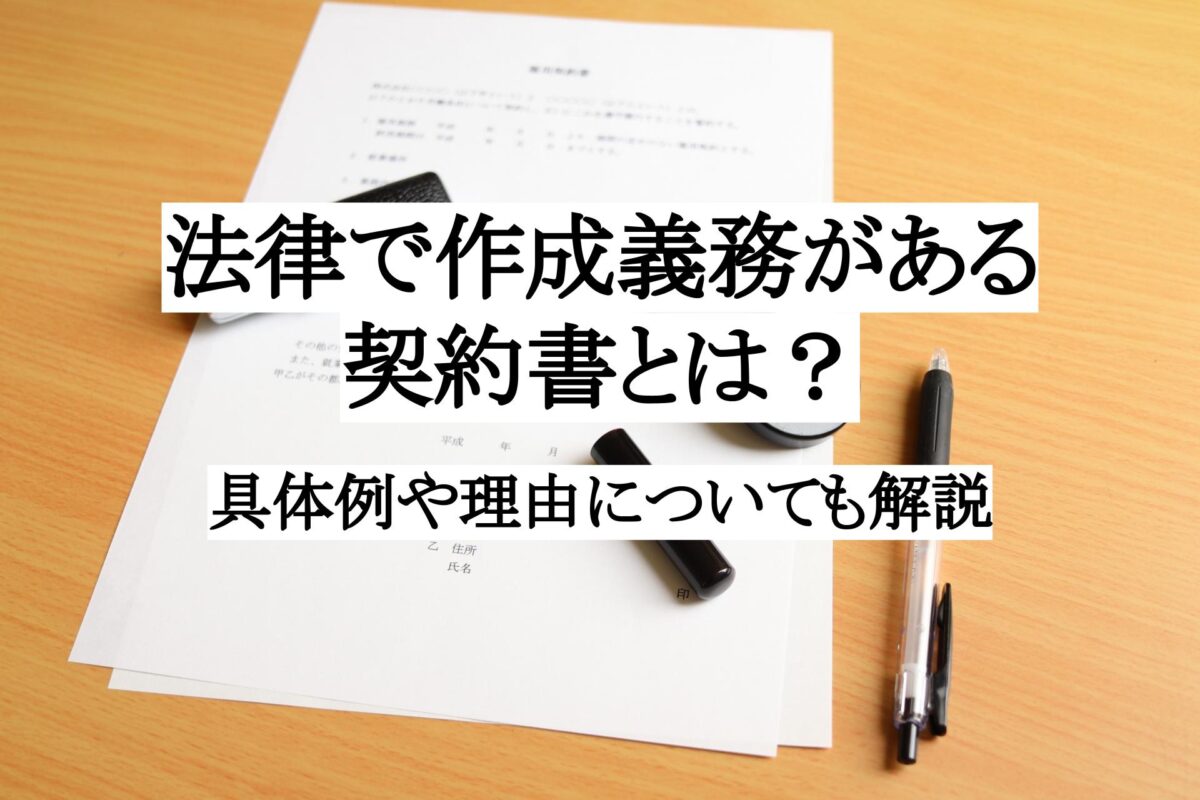企業が契約書を作成する理由として意外と多いのが、「取引先に契約書を提示するように要求されたから」という理由です。
実は、取引先からの契約書の提示の要求には、隠された理由があります。
このページでは、こうした取引先が契約書の作成を要求する理由について解説しています。
企業間取引では、よほど簡単な契約を除いて、契約書を作成するのは必須です。そこで、どちらかの企業が契約書を作成することになります。
通常は、契約交渉条の立場が優位な方の当事者が契約書を作成して提示するものです。
ところが、中には、明確な意図・理由にもとづき、わざと相手方に契約書の提示を要求してくる当事者もいます。
この場合、その意図・理由をよく推測しながら契約書を作成しないと、思わぬリスクにつながる可能性もあります。
取引先から契約書を求められる場合とは?
取引先から契約書を求められることは意外と多い
企業間の取引において、契約書を作成するきっかけとして、意外と多いのが、取引先からの契約書の作成や提示の要求です。
契約書を作成する理由・目的
取引先から契約書の提示を求められたから。
管理人の感覚では、自発的に契約書を作成する場合と、同じ程度の割合のように思われます。
その結果、慌てて契約書を作成することがあります。
イレギュラーな契約では作成を求められることがある
こうした場合、通常は、事前に用意していない、イレギュラーな契約書の作成が求められます。
代表的なものは、新規事業に関する契約書や、業務提携契約の契約書などがあります。
もっとも、本来は事前に用意しておくべき本業の契約書であるにもかかわらず、取引先から要求されて、慌てて作成する場合もあります。
取引先が契約書の作成を求めてくる理由は?
さて、なぜ取引先が契約書の作成や提示を求めるのかといえば、具体的な理由は、次のとおりです。
なぜ取引先が契約書の提示を求めてくるのか?
- 【理由1】取引先が作成したくないため
- 【理由2】御社の本業の契約書であるため
- 【理由3】法律により契約書を作成する義務があるため
- 【理由4】取引先の総務部や法務部の要求があるため
- 【理由5】御社の交渉の出方を見極めるため
- 【理由6】御社が企業として信頼できるかどうかを判断するため
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
【理由1】取引先が作成・自作したくないため
通常は交渉の主導権を握りたい側が契約書を作成する
取引先が契約書の作成を求めてくる1つ目の理由は、単純に取引先が用意したくないから、という理由です。
契約書は、原則としては、どちらが作成してもかまいません。この点につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
企業の姿勢にもよりますが、本来は、契約書は、契約交渉の主導権を握りたい側が作成するものです。
このため、取引先が契約交渉の主導権を握りたい場合は、取引先が契約書を作成するはずです。
自作の契約書は交渉の主導権を握るチャンスと考える
にもかかわらず、御社に契約書の作成を求めてくるというのは、単純に契約書作成の費用負担をしたくない場合が考えられます。
あるいは、取引先に契約書を作成するだけの体制がない可能性もあります。
こうした場合は、むしろ御社が契約交渉の主導権を握るチャンスであるともいえます。
ポイント
単に「自社で作成したくない」「自作の契約書を用意したくない」という理由であれば、むしろ契約交渉の主導権を握るチャンス。
【理由2】御社の本業の契約であるため
本業の契約書はあって当たり前
取引先が契約書の作成を求めてくる2つ目の理由は、その取引が御社の本業の契約だから、という理由です。
御社の本業に関する取引であるにもかかわらず、契約書を作成していない場合は、取引先から契約書の作成を要求されることがあります。
これは、本体はあってはいけない理由です。
というのも、本業の契約書は、その御社にとって最も件数が多い契約の契約書ですので、よほど簡単な取引である場合を除いて、契約書はあって当然なのです。
こうした本業の契約の場合は、取引先が作成するわけにもいきませんので、取引先としては、御社に作成を要求してきます。
契約書の作成を要求されるだけまだマシ
本業の契約書の作成を求められた場合、「面倒くさいなぁ…」と思いがちです。
ですが、契約書の作成を求められたというのは、まだ脈やチャンスがあるのであって、これはむしろマシなほうです。
企業間取引の際、本業の取引の契約なのに「契約書はありません」と言われると、取引先としては、(この会社はマズいんじゃないの?)と疑いを持ちます。
企業によっては、その時点で交渉を打ち切ってもおかしくありません。
つまり、企業間取引なのに「本業の契約書がない」という状態は異常事態といえます。
本業の取引ではいい加減な契約書を提示してはいけない
本業の取引では、インターネットで探した、いい加減な雛形の契約書をダウンロードして提示してはいけません。
インターネットからダウンロードした雛形は、検索のスキルが高い人が調べれば、どのサイトからダウンロードしたのか、たちどころにバレます。
ネットの雛形はすぐにバレる
- インターネットにアップされている雛形は、検索のスキルが高い人がチェックすると、どのサイトからダウンロードしたのか、すぐに分かる。
また、そうでなくても、契約書のリーガルチェックをする過程で、いい加減な契約書であることが判明すると、取引に応じてくれなくなる可能性が高いです。
わざわざ本業の契約書の作成を要求するということは、取引先も、その契約書を本気でリーガルチェックするつもりです。
このため、本業の契約書の作成を求められたときこそ、専門家のアドバイスを受けながらしっかりとした契約書を作成するべきです。
【補足】本業の契約書がない状態で取引をしてはいけない
なお、本業の取引の契約で「契約書はありません」と言ったにもかかわらず、契約書の作成を求めるのではなく、そのまま口頭で取引をしようとする取引先もいます。
こうした取引先とは、間違っても取引をしてはいけません。
繰り返しになりますが、企業間取引では、原則として契約書を作成するものです。
にもかかわらず、契約書を作成せずに取引を進めようとする取引先は、コンプライアンスの意識が低い、トラブルを想定していない、取引の詳細を決めるつもりがない、リスクを棚上げするなど、様々な問題があります。
目先の売上のために、こうした取引先と契約を結んでしまうと、将来、より大きな損失となるリスクがあります。
ポイント
- 本業の契約書はあって当たり前。むしろないほうが「ありえない」。
- 本業の契約書は、作成を要求されるだけまだマシ。本来であれば、契約交渉を打ち切れてもおかしくない。
- 本業の契約書の作成を求められた場合、取引先は本気でチェックするつもりであるため、いい加減な契約書を提示してはいけない。
- 本業の契約書がないのに取引しようとする取引先とは、契約を結んではいけない。
【理由3】法律により契約書の作成義務があるため
契約書の作成義務があれば当然要求される
取引先が契約書の作成を求めてくる3つ目の理由は、法律上、当然に作成しなければならないから、という理由です。
一部の法律では、契約書の作成が義務づけられている場合があります。
企業間取引の代表的な例としては、下請法第3条や、建設業法第19条などがあります。
この他、法律にもとづく作成義務がある契約書につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
こうした法律が適用される取引で、御社に契約書の作成義務がある場合は、本来は、取引先から要求されるまでもなく、契約書を作成しなければなりません。
にもかかわらず、契約書を作成していない、あるいは契約書がない場合は、取引先から契約書の作成を求められることがあります。
契約書作成の要求があればむしろ評価するべき
このように、法律にもとづいて契約書の作成を要求されると、「面倒くさい取引先だな…」と思いがちです。
もちろん、本当に面倒くさい取引であれば、交渉を打ち切ってもいいでしょう。
ただ、そうでない場合は、むしろ、法律にもとづいてフェアに契約交渉をしようとしている点を評価するべきです。
本当に面倒くさい相手というのは、御社が法律上の契約書作成義務を果たしていないことを承知のうえで、黙って口頭での取引に応じるものです。
というのも、こういう取引先は、自社の側が法律で保護されて有利になることを知ったうえで口頭の取引に応じるからです。
ポイント
- 契約書の作成義務があれば、当然、取引先からは契約書の作成を要求される。
- わざわざ法律にもとづく契約書の作成を求めてくる取引先は、「面倒な取引先」ではなく、むしろフェアな交渉相手。
- 法律にもとづく契約書の作成義務がある場合は、黙って口頭での契約に応じる取引先のほうが厄介。
【理由4】取引先の総務部や法務部の要求があるため
素直に「契約書がない」ことを白状するのもあり?
取引先が契約書の作成を求めてくる4つ目の理由は、総務部や法務部(場合によっては経理部や顧問弁護士など)からの要求があるから、という理由です。
取引先の総務部に法務機能がある場合や、法務部がある場合は、そうした部署から契約書の作成を求められる場合があります。
営業の担当者や、契約交渉の担当者、時には社長が、契約書について特に意識せずに取引を進めようとしても、総務部・法務部からは、契約書の要求があります。
こうした場合、素直に「契約書はありません」と言ってしまうのもひとつの対処法です。
ただし、その場合は、取引先が契約書を作成するリスクもあります。
いい加減な契約書では取引先の総務部・法務部に手玉に取られる
また、御社が契約書を作成するのであれば、取引先の総務部・法務部とのやり取りを想定した契約書を作成する必要があります。
この場合、当然ながら、いい加減な契約書では交渉になりません。
それどころか、取引先の総務部・法務部によって、手玉に取られるリスクがあります。
このため、取引先に総務部・法務部があることが判明している場合は、より慎重に、しっかりと作り込んだ契約書を用意して対処する必要があります。
このような場合は、素直に外部の専門家に依頼して契約書を作成するべきです。
ポイント
- 取引先に法務機能・法務部がある場合は、素直に「契約書がない」ことを白状し、取引先に契約書を作成してもらうのもひとつの方法。
- ただし、この場合、取引先から提示される契約書には、当然ながら多くのリスクがある。
- いい加減な契約書を提示した場合、経験豊富な総務部・法務部に手玉に取られるリスクがある。
【理由5】御社の交渉の出方を見極めるため
契約書を作らせれば企業の姿勢はわかる
取引先が契約書の作成を求めてくる5つ目の理由は、取引先が御社の交渉の出方を見極めようとしているから、という理由です。
つまり、御社を試す目的で契約書の作成を要求する、ということです。
これは、社長や法務部の契約交渉の経験が多く、巧みな(場合によっては老獪な)交渉ができる取引先にありがちな対応です。
経験豊富な担当者がいる場合は、御社から出てきた契約書とその間のやり取りを分析するだけで、ある程度の契約実務や対応の能力を見極めることができます。
このため、こうした理由で契約書の作成を求められたと感じた場合は、軽率に対応せずに、専門家とも相談しながら、慎重に対応するべきです。
経験豊富な法務部は契約書の作成の過程で何を見ているのか?
なお、こうした場合、経験豊富な法務部の担当者や、契約実務の専門家は、次のような点を見抜いています。
契約書の作成で見抜かれる部分
- 契約書の質
- ネット上の雛形を使っていないかどうか
- 契約書の作成者の実務能力・経験
- 外部の専門家がついているかどうか
- 修正や契約交渉のやり取りの経験の程度
この他にも、細かな点をいろいろと確認しますが、おおまかには、これらの点をチェックしています。
契約実務の経験が浅い方にとっては、信じられないかもしれませんが、作成された契約書と修正・交渉のやり取りを見るだけで、この程度のことは、ある程度推測できるものです。
このため、取引先に(特に長い経験がある)法務部がある場合は、ヘタに誤魔化して対応しても、たちどころに本性が見抜かれてしまいます。
ポイント
- 経験豊富な法務部の担当者は、契約書のやりとりだけで、企業の姿勢について、様々な分析ができる。
- こうした取引先には、下手な誤魔化しや小手先のテクニックは通用しない。
【理由6】御社が信頼できるかを判断するため
取引先が契約書の作成を求めてくる6つ目の理由は、御社が信頼できる企業であるかを判断しようとするから、という理由です。
この理由は、【理由5】とも関連しますが、契約書の作成を要求し、相手方の出方を見ることにより、信頼できる企業かどうかは、ある程度判断がつきます。
もちろんこれは、取引先や取引先の外部の専門家・顧問等に、契約実務の能力や経験がある者がいる前提の話です。
こうした理由で契約書の作成を要求された場合、まず小手先のテクニックや表面的な対応だけでは、誤魔化しきれるものではありません。
このため、【理由5】と同様に、軽率に対応せずに、専門家とも相談しながら、慎重に対応するべきです。
ポイント
取引先は、作成された契約書、契約書の出し方、交渉のやり取りなどから、御社が信頼できる企業かどうかを見極めている。
【補足1】基本契約・取引基本契約の定義
なお、継続的企業間取引では、いわゆる「取引基本契約書」の作成が要求されることがあります。
【意味・定義】基本契約・取引基本契約とは?
基本契約・取引基本契約とは、継続的取引の基本となる契約であって、個々の個別の契約に共通して適用される契約条項が規定されたものをいう。
基本契約・取引基本契約につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
【補足2】業務委託契約書とは?
また、企業間取引では、いわゆる「業務委託契約書」の作成が要求されることがあります。
【意味・定義】業務委託契約とは?
業務委託契約とは、一般的に、企業間取引の一種で、ある事業者が、他の事業者に対して、自社の業務の一部または全部を委託・受託する契約のことをいう。
業務委託契約につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
取引先による契約書の要求に関するよくある質問
- 契約書は何のために作成するのですか?
- 契約書は、取引先が作成を要求するために作成することがあります。
- なぜ取引先が契約書の作成を求めてくるのですか?
- 取引先が契約書の作成を要求する理由は、主に次のとおりです。
- 【理由1】取引先が作成したくないため
- 【理由2】御社の本業の契約書であるため
- 【理由3】法律により契約書を作成する義務があるため
- 【理由4】取引先の総務部や法務部の要求があるため
- 【理由5】御社の交渉の出方を見極めるため
- 【理由6】御社が企業として信頼できるかどうかを判断するため