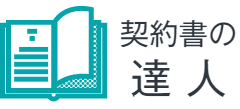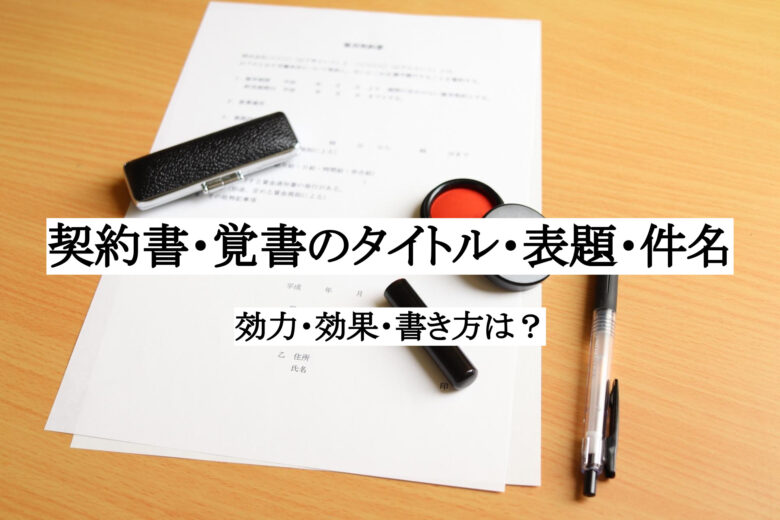後文には、作成した契約書の数や、所持する当事者などの補足情報を記載します。
契約の後文は、書き方によって、法的に非常に重要となる場合があります。
このため、契約書の本文ではないからといって、チェックを怠ってはいけません。
このページでは、こうした後文のポイントについて、解説しています。
後文は契約書の作成数・当事者の所持数を記載する
契約書の作成数・所持者・原本または写しの数を記載する
後文は、契約書の本文の後において、署名欄・作成年月日の直前に書かれている文章のことです。
【意味・定義】後文とは?
契約書の後文(ごぶん・あとぶん)とは、最後の本文の直後に書かれている文章であって、契約書の作成枚数や各契約当事者の所持数などが記載されたものをいう。
後文は、「ごぶん」または「あとぶん」と読み、正確には前者の読み方ですが、後者の読み方もします。
後文には、主に次の内容を規定します。
後文の記載内容
- 契約書の作成数
- 各契約当事者の契約書の所持数
- (場合によっては)各契約当事者が所持する契約書が原本か写しか
- (場合によっては)署名者に契約締結権がある旨の宣誓
後文の具体的な例文・記載例は?
一般的な後文の記載例
一般的な後文は、具体的には、次のように記載します。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】後文
本契約の成立を証するため、本書2通が作成され、甲乙それぞれが1通を保有する。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
原本1通・写し1通とする場合の記載例
原本が1通、写しが1通の場合は、次のように記載します。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】後文
本契約の成立を証するため、本書の原本1通・写し1通が作成され、甲が原本保有し、および乙が写しをを保有する。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
契約書は当事者の数だけ作成する
企業間取引では各契約当事者が1通ずつ原本を保有する
企業間取引の契約書は、通常は、当事者の数だけ作成し、各当事者が1通ずつ保有します。
契約自由の原則により、契約書は、法律にもとづく作成の義務がある場合を除いて、そもそも作成する必要はありません。
このため、契約書の作成数は、特に決まっているわけではありません(法律にもとづく作成義務がある場合を除く。後述)。
ですから、必ずしも当事者の数だけ作成する義務はありませんし、原本を1通だけ作成してもかまいません。
1通だけの原本では偽造・改ざんに対応できない
ただ、原本を1通だけしか作成しないと、その1通を所持している当事者が偽造や改ざんをしてしまう可能性があります。
これ位に対し、原本を所持していない当事者は、その偽造や改ざんに対して、手の打ちようがありません。
また、原本を1通だけしか作成しないと、所持していない当事者が、契約内容を確認できなくなってしまいます。
つまり、所持していない当事者にとっては圧倒的に不利な状況となってしまいます。
このような事情があるため、よほど特殊な事情がない限り、企業間取引では、原本を当事者の数だけ作成し、1通を各当事者が保有するようにします。
覚書や念書も偽造・改ざん・確認できないリスクがある
なお、1通だけ契約書の原本を作成した場合のリスクは、いわゆる「差入れる」書面も同じことがいえます。
具体的には、覚書、念書、確認書のように、タイトルが「契約書」となっていない書類の中には、一方の当事者から、他方の当事者に、1通だけ交付するものがあります。
例えば、念書・確認書など該当します。
こうした書類も、原本を2通作ったり、写しや控えがないと、保有している当事者による偽造・改ざんがある可能性があります。
また、原本を保有していない当事者が、差し入れた書類の内容を確認できないリスクもあります。
ポイント
- 企業間取引では、よほど特殊な場合を除いて、各契約当事者が1通ずつ原本を保有する。
- 原本を1通だけ一方の当事者が保有する場合、他方の当事者は、原本の偽造・改ざんや、確認できないリスクがある。
法律によっては作成や相互の交付の義務がある
なお、契約書の種類によっては、必ず当事者の数だけ作成しなければならないものもあります。
例えば、建設工事請負契約書、建設工事設計受託契約書、建設工事監理受託契約書、液化天然ガスに関する保安業務委託契約書などが該当します。
これらの契約書は、それぞれ作成義務の根拠となる法律において、明確に「相互に交付」することが義務化されています。
この他、下請法にもとづく三条書面のように、事実上、相互に交付することが義務づけられているものもあります。
いずれにせよ、こうした法律にもとづき作成が義務づけられた契約書については、法律にもとづき、慎重に作成する必要があります。
後文には署名者の権限を規定することもある
契約書の署名者には必ずしも契約締結権があるとは限らない
日本の契約書ではあまり見かけませんが、国際取引の契約書では、契約書の署名者が契約締結権を有している旨を明記することがあります。
実は、この契約締結権については、日本の契約書でも、重要となる場合があります。
というのも、法人=株式会社との契約では、代表取締役以外の者が契約書の署名者となる場合、その者が本当に契約の締結権があるかどうか、必ずしも明らかでないことがあるからです。
極端な話ですが、なんら権限がない(=無権代理)にもかかわらず、会社を代表するかのように振る舞うこともあります。
代表取締役以外の署名の場合は契約締結の権限を宣誓させる
もちろん、こうした場合は、次のような対処をするべきです。
署名者に契約締結の権限がないと疑われる場合の対処法
- 実印の押印がある会社から委任状と印鑑登録証明書を提出してもらう。
- 契約書には会社の実印を押印してもらい、印鑑登録証明書とともに提出してもらう。
しかしながら、緊急時などでは、こうした対処ができない場合もあります。
こうした場合は、せめて契約が無効とならない=権限外の行為の表見代理(民法第110条)となるように、署名者に契約締結の権限がある旨を宣誓してもらいます。
署名者の権限の記載の書き方・しかたは?
具体的な署名者の契約締結の権限の宣誓は、次のとおりです。
【契約条項の書き方・記載例・具体例】後文
本契約の成立を証するため、本書2通が作成され、甲乙それぞれが1通を保有する。なお、本書に署名する者は、本契約のそれぞれの当事者から正式に契約を締結する権限を授権したことを保証し、宣誓する。
(※便宜上、表現は簡略化しています)
なお、契約の署名者の契約締結の権限につきましては、詳しくは、「契約の当事者・署名者による署名・サインのしかた」をご覧ください。
ポイント
- 契約書の署名者には、必ずしも契約締結権があるとは限らない。
- 代表取締役以外の者による署名の場合は、後文で、署名者に契約締結の権限について宣誓させる。