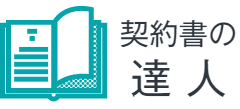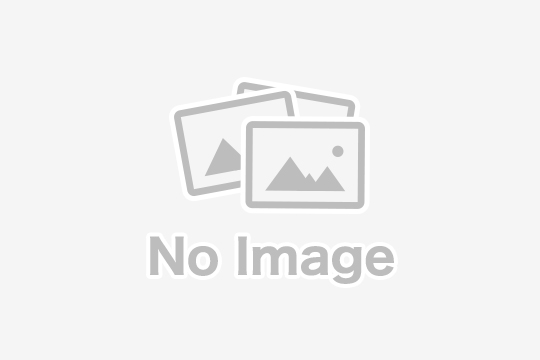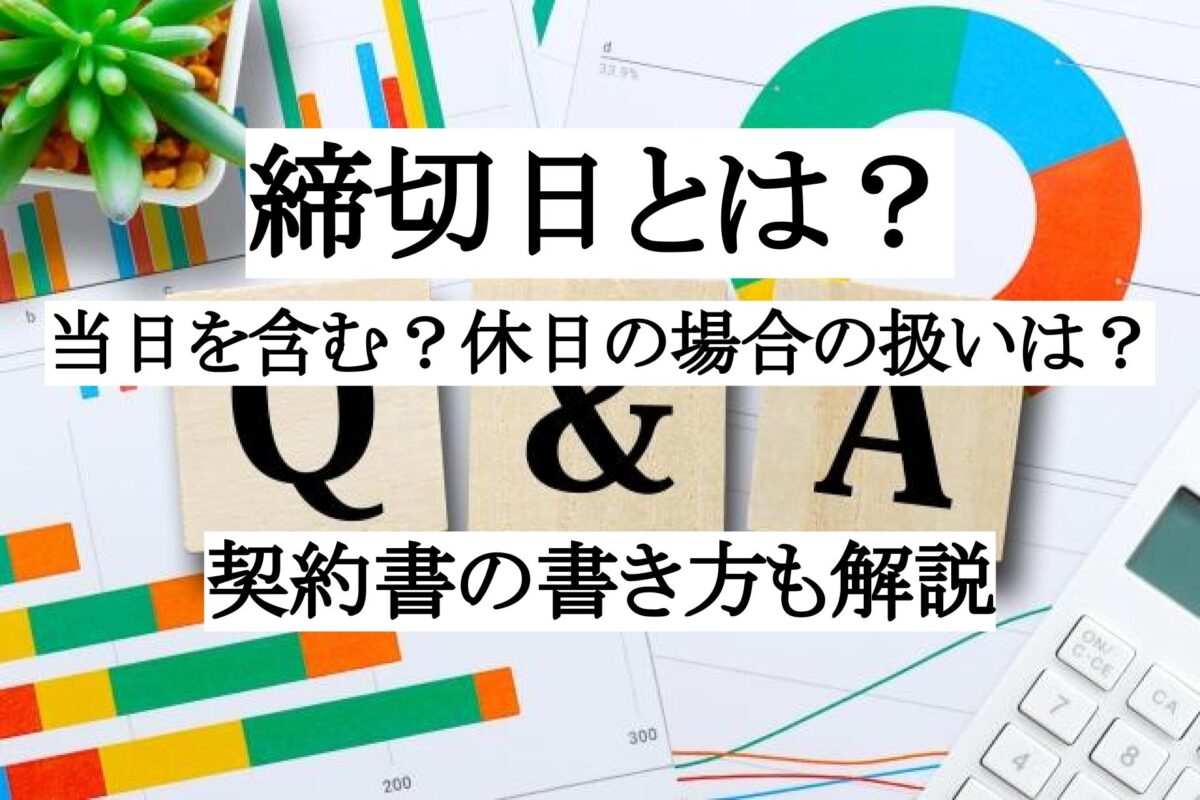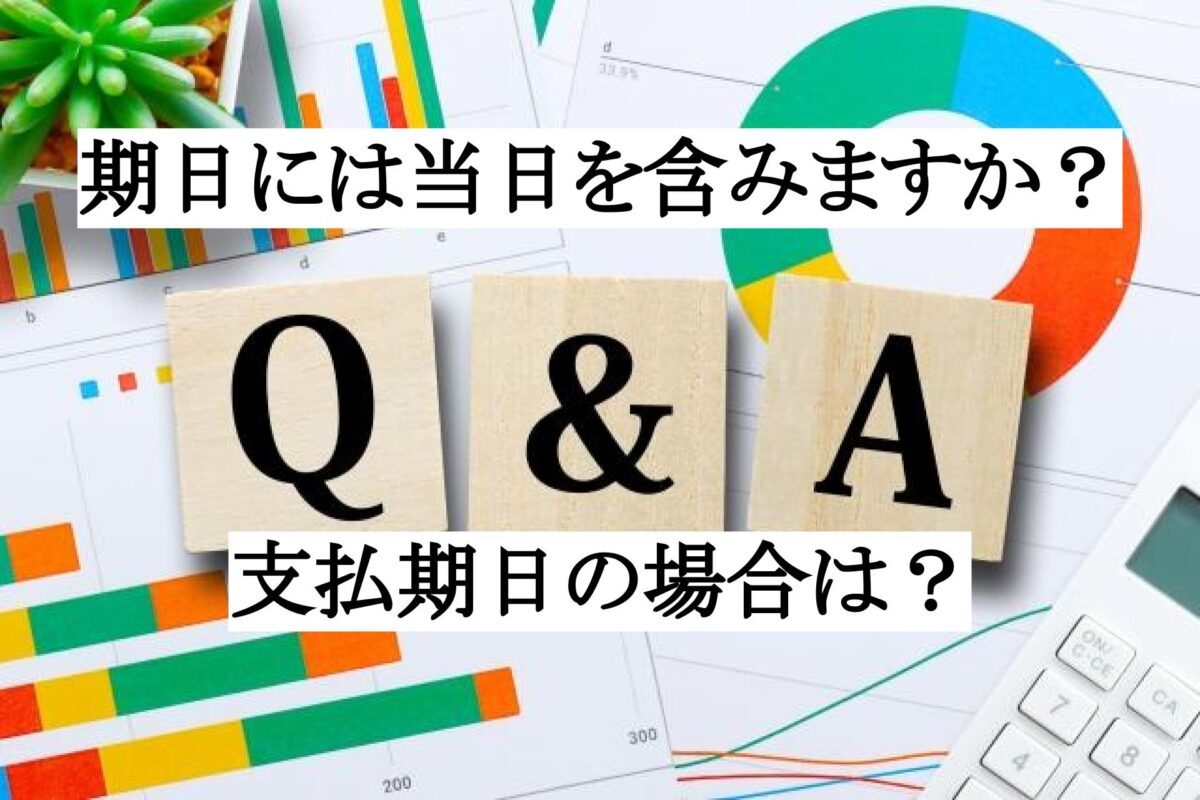- 注文書・発注書や注文請書・受注書は契約書なのでしょうか?また、これらに違いは何でしょうか?
- 注文書・発注書や、注文請書・受注書は、契約書の一種です。
これらの違いは、注文書・発注書や、注文請書・受注書は、一方の当事者から、相手方に対し、一方的に交付されるものであるのに対し、契約書は、一般的には相互に取交すものである、という点です。
このページでは、弊所によく寄せられるご質問である、注文書・発注書や注文請書・受注書と契約書の法的拘束力、法的効果や、それぞれの違いについて解説しています。
注文書・注文請書はたかが1枚でも立派な契約書
注文書・注文請書は契約書と同じ法的拘束力がある
結論をいいますと、注文書・発注書や注文請書・受注書は、一種の契約書であり、法的拘束力があります。
法的な効果としては、それぞれ、次のとおりです。
注文書・発注書、注文請書・受注書、契約書の法的効果
- 注文書・発注書:受注者への送付・交付により、注文者・発注者による契約の申込みの証拠となる。注文書・発注書の交付・送付だけでは、原則として契約は成立しない。
- 注文請書・受注書:注文者・発注者への送付・交付により、契約の申込みへの受注者による承諾の証拠となる。注文請書・受注書の交付・送付により、契約が成立する。
- 契約書:通常は、当事者の数(一般的には2部)が作成され、相互に1部づつ取交すことにより契約の成立の証拠となる。なお、契約書の取交しだけでは契約が成立しないようにすることも可能。
注文書・注文請書と契約書は法的効果に違いがある
注文書・発注書(以下、総称して「注文書」とします)、注文請書・受注書(以下、総称して「注文請書」とします)は、契約当事者の意思表示をするための書類です。
この点は、契約書と同じ法的効果です。
ただ、注文書・注文請書は、一方の当事者による相手方に対する一方的な意思表示の場合に使われるものです。
これに対し、契約書は、双方の当事者による、相手方に対する相互の意思表示の場合に使われるものです。
注文書・注文請書と契約書の違い
- 注文書は、注文者や発注者が、受注者に対して、一方的に意思表示(契約の申込みだけ)をするための書面。
- 注文請書は、受注者が、注文者や発注者に対して、一方的に意思表示(契約の承諾だけ)をするための書面。
- 契約書は、注文者・発注者と受注者が、相手方に対して、相互に意思表示(契約の申込みと承諾)をするための書面。
- 注文書の交付・送付だけでは原則として契約は成立しないが、注文請書の送付・交付と契約書の取交しは、契約が成立する。
- 注文書には原則として収入印紙を貼る必要がないが、契約書・注文請書には収入印紙を貼る必要がある(後述)。
なお、契約書の意味・ポイント・解説につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
注文書・注文請書は基本契約書とセットで使う
1枚だけの注文書・注文請書には契約内容が書ききれない
注文書・注文請書は、本来は、基本契約書とセットで使われるものです。
通常、注文書・注文請書は、せいぜいA4の紙1枚程度のものです。
これでは、どんなに簡単な企業間取引であっても、すべての契約内容を書けません。
このため、注文書・注文請書に書ききれない契約条項は、通常は基本契約書に規定します。
このため、しっかりとした基本契約さえ締結していれば、注文書・注文請書が1枚程度であっても、特に問題とはなりません。
注文請書がなくても契約は自動的に成立することもある
契約は申込みと承諾があって成立する
中小企業にありがちですが、取引の際に、注文書だけを使って、注文請書を使わないことがあります。
実は、これは非常に問題が多い取引の方法です。
契約は、「申込み」と「承諾」があって成立するものです。
民法第522条(契約の成立と方式)
1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
売買の取引なら、あるものを「売ります」という申込みと「買います」という承諾がなければ、成立しません。
注文書や注文請書は、この申込みや承諾があったことを証明する書類です。
にもかかわらず、注文書だけ使って注文請書を使わないということは、注文を承諾したのかどうかわからない状態で取引が進んでしまう、ということです。
商法第509条により自動的に契約が成立する
ちなみに、企業間の継続的取引では、注文書による申込みがあったにもかかわらず、受注者からその申込みに対する諾否の通知がない場合は、契約が自動的に成立したものとみなされます。
これは、商法第509条によるものです。
商法第509条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
1 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
引用元:商法 | e-Gov法令検索
このため、企業間の継続的取引の受注者としては、注文書が届いているにもかかわらず、うっかり放置してしまうと、契約が自動的に成立してしまう、というリスクがあります。
なお、こうした場合に、自動的に契約が成立しないように特約を設定することも可能です。
ポイント
- 一般的な企業間取引では、注文書・注文請書は、単体で使うのではなく、基本契約書とセットで使う。
- 受注者が注文請書を返送しなくても、商法第509条により、契約が成立する。
- 受注者としては、注文請書の返送がない場合に契約を不成立としたい場合は、必ず契約で特約を規定する。
【補足1】実は注文書には収入印紙を貼る必要がない
注文書は原則として課税文書に該当しない
すでに触れたとおり、注文書は、単に契約の申込みの書面でしかありません。
このため、実は、注文書は課税文書ではなく、原則として収入印紙を貼る必要がありません。
[平成29年4月1日現在法令等]
契約とは、申込みとその申込みに対する承諾によって成立するものですから、契約の申込み事実を証明する目的で作成される単なる申込書、注文書、依頼書等(以下「申込書等」という。)は、通常、課税対象にはなりません。(以下省略)
完全自動成立の注文書は課税文書
もっとも、注文書を送付しただけで自動的に契約が成立する手続きとした場合、その注文書は、課税文書となります。
[平成29年4月1日現在法令等]
(途中省略)次に掲げるものは、一般的に契約書に該当するものとして取り扱われています。
(1)契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。
(2)(以下省略)
このため、注文書の送付により完全に自動的に契約が成立する手続きでは、印紙税の節約のメリットはありません。
ポイント
- 原則として、注文書・発注書に収入印紙を貼る必要はない。
- 例外として、契約が完全に自動で成立する注文書については、収入印紙を貼る必要がある。
【補足2】注文書・発注書の関連記事
注文書・発注書そのものの定義・解説につきましては、詳しくは、以下のページをご覧ください。