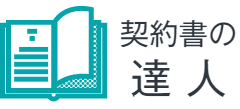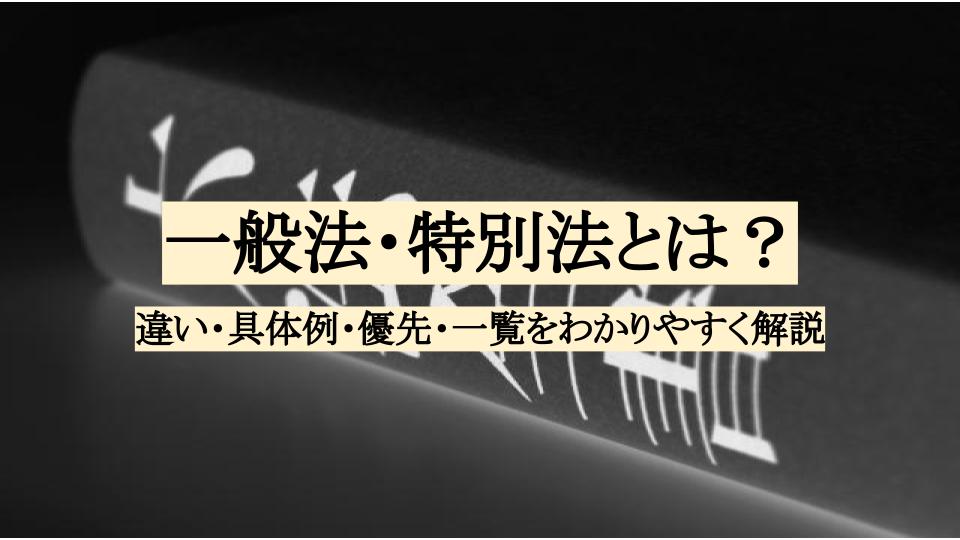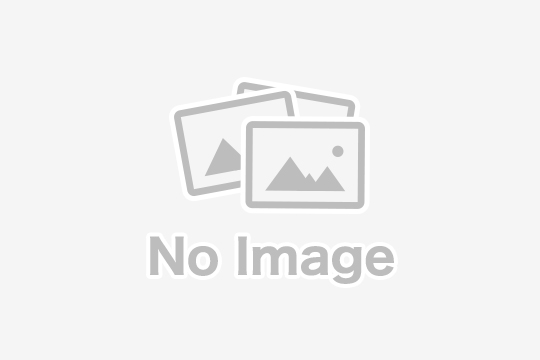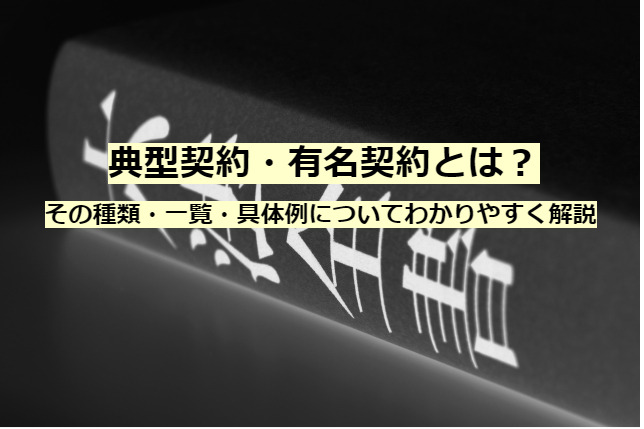契約書とは、契約内容を記載した書面のことです。
また、契約とは、2者以上の契約当事者による、債権・権利と債務・義務を発生させる合意のことで、簡単にいえば、なんらかの権利・義務を発生させる約束のことです。
一般的な企業間取引の契約では、様々な理由により、契約書を作成するべきとされていて、口約束はするべきではありません。
このページでは、こうした契約書・契約の基本的なポイントについて、解説します。
契約書とは?
【意味・定義】契約書とは?
契約書=契約内容を記載した書面のこと
契約書とは、契約内容を記載した書面のことです。
【意味・定義】契約書とは?
契約書とは、契約内容を記載した書面をいう。
タイトルに「契約書」がなくても法的拘束力がある
また、契約書は、タイトルが「◯◯契約書」となっていなくても、原則として、法的拘束力を有します。
よくありがちな勘違いですが、「念書・覚書・確認書・仮契約書は正式な契約書ではないので法的拘束力がない」というのは間違いです。
念書・覚書・確認書・仮契約書も、法的拘束力がある契約書の一種です。
法律での契約の定義―印紙税法における契約書の定義は?
ちなみに、印紙税法における契約書の定義は、次のとおりです。
…契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含みます。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」といいます。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます。
引用元: No.7117 契約書の意義|国税庁
ポイント
- 契約書とは、契約内容を記載した書面のこと。
- 念書・覚書・確認書・仮契約書も、法的拘束力がある契約書の一種。
契約とは?
契約=権利・義務を発生させる約束
一般的に、契約とは、2者以上の契約当事者による、債権と債務を発生させる合意のことをいいます。
【意味・定義】契約とは?
契約とは、2者以上の契約当事者による2つ以上の対立する意思表示の合意であって、債権(場合によっては物権・準物権・身分に関するものも含む)および債務を発生させることを目的としたものをいう。
つまり、簡単にわかりやすく表現すれば、契約とは、2者の契約当事者による、権利と義務を発生させる約束のことです。
一般的な企業間取引における当事者間の合意は、ほとんどが契約に該当します。
契約も、契約書と同じように、「合意」や「確認」など契約とは別の用語や表現を使われていたとしても、法的拘束力が発生することがあります。
ポイント
- 契約とは、2者以上の契約当事者による、債権と債務を発生させる合意のこと。
契約書は取交すもの・契約は締結するもの
「契約書を締結する」「契約を取交す」は間違い
よくありがちですが、「契約書を締結する」「契約を取交す」は、厳密には間違った表現です。
正確には、「契約を締結する」または「契約書を取交す」という表現となります。
契約書は書面ですので、「取交す」ものであり、締結するものではありません。
また、契約は合意・約束ですので、「締結する」ものであって、取交すものではありません。
このため、「契約書を締結する」「契約を取交す」という表現は誤りです。
契約書・契約でありがちな間違い
- 【誤った表現】「契約書を締結する」「契約を取交す」
- 【正しい表現】「契約を締結する」「契約書を取交す」
「契約書を締結する」「契約を取交す」のリスクは?
細かな話ですが、「契約書を締結する」「契約を取交す」といった表現のミスをしてしまうと、「契約実務に慣れていない」というメッセージを発してしまうことになります。
企業間の契約交渉では、お互の法務部や担当者にどの程度の契約実務の能力があるのかが、重要となる局面があります。
特に、自社の契約実務の能力が不十分な場合、相手方にバレないように交渉を進める必要があります。
そうした状況で、「契約書を締結する」「契約を取交す」という些細な表現のミスをしてしまうと、相手方に自社の契約実務の能力の低さ・不十分さがバレるリスクがあります。
このため、「契約書を締結する」「契約を取交す」といった誤った表現ではなく、「契約書を取交す」「契約を締結する」と正確な表現を使うよう、心がけるべきです。
ポイント
- 「契約書を締結する」「契約を取交す」は、間違った表現。
- 正しくは、「契約を締結する」または「契約書を取交す」。
- 「契約書を締結する」「契約を取交す」という間違った表現をすると、契約交渉の相手方に対し、自社の契約実務の能力が不十分であることが露見する。
原則として契約は契約書がなくても成立する
契約は口頭=口約束でも成立する
契約は、原則として、口頭でも成立し、契約書の作成を必要としません。
これは、いわゆる「契約自由の原則」のうち、「方法自由の原則」によるものです。
【意味・定義】方法自由の原則とは?
方法自由の原則とは、契約締結の方法を自由に決定できる原則をいう。
例外として、契約の成立のために契約書の作成が必要なものは、後述の「要式契約」の場合に限ります。
例えば、連帯保証契約は、書面でしなければ効果は生じません(民法第446条第2項)。
法律上作成が義務づけられる契約書もある
また、契約自体の成立には影響はありませんが、法律の規制によって、契約書の作成を義務づけられた契約もあります。
具体的には、次のものが該当します。
法律により作成義務がある契約書
- 一部の業務委託契約書(三条書面)等(下請法)
- 建設工事請負契約書(建設業法)
- 家内労働手帳(家内労働法)
- 建設工事設計受託契約書・建設工事監理受託契約書(建築士法)
- 雇用契約書・労働契約書・労働条件通知書(労働基準法・労働契約法)
- 労働者派遣契約書(労働者派遣業法)
- 一部の消費者・事業者向けの契約書(特定商取引法・割賦販売法)
- 金融商品取引契約書(金融商品取引法等)
- 投資顧問契約書(同上)
- 探偵業務委託契約書(探偵業法)
- 住宅宿泊管理受託契約書(住宅宿泊事業法)
- 保険契約書・保険約款(保険業法)
- 信託契約書(信託業法)
- マンション管理委託契約書(マンション管理適正化法)
- 不動産特定共同事業契約書不動産特定共同事業法)
- ゴルフ場会員契約書(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律)
- 商品投資顧問契約書(商品投資に係る事業の規制に関する法律)
- 定期建物賃貸借契約書(借地借家法)
- 特定商品等預託等取引契約書(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)
- 貸金業者による金銭消費貸借契約書(貸金業法)
- 一部のフランチャイズ契約書(中小小売商業振興法)
- 積立式宅地建物販売契約書(積立式宅地建物販売業法)
- 警備契約書(警備業法)
- 熱供給契約書・約款(熱供給事業法)
- 電力小売供給契約書・約款(電気事業法)
- ガス小売供給契約書・約款(ガス事業法)
- 産業廃棄物処理契約書(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
- 不動産の売買・交換・賃貸に関する契約書(宅建業法)
- 企画旅行契約書・手配旅行契約書等(旅行業法)
- 福祉サービス利用契約書(社会福祉法)
- 商品取引契約書(商品先物取引法)
これらの法律上作成が義務づけられている契約書につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
ポイント
- 契約は、原則として口頭=口約束でも成立する。
- 例外として、「要式契約」の場合は、契約書を作成しないと契約が成立しない。
- 「要式契約」以外でも、法律上、契約書(=書面)の作成が義務づけられている契約がある。
ビジネスの世界では契約書が必要
契約書を作成する理由・目的は?
契約は口頭でも成立するとはいえ、それはあくまで民法上、つまり学術的な次元の話です。
ビジネスの世界では、次のような理由・目的によって契約書が必要となります。
特に、企業間取引では、契約書は事実上必須であるといえます。
逆に、契約書がなければ、契約の存在そのものを含めて、明確にはなりません。
なお、契約書を作成する理由につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
https://xn--wtsq13a09q.jp/category/reason-for-creating-contract/
契約書を作成しないデメリット・リスクは?
ビジネスの世界では、契約書を作成しないことは、多くのデメリット・リスクとなります。
契約書を作成しないデメリット・リスク
- 契約内容が客観的に明らかにならない。
- 訴訟のリスクが高くなる。
- ビジネスの実態に合わない法律に従わなければならない。
- 法律違反をしていないことを立証できない。
- 企業として信頼されない。
このように、契約書がないことのデメリットはいくつもあります。
これに対して、契約書がないことのメリットは、せいぜい、契約書を用意する一時的なコストがからない程度のものです。
契約書がないメリット
契約書の作成・取交しに関する、一時的な金銭的・時間的・手続的な費用が発生しない。
このため、事業上の契約、特に企業間取引の契約では、契約書の作成は必須です。
ポイント
企業間取引では、事実上、契約書を作成することが必須となる。
様々な契約の種類・分類法
契約は、次のとおり、その性質に応じて、様々な種類に分類することができます。
典型契約・非典型契約・混合契約
典型契約・非典型契約・混合契約
有償契約・無償契約
有償契約・無償契約
- 有償契約:契約当事者の双方または一方に、経済的な費用負担・損失がある契約。
- 無償契約:契約当事者の双方に、経済的な費用負担・損失がない契約。
双務契約・片務契約
双務契約・片務契約
- 双務契約:契約当事者の双方が、債務を負担する契約。
- 片務契約:契約当事者の一方だけが、債務を負担する契約。
諾成契約・要物契約
諾成契約・要物契約
- 諾成契約:当事者の合意だけで成立する契約。
- 要物契約:当事者の合意に加えて、その成立に一定の給付が必要な契約。
要式契約・不要式契約
要式契約・不要式契約
- 要式契約:契約の成立のために、一定の方式(ほとんどの場合は契約書の作成)が必要な契約。
- 不要式契約:契約の成立のために、なんらの方式も必要がない契約。
一回的契約・継続的契約
一回的契約・継続的契約
- 一回的契約:1回の債務の履行を目的とした契約。売買契約・請負契約など。いわゆる「スポット」の契約。
- 継続的契約:継続的な債務の履行を目的とした契約。賃貸借契約、雇用契約、委任契約など。
- 回帰的契約:一回的契約を継続的に履行する契約。一定量の電気・ガス・原材料の供給契約やウォーターサーバーの契約など。
基本契約・個別契約
基本契約・個別契約
- 基本契約:個別契約に適用される共通の契約内容を規定した契約。総括契約ともいう。
- 個別契約:個々の取引の契約内容について規定した契約。
本契約・予約
本契約・予約
- 本契約:予約にもとづいて成立した契約。
- 予約:将来、一定の内容の契約を締結することを合意する契約。
有因契約・無因契約
有因契約・無因契約
- 有因契約:契約の成立になんらかの前提となる原因が必要な契約。
- 無因契約:契約の成立になんらの前提となる原因を必要としない契約。
契約書・契約に関連するおすすめ記事
契約書の作成方法・作り方おすすめ関連記事9選
契約書の作成や作成方法・作り方につきましては、以下の記事をご覧ください。
契約書の書式・書き方・ルールのおすすめ関連記事
契約書の書式・書き方・ルールについては、以下の記事をご覧ください。
契約書・契約に関するよくある質問
- 契約書・契約とは何ですか?
- 契約書・契約とは、以下のとおりです。
- 契約書とは、契約内容を記載した書面のこと。
- 契約とは、2者以上の契約当事者による2つ以上の対立する意思表示の合意であって、債権(場合によっては物権・準物権・身分に関するものも含む)および債務を発生させることを目的としたもの。
- なぜ契約書を作成する必要があるのでしょうか?
- 契約書を作成する理由・目的は以下のとおりです。