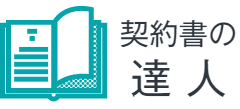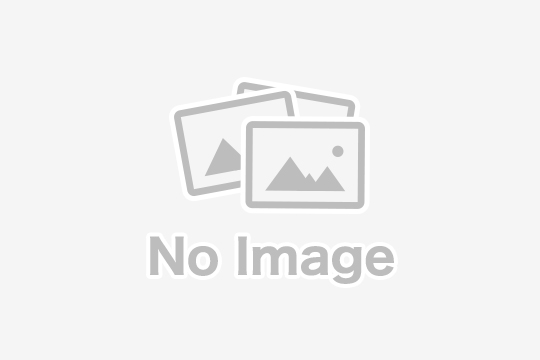契約交渉では、契約自由の原則のうちの、締結自由の原則により、契約締結の拒否の自由も認められます。
このため、実際に契約が成立した後に比べると、法律による規制は、かなりゆるいといえます。
ただし、一部の法律によっては、厳しい規制がある場合もあります。
実際の契約交渉では、こうした規制などを遵守しながら、契約交渉を進めていくことになります。
このページは、こうした契約交渉の一連の過程・ポイントについて、解説します。
契約交渉は原則として自由にできる
締結自由の原則=締結拒否自由の原則
契約交渉の段階では、まだ当事者同士を拘束する契約は成立していませんので、契約に縛られることはありません。
また、契約自由の原則のうちの、締結自由の原則により、契約を締結するかどうかも、自由に決められます。
【意味・定義】締結自由の原則とは?
締結自由の原則とは、契約自体を締結する(結ぶ)か締結しないかを自由に決定できる原則をいう。
つまり、いわば「契約締結拒否」の自由もあるともいえます。
このため、契約交渉段階では、比較的自由に振る舞うことができます。
契約交渉段階でも最低限の法規制はある
ただし、これは、あくまで契約=当事者の合意による拘束がないだけであり、最低限の法律による規制はあります。
特に、すべての契約交渉では、民法上の信義誠実の原則が適用され、最低限の説明責任・情報提供義務が発生します。
また、特定の事業の契約では、後述のとおり、法律による厳しい規制があり、「自由」とは程遠いのが実態です。
実際の契約交渉では、こうした法規制にも注意しながら進める必要があります。
契約交渉の目的は守られる契約
なお、契約交渉の結果、最終的に目指す契約は、「有利な契約」ではなく、「守られる契約」です。
確かに、契約書にサインがあれば、たとえ厳しい条件を突きつけていたとしても、違法なものでもない限り、たいていの契約条件は有効となります。
しかし、相手方にとって、あまりにも厳しい条件での契約を締結してしまうと、結果として、相手方が契約の履行もできないまま債務不履行に陥ってしまうことになります。
交渉によって有利な条件を勝ち取ることも重要なことですが、その有利な条件も、結局のところは、守ってもらうことが前提です。
つまり、「守られる契約」のギリギリの範囲内で、自社にとって「有利な契約」を勝ち取ることが、契約交渉の最終目標ということです。
ポイント
- 契約交渉は、原則として自由。
- 業種によっては、契約交渉段階から、自由とはほど遠い規制がある。
- 契約は守られてこそ意味がある。守られない契約は締結する意味がない。
契約交渉の一連の行程のポイントは?
【ポイント1】広告・勧誘の段階から法規制がある
契約交渉に入る際には、交渉当事者のどちらからか、アプローチがあるものです。
この際、商品・サービス等を提供する事業者の側による広告・勧誘がある場合、一定の法規制がかかります。
特に、消費者に対する広告・勧誘や、一定の分野の契約に関する広告・勧誘については、非常に厳しい規制があります。
こうした、広告・勧誘等の規制については、詳しくは、次のページをご覧ください。
【ポイント2】秘密保持契約を締結する
特に企業間取引の契約交渉では、契約交渉段階で、非常に重要な企業秘密を開示する場合があります。
現在の法律では、こうした契約交渉段階では、原則として、当然には、交渉当事者に秘密保持義務が課されません。
このため、遅くとも、漏えい・開示されると困る情報を開示する直前までには、秘密保持契約を締結する必要があります。
このほか、契約交渉段階における秘密保持契約につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
また、秘密保持契約そのものにつきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
【ポイント3】契約交渉中は信義誠実の原則を守る
契約交渉にあたっては、当然のことながら、誠実におこなうことが重要です。
まだ契約が成立していない、契約交渉段階であっても、過去の判例では、民法上の信義誠実の原則を適用しています。
具体的には、契約交渉の当事者には、一定の説明責任や情報提供義務が課されます。
また、こうした説明責任や情報提供義務の中には、法律にもとづいたものもあります。
【ポイント4】契約交渉は不当に破棄しない
すでに述べたとおり、契約交渉では、契約自由の原則のうちの、締結自由の原則があります。
この締結自由の原則により、契約を締結するのも、締結しないのも自由です。
このため、契約締結の拒否の自由も認められます。
ただし、どんな状況であっても、まったく自由に契約締結を拒否できるかというと、必ずしもそうではありません。
契約交渉段階で、交渉を不当に破棄した場合、状況によっては、信義誠実の原則に違反し、損害賠償責任を負うことになります。
この他、契約交渉段階での不当破棄の責任につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
【ポイント5】予備的合意書(Loi・Mou)へのサインは慎重に
特に国際取引の契約交渉で、非常に長期間に渡って契約交渉をする場合、途中で、予備的合意書=「Letter of Intent」(Loi)・「Memorandum of Understandings」(Mou)へのサインを求められます。
この書面は、「予備的」とはいえ、「合意書」の一種ですので、場合によっては、法的拘束力が認められる可能性があります。
これは、国際取引だけではなんく、国内取引における議事録へのサインでも注意するべきものです。
このため、予備的合意書や議事録へのサインの際は、法的拘束力認めるられるリスクを考慮し、場合によっては、法的拘束力の有無を明記するべきです。
このほか、予備的合意書につきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
【ポイント6】最終的な契約書にはすべての合意を盛り込む
最終的に契約交渉がまとまった場合、または、契約交渉と平行して、契約書を作成することになります。
契約書には、契約交渉で合意した内容を、漏れなくすべて規定するようにします。
特に、契約交渉の結果、勝ち取った有利な条件については、契約書に規定しないと、契約条件としては失効する可能性があります。
これは、完全合意条項・完全合意事項が規定された契約書では、特に注意が必要です。
ポイント
- 業種・契約の種類・勧誘方法によっては、広告・勧誘の段階から法規制がある。
- 特に企業間取引の契約交渉では、契約交渉に入る前に、必ず秘密保持契約を締結する。
- 契約交渉中は信義誠実の原則を守り、必ず説明責任・情報提供義務を果たす。
- 契約交渉は不当に破棄しない。不当に破棄した場合、損害賠償責任が発生する。
- 予備的合意書(Loi・Mou)は法的拘束力がは発生する可能性があるため、サインする際は慎重に対処する。
- 最終的な契約書にはすべての合意を盛り込む。契約書に規定されない合意は、失効する。