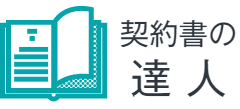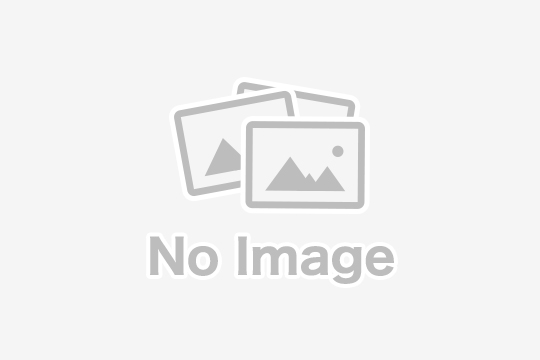一般的に、業務委託契約は、企業間の業務委託についての規定した契約です。
ただ、実は、法律的には「業務委託契約」という名前の契約ありません。
このため、実際の業務委託契約は、内容によって様々で、個々の案件ごとによく確認しなければならない契約です。
このページでは、こうした業務委託契約のポイントについて、わかりやすく解説します。
業務委託契約は定義がない
業務委託契約は民法・判例・学説とも定義がない
「業務委託契約」や「業務委託」という言葉は、民法では出てきません。
判例や学説としても、特に統一的な定義はありません。
このように、業務委託契約は、そもそも定義がない契約です。
一般的なビジネス用語としては、「企業間で締結される業務の委託・受託の契約」という程度の意味でしょう。
【意味・定義】業務委託契約とは?
業務委託契約とは、企業間取引の一種で、ある事業者が、相手方の事業者に対して、自社の業務の一部または全部を委託し、相手方がこれを受託する契約をいう。
ただ、これも法的な定義にはなっていません。
通常は民法上の請負契約か(準)委任契約のいずれか
一般的な業務委託契約の内容は、民法上の請負契約か、委任契約(準委任契約)のいずれかに該当します。
【意味・定義】請負契約とは?
請負契約とは、請負人(受託者)が仕事の完成を約束し、注文者(委託者)が、その仕事の対価として報酬を支払うことを約束する契約。
【意味・定義】委任契約とは?
委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約。
【意味・定義】準委任契約とは?
準委任契約とは、委任者が、受任者に対し、法律行為でない事務をすることを委託し、受任者がこれ受託する契約。
なお、請負契約と(準)委任契約の違いにつきましては、詳しくは、次のページをご覧ください。
業務委託契約は大きく分けて7パターン
業務委託契約は、請負契約や(準)委任契約を含めると、次の契約に該当する可能性があります。
典型的な業務委託契約の7つのパターン
- 請負契約である業務委託契約
- 委任契約・準委任契約である業務委託契約
- 寄託契約である業務委託契約
- 組合契約である業務委託契約
- 実は雇用契約・労働契約である業務委託契約
- 実は労働者派遣契約である業務委託契約(偽造請負)
- 売買契約・譲渡契約が含まれる業務委託契約
もちろん、これらに該当しない、非常に特殊な業務委託契約もあるでしょう。
また、知的財産権の使用・利用が関係してくる業務委託契約となると、ライセンス契約の要素も含まれてきます。
「業務委託契約書」のタイトル・表題に惑わされない
このように、業務委託契約は、契約内容によって、性質が異なります。
そういう意味では、「業務委託契約書」というタイトル・表題を鵜呑みにしてはいけません。
もっといえば、「業務委託契約書」という契約書のタイトル・表題は、何も表現していないのと同じことです。
業務委託契約書こそ、タイトル・表題ではなく、その内容をしっかりと見極めることが重要です。
定義がないからこそ業務委託契約書が重要となる
このように、業務委託契約は、法律によって内容が決まっていません。
また、一般的には民法上の請負契約か準委任契約に該当します。
しかし、請負契約か準委任契約のどちらに該当するのかは、契約形態の条項で契約内容として規定しなければなりません。
このため、業務委託契約の実務では、業務委託契約書の作成が非常に重要となります。
契約書を作成する理由・目的
業務委託契約は法律の定義がない契約であることから、契約内容を詳細に規定した業務委託契約書が必要となるから。
ポイント
- 業務委託契約には法的な定義がない。
- 一般的な業務委託契約は、民法上の請負契約か準委任契約のいずれか。
- ただし、業務委託契約は、他の契約に該当する場合もある。
- 特に業務委託契約書は、タイトル・表題ではなく、内容で判断する。
内容によって適用される法律・責任が変わる
請負契約・(準)委任契約によって責任の性質が変わる
瑕疵担保責任か善管注意義務が課される
業務委託契約は、内容によって、適用される法律が違ってきます。
すでに触れたとおり、一般的な業務委託契約は、請負契約か(準)委任契約のいずれかの契約です。
これらの契約は、それぞれ、契約不適合責任(旧民法における瑕疵担保責任)または善管注意義務の責任が発生します。
【意味・定義】請負契約における契約不適合責任とは?
請負契約における契約不適合責任とは、仕事の種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合(契約不適合があった場合。瑕疵、ミス、欠陥等があった場合を含む。)において、注文者から請求された、履行の追完、報酬の減額、損害賠償、契約の解除の請求に応じる請負人の責任・義務をいう。
【意味・定義】善管注意義務とは?
善管注意義務とは、行為者の階層、地位、職業に応じて要求される、社会通念上、客観的・一般的に要求される注意を払う義務をいう。
契約不適合責任と善管注意義務の違いは?
契約不適合責任と善管注意義務は、性質がまったく異なる責任です。
契約不適合責任と善管注意義務の違い
- 契約不適合責任の性質:受託者が仕事の結果に対して負う責任。
- 善管注意義務の性質:受託者が仕事の過程に対して負う責任。
このため、業務委託契約では、契約形態を請負契約か(準)委任契約かを決めていないと、特に仕事の結果が失敗に終わった場合に問題となります。
例えば、契約形態を決めていないシステム開発の業務委託契約で、結果的にシステムが完成しなかった場合、次のように、委託側と受託側で主張が対立します。
委託者・受託者の主張
- 委託者(ユーザ):このシステム開発の契約は請負契約だから、システムを完成させる責任がある。よって、システムが完成しないと料金は払わない。
- 受託者(ベンダ):このシステム開発の契約は準委任契約だから、システム開発の作業を提供するだけ。よって、システムを完成させる責任は負わないし、作業の料金を請求できる。
当事者の資本金と業務内容によって下請法が適用される
また、委託者・受託者の資本金の金額と業務内容によっては、下請法が適用されます。
下請法は、正式には、「下請代金支払遅延等防止法」といいます。
下請法が適用される場合、委託者は「親事業者」ということになり、様々な規制や禁止行為が適用されます。
代表的なものとしては、親事業者である委託者は、下請事業者である受託者に対し、下請法第3条にもとづく書面(いわゆる三条書面)を交付しなければなりません。
このため、契約実務では、三条書面の基準を満たすように、業務委託契約書を作成する必要があります。
契約書を作成する理由・目的
下請法が適用される業務委託契約では、親事業者が下請事業者に対し三条書面を交付する義務があることから、業務委託契約書を三条書面として運用するためには、下請法を遵守した契約書が必要となるから。
ポイント
- 請負契約か準委任契約かによって、受託者が果たす責任・義務は、瑕疵担保責任か善管注意義務のいずれかになる。
- 瑕疵担保責任は仕事の結果に対する責任であり、善管注意義務は仕事の過程に対する責任。
- 契約形態を決めていないと、トラブルになった際に、委託者・受託者ともに自分にとって都合のいい主張をする。
- 委託者・受託者の資本金と業務内容によっては、下請法が適用される。
業務委託契約書では業務内容の規定に注意する
業務内容の明確化がトラブルの防止の第一歩
業務委託契約書を作成する際には、業務内容を明確化することが重要となります。
業務委託契約には、さまざまなトラブルがありますが、最も典型的なものは、業務の実施ができたかどうかを巡って、委託者と受託者の間で解釈が割れるトラブルです。
このトラブルの原因としては、もちろん、委託側の要求水準のハードルが極端に高い、あるいは、受託側の業務の実施能力が極端に低い、ということもあり得ます。
しかし、通常は、そもそも業務内容が曖昧であるために、当初想定した「業務の実施」が何なのかが決まっていない、という点に問題があります。
このようなトラブルを防止するためにも、なるべく業務内容は、一義的かつ客観的に規定するべきです。
できるだけ検査仕様も決めておく
また、業務内容が曖昧な場合、実施された業務が検査に合格するかどうか、という点でもトラブルになります。
大半の業務委託契約では、実施された業務について検査がおこなわれます。
この検査でも、業務内容の問題点と同じく、実施された業務が合格か不合格かを巡って、委託者と受託者が揉めることがあります。
このため、なるべく、業務委託契約では、明確な検査仕様(検査項目・検査方法・検査基準)を決めておき、一義的かつ客観的な検査ができるようにしておくべきです。
なお、業務委託契約書について、さらに詳しい情報をお求めの場合は、姉妹サイト「業務委託契約書の達人」をご覧ください。
ポイント
- 業務委託契約書では、業務内容を明記することで、契約当事者間のトラブルを予防できる。
- なるべく検査仕様(検査項目・検査方法・検査基準)を決めておくことで、検査結果の合格・不合格を巡るトラブルを予防できる。